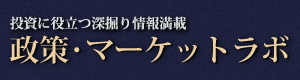英・独・仏はイランの核開発問題を交渉で解決したいという強い思いがあり、3ヵ国でイランとの交渉を行おうとしていたが、米国が強く反対をしていた。
米国のブッシュ大統領は、2002年の一般教書でイランをイラク、北朝鮮と並ぶ「悪の枢軸」と名指しをしていた。欧州諸国は米国を翻意させるべく、日本に役割を果たしてくれという。
米国側の私の交渉のカウンターパートは今、国家安全保障担当大統領補佐官として対イラン強硬派で名をはせるジョン・ボルトン国務省軍縮・不拡散担当次官だった。
その時は、米政権内は対イラン強硬論一色ではなく、穏健派といわれたアーミテージ国務副長官に働きかけを行い、パウエル国務長官を動かして、欧州3ヵ国によるイランとの交渉開始にG7としてお墨付きを与えることに成功した。
だが、その時のボルトン次官の不快感に満ちた言動を今でも思い出す。
15年後の今、ボルトン補佐官は自己の信念を貫こうとしているということだろうか。
イランの核問題の解決には、レジーム・チェンジ(政治体制の変更)しかないというのがボルトン補佐官の持論といわれる。
根強い反イラン感情
「体制自体が脅威」
米国はその後、オバマ政権下で自ら参加して核合意をまとめ制裁を解除した。米国はトランプ政権下で、何故かくも強硬な対イラン政策に変わったのだろう。
トランプ政権は国連常任理事国5ヵ国プラス独とイランの核合意は核開発のスピードを緩めただけで不十分とし、合意から離脱し、石油も一定期間の猶予後、完全に輸入を禁止する措置をとった。
米国はイランに核開発をやめさせるために「最大の圧力」政策をとるとし、イランの革命防衛隊をテロ組織と認定した。さらに6月13日に起きたオマーン湾でのタンカー攻撃事件を間髪入れずイランの所業と断定し、米軍の増派をただちに決めている。
こうした対イラン強硬政策の根底には、根強い反イラン感情がある。
1979年のイスラム革命の際、イランを離れたパーレビ皇帝を受け入れた米国にイラン側が激怒して、米国大使館員が1年以上人質に取られたいわゆる「イラン人質事件」の爪あとは色濃く残る。