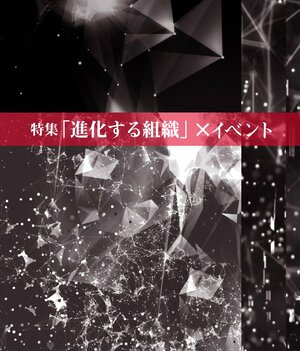「プロセスエコノミー」は発明ではなく「イノベーション」
高宮 よく「発明とイノベーションは違う」という話があると思います。
ライト兄弟が飛行機を発明しましたが、その発明によって、国をまたいで「飛行機で旅行すること」が一般に普及したわけではないんですね。
尾原 確かに。彼らは「飛ぶという機能」を発明しただけですよね。
高宮 商業用として「世の中に普及させた人」が「イノベーションを起こした人」なんですね。
純粋に「ビジネスとして」という意味でいうと、「発明する必要なく、イノベーションを起こせばいい」のです。イノベーションを起こして、社会やユーザーに対して「新しい価値」を差分として作り出したときに、その差分の分だけお金がもらえるのだと思っています。
つまり、必ずしも本当に「ゼロベース」で発明する必要はないんです。もちろん、発明からイノベーションまで、一気通貫できた方が、より大きな価値を出し、その対価を受け取ることができるのですが、難易度は上がります。
尾原 ある兆しの中で初めに動きだせば、ユーザーがその上で、スケーラブルな(拡張性のある)新しいイノベーションを起こしていきますよね。そこにちゃんと気付いて、「加速できるのか」「戦略を集中できるのか」ということですね。
高宮 「プロセスエコノミー」の話から「インターネットの長い時間軸」や「ビジネスモデル論」まで、膨らんでしまいましたが、大丈夫でしたか?
尾原 いやいや。まさに、お聞きしたかったことを聞くことができました。『プロセスエコノミー』の書籍の中でも「エフェクチュエーション(起業家の共通する思考プロセスや行動様式)」の話をしていますが、変化の時代に大事なことは、「発明的にこれをするんだ!」と決めると、逆に変化に気付けなくなることなんです。
初めに決めた戦略は、変化に気付けず戦略にふたをしてしまいますが、後から立ち上がってくるイノベーションに気付いて、そこにフォーカスした方が大きくなれます。つまり、「プロセスエコノミー」時代において、大きなイノベーションを作っていくには、「いろんな人を巻き込みながら、一緒にプロセスを作っていく」ことが大事だと思っています。
高宮 「プロセスエコノミー」は、完全に「イノベーション」だと思うんですよね。
何か新しいテクノロジーを発明したわけでも何でもないんだけど、既に世に普及しているテクノロジーを組み合わせて、「今まで見過ごされていた価値」や、「商業ベースに乗っていなかった新しい価値」を普及させたのが「プロセスエコノミー」だと思います。