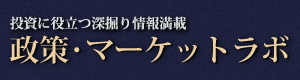Photo:123RF
Photo:123RF
ロシアによるウクライナ侵攻は、これまでの資源高に拍車をかけた。資源高による企業収益の圧迫を回避しようと、燃料価格の上昇分を販売価格に反映する「サーチャージ制」を導入する流れが各企業で強まろうとしている。(マーケット・リスク・アドバイザリー共同代表 新村直弘)
資源高でコストを圧迫
“価格上乗せ”サーチャージ制導入の流れ
足元の資源価格の上昇がコストアップ要因となり、企業収益を圧迫している。
生産に関わるコストのうち、燃料や光熱費の上昇分をコストとして販売価格に上乗せするのは難しく、売り手側がそのコストを負担することが多い。
突発的なリスクが顕在化して一時的に価格が高騰(または下落)した場合、売り手と買い手の間で価格交渉が行われて、値上げ(または値下げ)の落としどころを探るというのが一般的だ。
しかし、足元の資源高は、企業がその上昇分を自己負担できないほどのレベルに達している。2021年度の原油価格(TOCOM原油価格)の平均は5万4973円/KLだった。これに対し、2022年度の平均価格は原稿執筆時点で8万7924円/KLと、前年度に比べてほぼ6割も上昇している。
総務省が令和2年8月に発表した産業連関表を基にすると、エネルギーコストの費用に占める比率は9.7%。21年度から22年度の原油価格の上昇を当てはめると、その企業が節電や省エネなどの対策を行っていなければ、トータルで16%のコストアップになったということになる。
このコストアップは、さすがに許容できる範囲ではないといえる。
このため日本企業は、自社の自助努力で吸収仕切れない市場価格の変動リスクを顧客に転嫁する動きを強めざるを得なくなっている。
代表的なのが、原材料や燃料の価格上昇分を上乗せする「サーチャージ制」だ。足元の資源価格の上昇を受けて、各企業がサーチャージ制を導入する流れが強まっている。今後、こうした資源価格の上昇分は、最終価格に転嫁されることが予想される。