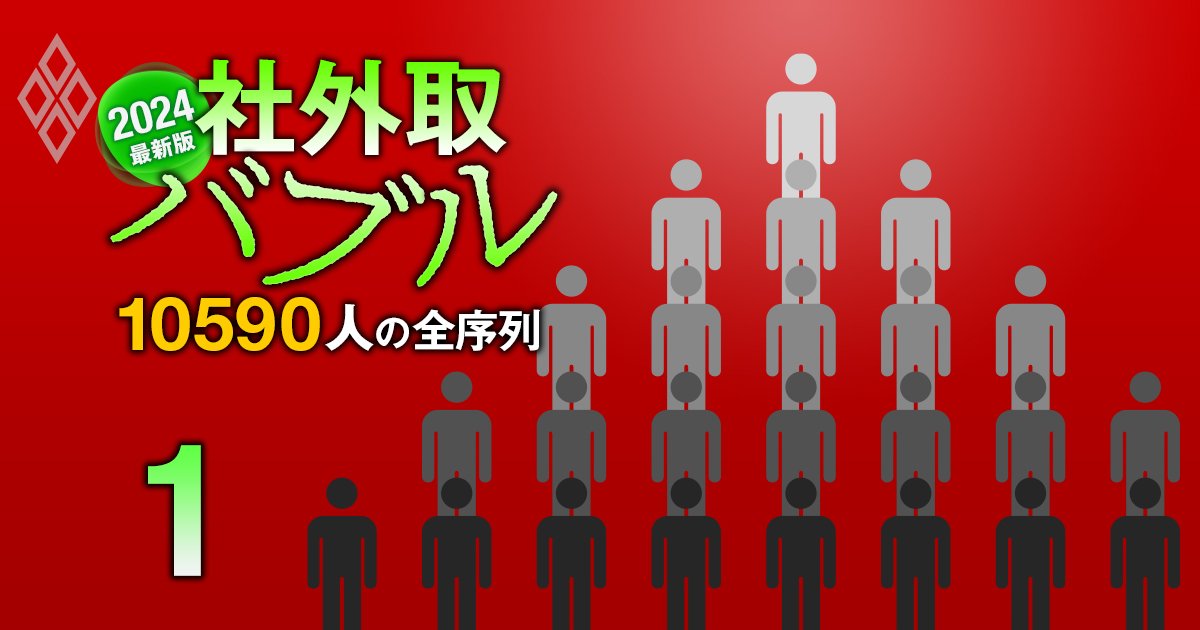東京五輪組織委員会の会長が“女性蔑視”発言で辞任したり、開会式の演出を担当したミュージシャンや演出家が過去の「差別」問題で辞退・解任された出来事で、日本でも「キャンセルカルチャー」という言葉が広く知られるようになった。
キャンセルカルチャーに確立された定義があるわけではないが、ここでは「社会正義に反する言動をした者に対し、法的な手段ではなく、SNSなどを使った大衆行動(バッシング)によって、社会的地位をキャンセル(抹消)する運動」としよう。こうしたキャンセルを先導する者は、揶揄を込めて、「ソーシャル・ジャスティス・ウォリアー(SJW:社会正義の戦士)」と呼ばれる。
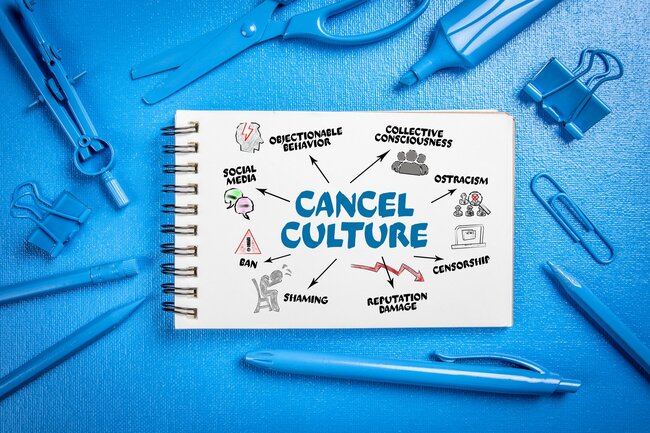 イラスト:stoatphoto / PIXTA(ピクスタ)
イラスト:stoatphoto / PIXTA(ピクスタ)
アメリカの大学では、社会正義を掲げる学生たちによる過激なキャンセルが常態化しており、それが学問や言論の自由を傷つけ、社会に深刻な害悪を与えている――そう警告するのが、ジョナサン・ハイトとグレッグ・ルキアノフの『傷つきやすいアメリカの大学生たち 大学と若者をダメにする「善意」と「誤った信念」の正体』(西川由紀子訳、草思社)で、2018年の発売直後からアメリカでは大きな話題になった。原題は“The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure(アメリカン・マインドの甘やかし 善意と愚かな考えが如何にして傷つき世代をつくりだしたのか)”。
「甘やかされた子どもたち」がキャンパスに押し寄せた
ジョナサン・ハイトはアメリカの著名な社会心理学者で、『社会はなぜ左と右にわかれるのか 対立を超えるための道徳心理学』(高橋洋訳、紀伊國屋書店)などで、伝統や文化、共同体などを全否定する過激なリベラル(左派)を批判した。思想的にはリベラル右派(共同体主義者:コミュニタリアン)で、右翼(白人至上主義)ではまったくない。
グレッグ・ルキアノフはジャーナリストで、FIRE(The Foundation for Individual Rights and Expression:個人の自由と表現のための財団)の代表者。FIRE(「経済的独立・早期リタイア」のことではない)は超党派の非営利組織で、大学における「権利、言論の自由、適正手続き(デュー・プロセス)、学問の自由」を守る活動をしている。
大学内のキャンセルカルチャーを批判するFIREは一般に「保守派」と見なされるが、フロリダ州の「ストップWOKE法」に対しては、言論の自由を制限し、憲法修正第一条(「連邦議会は(略)言論若しくは出版の自由、又は人民が平穏に集会し、また苦痛の救済を求めるため政府に請願する権利を侵す法律を制定してはならない」)に反するとして連邦裁判所に訴訟を起こし、勝訴している。
ちなみにWOKE(ウォーク)は「社会正義に目覚めたひとたち」のことで、日本の「(社会問題に)意識高い系」と同じく、揶揄として使われる。「ストップWOKE法」では、州内の企業や教育機関に対して、人種やジェンダー、環境問題など、社会正義についての特定の主張を従業員や子どもたちに教える(あるいは「洗脳する」)ことを違法とした。保守派が推進するこの法律に反対したことからわかるように、イデオロギーとしての“正義”よりも言論の自由を優先するルキアノフ(FIRE)は「リベラル」の陣営に属している。
本書の原題(『アメリカン・マインドの甘やかし:The Coddling of the American Mind』)は、1987年にベストセラーとなった哲学者(古典文献学者)アラン・ブルームの『アメリカン・マインドの終焉:The Closing of the American Mind』からとったものだ。ブルームはこの本で、大学が(西洋の古典を教える)教養主義を放棄し、分析哲学やポストモダン哲学の相対主義(脱構築)に傾斜したことで、健全なる「アメリカの精神」が失われつつあると論じた。ハイトとルキアノフは、それから30年超を経て、いまやアメリカの大学は「社会正義」の思想に席巻されていると警告する。その背景にあるのが、「甘やかされた子どもたち」がキャンパスに押し寄せたことだ。ハイトとルキアノフは、次のように述べる。
大学というのは、不愉快なものやあからさまに敵意に満ちたものも含めて、多様な人々や思想と向き合える、この世で最高の環境ではないのか。高度な設備、有能なトレーナー、万が一のためにセラピストまで待機している、究極の〈知のジム〉である。
それにもかかわらず近年の大学は、人種やジェンダーの問題でマイノリティの学生の感情を傷つけることを極端に恐れるようになった。リベラル化する社会では、トラウマを負わせるような経験をさせることは、どのような理由でも許されないのだ。
『甘やかされた子どもたち』を象徴しているのが、近年の大学キャンパスに登場した「セーフスペース」だ。名門ブラウン大学(ロードアイランド州:アイビーリーグのひとつ)では、〈アメリカはレイプ文化の国〉という左派の主張を批判する講演を聞いて「トラウマ体験を思い出してしまった者たちが静養し、サポートを受けられる」場所(セーフスペース)を学生たちが設置した。そこには「クッキー、塗り絵本、シャボン玉、粘土セット、ヒーリングミュージック、枕、毛布、子犬が元気に走り回る映像などが用意され、トラウマ対処法の訓練を受けたとされる学生やスタッフまでが待機していた」という。
著者たちは、こうした安全への過度な配慮がかえって学生たちを脆弱にしていると批判する。子どもたちをピーナッツに触れさせないようにすると、逆にピーナッツアレルギーが増えるのと同じパラドックスが、アメリカの大学で起きているというのだ。