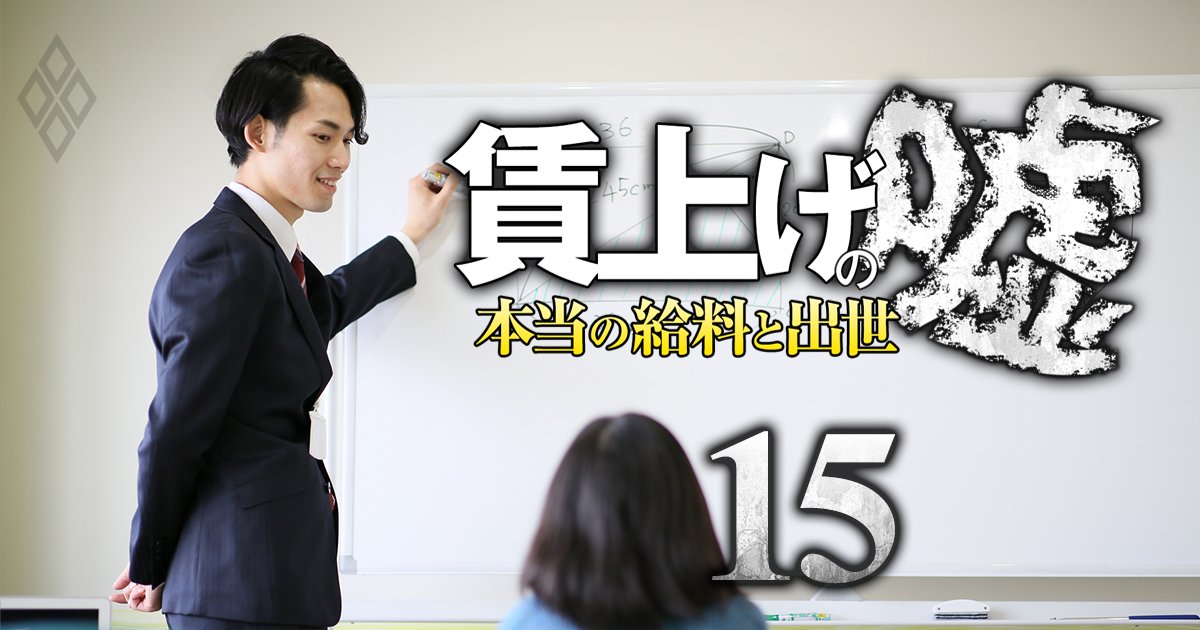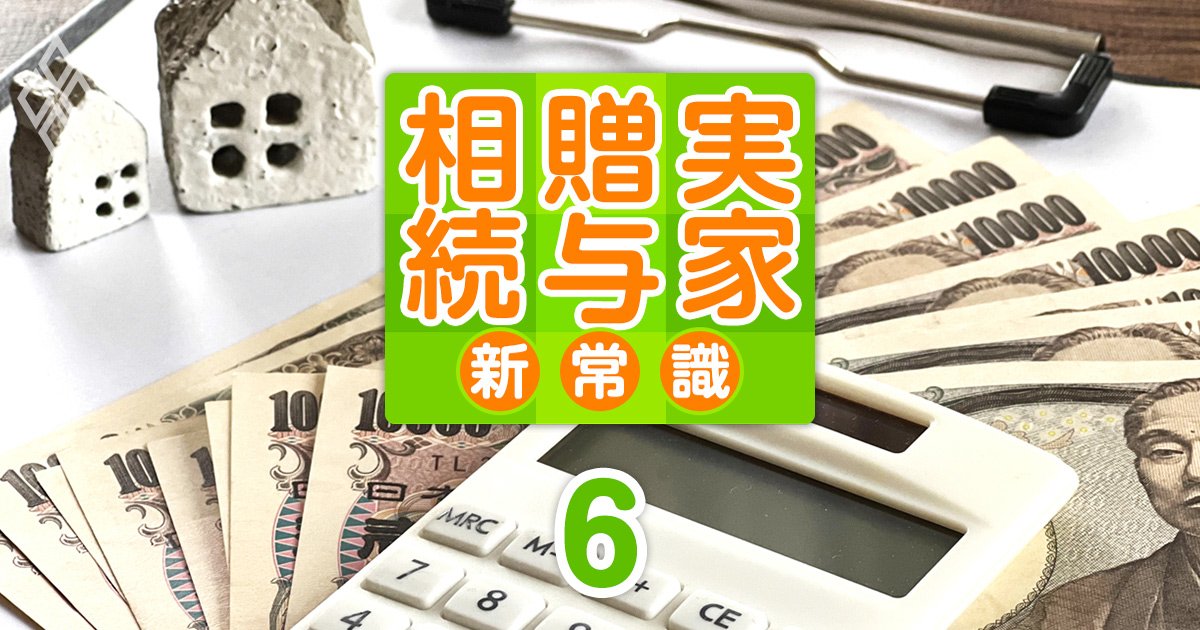「使うか、使わないか」から「いつ、どのように使うか」へ
しかし、もはや「AI技術を使わない」という選択肢はなく、止めようとしても止められないところまで来たといえる。
「いつ使うか?」は「今」であり、「どのように使うか?」は、業種によっていろいろだ。プログラミングの代行やサポートをさせたり、(自分でも精査するという前提で)企画書や論文のための情報調査・骨子生成に使ったり、データから表やグラフを生成したり、動画・音声から自動で文字起こし→文章の整形→要約を行ったり、ラフスケッチからWebページを制作したり……こうした作業であれば、仕事に役立つ有能なツールとしてAIを活用できるはずだ。
そして、筆者がAIの進化によって再びブームが起こる、というより、一般生活者の間で今度こそ定着していくのではと考えているのが、スマートスピーカーである。これまでのサービスでは、主に音声認識の部分でAIが使われ、その後の処理は、WebやECサイト内の検索結果を合成音声で返したり、決められた手順を呼び出してスマート家電をコントロールしたりする程度だった。そのため、結局は定型的な処理にしか利用されず、今に至っている。
たとえば、Echoデバイスを通じて商品の発注が増えると考えたアマゾンのもくろみも失敗し、Alexaのハードウエア部門の赤字は年間約1兆4000億円といわれる。同様に、グーグルもGoogleアシスタント事業で同じような目に遭ってきた。
確かに、音声のみのコミュニケーションでECサイトのような一覧性もなく、言われた注文を受けるだけのスマートスピーカーでは、要領を得ない御用聞きと同じで、商品の販売促進にはつながらない。しかし、ユーザーの希望を聞いて相談に乗り、的確なギフトのアドバイスや、より生活を豊かにしてくれる製品の提案を行ってくれるとしたらどうだろう? 優秀なカスタマーサービスやコンシェルジュが電話の相手をしているようなもので、顧客のエンゲージメントも高まり、商品の購入につながるコンバージョン率も向上するはずだ。
 左はAmazon、右はGoogleのスマートスピーカー。チャット系AIは、普及台数は多いがビジネスとしては不振が続くスマートスピーカー復権の原動力となる可能性がある
左はAmazon、右はGoogleのスマートスピーカー。チャット系AIは、普及台数は多いがビジネスとしては不振が続くスマートスピーカー復権の原動力となる可能性がある
そのほかの処理でも、チャット形式のやりとりは、タイピングよりも音声を介するほうがはるかに楽であり、レスポンスをテキストやイメージなどで返すことが適する場合には、今のスマートスピーカーもそうであるように、そうした情報をコンピューターなどのデバイスに送ってくれればよい。もちろん企業ユースでは、AIとの音声チャットを含めて、すべてをコンピューターやタブレット上で行うことが理にかなっているが、一般家庭では、こうしたスマートスピーカーの再興が起こっても不思議ではない。
その場合、実はEchoデバイスはアマゾンでも最も売れている商品の一つ(ただし、価格≒原価のため利益にならない)なので、巨大なインストールベースがある。したがって、クラウド側のAlexaのAI性能を向上させるだけで、この市場を押さえられる可能性が高い。グーグルも似たようなことを考えているはずだ。