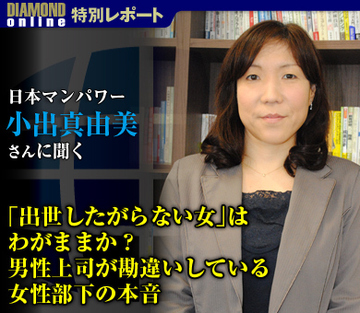政府は今年6月に示した新しい成長戦略のなかで、「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%以上」との目標を掲げた。一方、現在の日本における女性管理職の比率は11%に過ぎず、目標との乖離が著しい。では一体なぜ、日本では女性の管理職が増えないのだろうか。その背景には「日本の労働市場の疾患」があり、「この疾患を解決しなければ女性管理職は少ないままだ」と八代尚宏・国際基督教大学客員教授は指摘する。
「女性管理職比率11%」の意味
 やしろ・なおひろ
やしろ・なおひろ国際基督教大学客員教授・昭和女子大学特命教授。経済企画庁、日本経済研究センター理事長等を経て現職。著書に、『新自由主義の復権』(中公新書)、『規制改革で何が変わるか』(ちくま新書)などがある。
Photo by Toshiaki Usami
6月の「日本再興戦略」で示された成長戦略の柱のひとつに「女性の活用」があり、「社会のあらゆる分野で2020年までに指導的地位に女性が占める割合を30%以上」との目標が掲げられている。しかし、2012年現在の日本の女性管理職比率11.1%は、米国43.7%、フランス39.4%の欧米主要国や、フィリピン47.6%、シンガポール33.8%のアジア主要国と比べても、著しく低い水準にある(労働政策研究・研修機構)。こうした状況の改善を、政府が数値目標として掲げたことには大きな意味がある。
企業の課長相当職以上の女性比率を企業規模別にみると、従業員10~29人規模の16.5%に対して、5000人以上規模で4.0%と大きな差が見られる。とくに大企業で管理職の女性が少ない原因は、個々の女性を差別しているわけではなく、もともと管理職の年齢層に女性が少なく、相応しい人材に乏しいためという(厚生労働省「雇用機会均等調査(2013年度)」)。
しかし、これは日本的雇用慣行における内部昇進を前提とした論理である。現行の仕組みのままで、あと6年間のうちに女性管理職比率を3倍にすることは、きわめて困難である。むしろ、企業内部に管理職に相応しい人材がいなければ、外部から登用すれば良い。そうなれば、企業経営に重要な役割を果す管理職を、男女、年齢、国籍にかかわらずオープンにすることにも結びつく。これは、もっぱら内部昇進で管理職になる、従来の人事管理のあり方自体の改革となり、それが実現してこそ、成長戦略に貢献するものといえる。
これには企業の自主努力だけでなく、政府の役割も重要である。解雇に伴う金銭補償ルールの確立や、時間ではなく成果に基づく賃金制度は、暗黙のうちに男性世帯主を保護する現行制度の改革でもある。女性管理職比率がどこまで高まるかは、労働市場改革の成果を図るリトマス試験紙といえる。