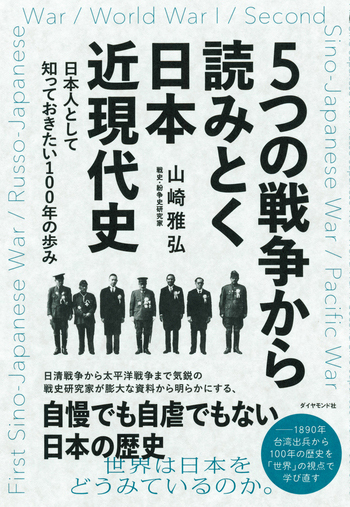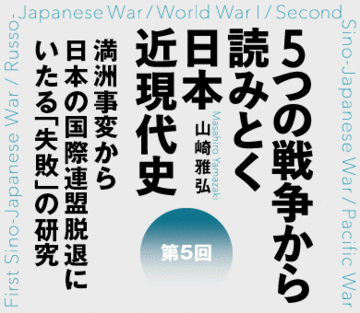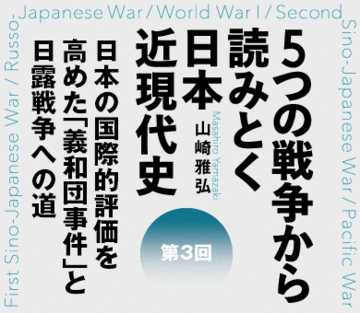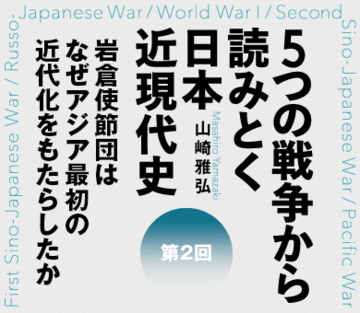近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5000部突破の気鋭の戦史・紛争史研究の山崎雅弘による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第6回は日中戦争の収拾に尽力したドイツと、それを水泡に帰した日本の辿った道筋を解説します。

日中戦争の収拾に尽力したドイツ
小規模な銃撃戦に過ぎなかった盧溝橋事件が、瞬く間に日中間の全面的な軍事衝突へと発展した時、欧米各国はどのような反応を示したのでしょうか。
イギリスは日中戦争をできれば回避したいと思っており、紛争が拡大すると「仲介役をする用意がある」と日本側に申し出ました。しかし、日本陸軍は、イギリス政府は中国関連の問題において、中立ではなく「中国寄り」だと見なして不信感を募らせていたため、日本政府もイギリスに和平の仲介を頼むことはしませんでした。アメリカは、1920年代末の恐慌の後遺症からまだ立ち直っておらず、日本との貿易を継続するため、日中の戦いでは傍観者という立場をとっていました。北の大国ソ連は、日本軍が満洲からシベリアや沿海州へと攻め込むことを恐れていたため、中国軍と日本軍の戦いが長期化することを内心で歓迎しており、和平の仲介には無関心でした。
こうした状況の中で、近衛政権が仲介役として選んだのは、ドイツでした。1933年にナチ党(正式名称は国家社会主義ドイツ労働者党)の指導者アドルフ・ヒトラーが権力の座についていたドイツは、1930年代前半には国民軍に軍事顧問を派遣するなど、国民政府との軍事的な繫がりを持っていました。しかし、1936年11月25日に日独伊防共協定が締結されると、ドイツの中国および極東アジア政策は、日本との同盟関係を重視することによる政治的利益を優先する方向へと見直されていました。
上海方面での本格的な日本軍の攻勢が始まる以前の1937年10月1日、近衛は主な大臣と相談して、中国側に提示する「和平の条件」を策定し、それを11月2日にドイツの駐日大使ディルクセンに伝えました。ディルクセンから内容を知らされた駐華大使トラウトマンは、11月6日に蔣介石と面会して、日本の条件を説明しました。これを聞いた蔣介石は、最初は和平提案を拒絶したものの、やがて考えを変え、日本軍が南京へと迫りつつある中で、もし日本側が中国の領土保全を約束するなら、先の条件で和平を受け入れてもいい、とトラウトマンに答えます。
この時が、日中戦争を交渉で解決できたかもしれない、最大のチャンスでした。トラウトマンはさっそく、この内容をディルクセンに伝え、日本政府の決断に期待しました。しかし結局、後に「トラウトマン工作」と呼ばれることになるドイツの和平交渉は、実を結ばないまま立ち消えとなってしまいます。その原因は、南京陥落後の12月21日に、日本側が新たな和平条件を策定して、条件を吊り上げたことにありました。日本政府は、上海および南京方面で軍事的な大勝利を収めたこと、その過程で予想外の損害を被って大勢の日本兵が死んだことを理由に、「十月に策定したような和平条件では軍や国民が納得しない」と考えて、賠償金の要求や日本軍部隊の駐留範囲の拡大など、中国側が受け入れられないほど強硬な要求を上乗せしました。
そして、中国側の回答期限を1938年1月15日と定め、蔣介石が返答しないのを見た近衛政権は、1月16日に「今後はもう国民政府を対手(戦争終結の交渉相手)とは見なさない」という、捨て台詞のような声明(第一次近衛声明)を居丈高に発表して、蔣介石との交渉を打ち切ってしまいます。これにより、ドイツの和平工作は水泡に帰し、日中戦争の終結は大きく遠のきました。
日中戦争はなぜ泥沼化したのか
実際の南京陥落から2日前の1937年12月11日、日本の新聞によって華々しく報じられた「日本軍の南京占領」というニュースに沸き立った日本国民は、東京の銀座などで「祝賀パレード」を行い、中学生や高校生も動員されて提灯行列に加わりました。
多くの日本国民は、敵国の首都を攻め落としたのだから、これで日中戦争に決着がついたと思い、自国の大勝利を信じましたが、戦争が終わる兆しは全くありませんでした。中国軍が、日露戦争の奉天会戦のような、日本軍が望んだ「決戦」に応じず、不利になると退却して日本軍部隊を奥地へと引き込むという戦略をとったこともあり、見かけ上は日本があらゆる場所で「勝っている」かに見えました。実際、前線での戦いではたいていの場合は日本軍が勝利しており、威勢のいい新聞報道が国民の意気をさらに高めました。
しかし、当時の日本軍は1960年代後半のベトナム戦争におけるアメリカ軍と同様、「個々の戦闘での勝利」を、どうすれば「戦争全体の勝利」に結びつけられるのかという問題について、明確な答えを持ち合わせていませんでした。日本軍が個別の戦場で軍事的(戦術的)に勝利を収めても、自国が不当に侵略されていると考える中国人の日本への敵意や戦意は高まるだけで、政治的にはどんどん日本軍が不利な状況になっていたのです。こうした戦況の停滞と並行する形で、日本国内の政治状況も、国民にとって次第に厳しいものになっていきました。日本政府と陸海軍は、日中戦争という国家的な一大事を利用する形で、予算の獲得や権限の拡大などを法制化し、国民の負担を増大させました。
1937年9月の第72臨時国会で、日露戦争の全戦費を上回る20億2200万円の臨時軍事費が、わずか1日の審議で可決され、軍事費関連など11本の法律案も原案通り可決しました。10月25日には、総力戦体制を整えるとの名目で、資源局と企画庁が統合されて内閣直属の「企画院」が設立されましたが、この組織が中心となって、1938年3月に「国家総動員法」が帝国議会で可決され、四月一日に公布されました。
国家総動員法とは、あらゆる物資の統制運用と国民の徴用、労働条件の変更などを、政府(内閣)が必要だと判断すれば法律がなくても独断で決定して、国民を従わせることができるという「非常委任立法」でした。この法案の内容が明らかになると、時の政権に過大な権限を与えるものだとして、国民の間から批判や抗議の声が高まりましたが、政府と軍は「前線の兵士が命をかけて戦っている時には、後方の国民も財産権や憲法にこだわらず、全てを国に捧げるのが当然だ」として、採決を押し通しました。
報道の自由については、1937年7月31日の陸軍省令と8月16日の海軍省令、12月13日の外務省令によって、新聞が書いてはいけない禁止事項が拡大され、情報の統制が強化されました。12月14日には、右派の海軍大将である末次信正が警察機構を司る内務大臣に就任し、反戦や政府批判を口にする人間への弾圧も強まりました。
1938年に入り、日中戦争が完全に泥沼化すると、日本経済には暗い影が落ち、物資の統制が強化されました。一般向けの日用品から鉄が姿を消し、羊毛や木綿、革なども、軍需(軍隊の需要)が優先されて市民の手には渡らなくなりました。1939年には物価の高騰が人々の生活を直撃し、食料や燃料が深刻なレベルで不足して、1940年になると米の配給制が各地で始まりました。1938年10月に行われた武漢(武昌、漢口、漢陽の三都市)攻略作戦以後、日本軍は大規模な攻勢作戦の続行をあきらめ、占領地の維持による持久戦態勢へと移行しました。
そして、1939年末以降は、軍事作戦で中国を屈服させる見込みが完全になくなったため、人員面や資金面での戦争の負担を軽減する目的で、中国戦線の兵力を縮小する方針をとるようになりました。中国戦線における日本軍人の死傷者は、1941年までには50万人に達していましたが、日本政府も軍の指導部も、どうやってこの戦争を終わらせたらよいのか、糸口を見つけられないでいました。実際には、彼らの「見通しの甘さ」と「判断ミス」こそが戦争長期化の原因でしたが、彼らが自分たちの間違いを認めることはありませんでした。