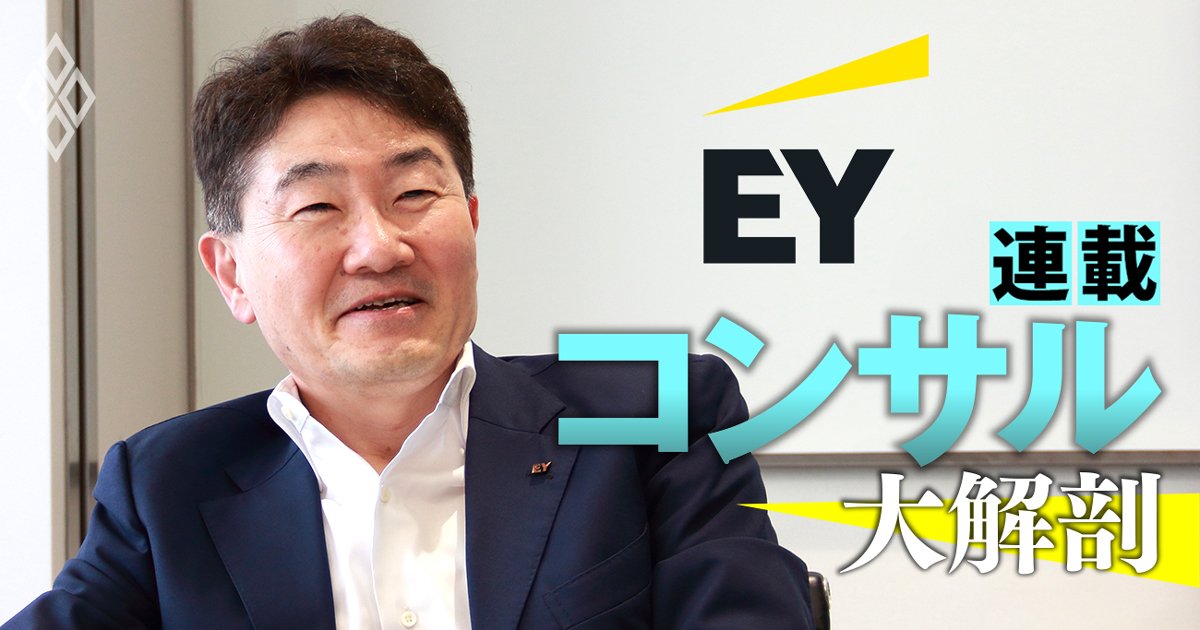シニア社員の定年後の虚無感を描き、異例のヒットを飛ばしている『孤舟』(渡辺淳一著、集英社刊、税別1600円)。
シニア社員の定年後の虚無感を描き、異例のヒットを飛ばしている『孤舟』(渡辺淳一著、集英社刊、税別1600円)。大海の波間を漂う“孤独な舟”を意味する『孤舟(こしゅう)』。昨今、人生にさまよう“孤舟族”が大量に生まれているのをご存じだろうか?
恋愛小説の大家、渡辺淳一氏が御年76歳にして今秋発表した小説『孤舟』(集英社)が、ヒットを飛ばしている。不振に喘ぐ文学界においては、異例の10万部超えを早々に実現し、男性ビジネスマンはもとよりOLや主婦層からも喝采を集めているのだ。
あらすじはこうだ。大手広告代理店の上席常務執行役員まで上りつめた主人公・威一郎は、定年退職の日を迎える。趣味に家族サービスに勉学にと、「第二の人生」の夢を描いていた彼の目論見は、早々に崩れ去る。そこに待っていたのは、「何もすることがない」という悪夢のような現実。そして、「耐え難いほどの長さ」である1日を無為に重ねることになってしまう。
そこで描かれる彼の苦悩は、なんとも切実だ。「昔の部下の前では、精一杯背伸びをして強そうに見せる」「朝から犬を連れて散歩している自分が、いかにも職を失った惨めな老人になったような気がしてならない」「現役時代よりも約半分に減ってしまった年賀状の数に落ち込む」――思わず身につまされるようなリアルさだ。
さらに大きな誤算だったのが、妻との関係悪化。専業主婦である妻は、「主人在宅ストレス症候群」から心身のバランスを崩し、ことあるごとに威一郎と衝突してしまう。そんな彼女をなだめすかそうと、夫が珍しく料理を作れば、「女の城」であるキッチンを荒らされた妻は憤慨し、「もう料理はしてくれるな」と言い渡す始末である。
本書の核をなすテーマの1つに、主人公が団塊世代であることも挙げられる。熾烈な競争社会を生き抜いたその先に待っていたのは、「定年」という現実。会社を晴れ晴れと去ったものの、降りかかってきたのは「職を失った侘しさと虚しさ」だ。
かくいう筆者も、間もなく古希を迎える自分の父親が、今なお“男の沽券”に執着し続け、現役時代と何ら振る舞いを変えない姿を目にし、思わず憐憫の情を抱いてしまうことがある。男というものは、かくも生きにくいものなのか……。そんな彼らがどこか滑稽であり、どこか哀切に思えてしまうのは、“社会的な生き物”として生まれてきた宿命なのか。
プライドや矜持と、孤独とは背中合わせである。この小説の最後では、威一郎の再生が描かれており、読後感は非常に爽やかだ。それは、彼が現実を素直に受け入れ、等身大の自分を愛し、周囲を愛することができるようになったから。七転八倒の末、ようやくその境地に至った彼は清々しい。
本書が執筆されたのは、作者の渡辺氏が周囲から威一郎と同様の悩みを数多く聞くようになったことがきっかけだそうだ。定年という現実に対して、シニカルに警鐘を鳴らしつつ、その実、渡辺氏ならではの男性たちへの温かいエールに溢れている気がしてならない。人類が初めて直面するという「超高齢化社会」を生き抜くための福音とも呼べる書の1つであろう。
(田島 薫)