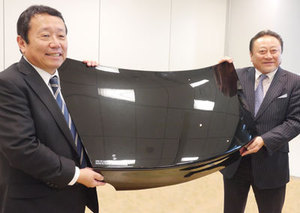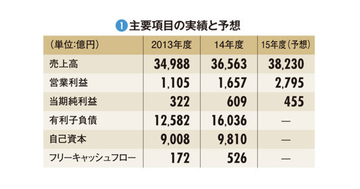「企業」とは、なんだろうか。事業を通じて人と社会に対して企業はどのような責務を持ち、変革に寄与していかなければならないのか。私自身の人生観とも重ねながらまとめてみようと思う。(三菱ケミカルホールディングス会長 小林喜光)
 Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
理屈なしに生きることの啓示を受けたシナイ砂漠での経験
それは生きることへの強烈な原体験になった。シナイ半島に広がるシナイ砂漠。黒いショールをまとった女性が、数匹の黒い羊を引き連れてオアシスに向かって歩いてくる。
乾ききった砂漠とぎらつく太陽だけの無音の世界で、女性と山羊だけが強烈な命のオーラを発していた。「どうしてこんな場所で生きていくのか」という疑問の前に、「これが生きることの凄さなのか」と圧倒された。私の人生は、その瞬間から始まったと言ってもいい。
1971年に東京大学で相関理化学という物理学や化学、生物学などの枠を超えた学際分野の大学院修士を修了した私は、博士課程1年のときにイスラエルのヘブライ大学物理化学科に国費留学した。
東京大学在学中は70年安保を前にした大学紛争の真っただ中で、学部4年生のときには安田講堂が占拠され、卒業する年の1月に機動隊投入による壮絶な衝突を経て封鎖が解除された。
当時は旧来の日共に加え、中核や革マルなどの新左翼各派や全共闘運動の全盛時だったが、私はそうした活動に興味が持てなかった。当時の若者たち、つまり団塊世代の多くが感じていた社会への疑問と私が感じていた違和感は、少し違っていたのかもしれない。
満員電車に揺られて人生を終える。そのことにいったい何の意味があるのか。常に自由でありたいと思い、束縛されるような生き方は拒否する。サラリーマンになって自分の能力を売って一生を終えるなど許しがたいことだと感じていた。
そうした思いを抱いていた頃に刊行されたのがイザヤ・ベンダサン(山本七平)の『日本人とユダヤ人』だった。安全と水はただと思っている日本人の感覚と、真逆の歴史にあるユダヤ民族の苦悩が比較され、また、ユダヤ人に「ユダヤ教」があるように、日本人にも「日本教」があると語られるなど、日本人と対置されるユダヤという民族に興味を抱いた。
ユダヤ人のいる国。「ただただ、その場所に行ってみたい」と思った。15歳の頃から、「人はなんのために生きていくだろう」と悩み始め、大学への進学でも「文系に行けば、思索が錯綜して作家のように自死に至る隘路にはまりかねない。理系ならば1足す1は2という明確な論理や答で無理やり自分を納得させられるだろう」と道を選んだものの、私はまだ自分を満足させられる答を見いだせずにいた。
黒ショールの女性と黒い山羊。そこには、生きている凄さ以外のいっさいの解釈の余地はなかった。無の中に動くものがあるという美しさ。「とりあえず、やっぱり生きてみるか」。私の思いも、解釈の余地などない単純なものだった。
それは啓示なのだ。砂漠と太陽だけの苛烈な自然のなかで、かつてムハンマドが啓示を受けたように、日々の暮らしへの疑問に満ちた一人の若者が啓示を受けた。
勤め人になって何度もくたびれ、辞めたいと思ったときも、そのたびに、あの時の情景が思い浮かばれ、「もう少し頑張ってみるか」という気になった。
エルサレムには、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つの聖地があり、同じ場所を聖地にしながら3つの宗教は長い間、戦いを繰り返してきた。人間の業とも言えるようなどうしようもなさ。と同時にそれは、人類の歴史や思考の深さや重みを強烈に感じさせる場所でもあったのだ。