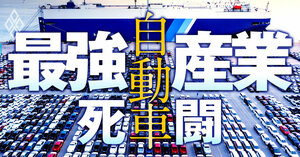ポピュラー音楽の本場であるアメリカ・ハリウッド。その最前線で活躍する一人の日本人がいる。レコーディングエンジニア・プロデューサーSADAHARU YAGI。ヤギ氏は2014年、ドラコ・ロサのアルバム「VIDA」の制作に携わり、世界で最も権威ある音楽賞であるグラミー賞を「ベスト・ラテン・ポップ・アルバム」部門で受賞した。高校時代から、いずれはアメリカで活躍し、グラミー賞を獲得することを夢見ていたヤギ氏。大学卒業後、単身、アメリカに乗り込み、下積みから地道に這い上がってつかんだ栄光だった。ポピュラー音楽の本場でつかんだ「仕事の本質」とは何か? 話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド社 田中 泰、構成/前田浩弥)
 グラミー賞を受賞した黄金コンビ、ドラコ・ロサ(左)とヤギ氏 Photo by Gianni Neiviller
グラミー賞を受賞した黄金コンビ、ドラコ・ロサ(左)とヤギ氏 Photo by Gianni Neiviller
不器用だった高校時代。下校時のウォークマンが心の支えだった
――ヤギさんはドラコ・ロサのアルバム「VIDA」でグラミー賞を受賞されました。日本人がアメリカ・ハリウッドというポピュラー音楽の本場で活躍し、グラミー賞を獲るというのは本当に素晴らしいことだと感じます。
ヤギさん(以下、ヤギ) ありがとうございます。でもこれは、僕個人が優れているということではなく、チームとしていい仕事をした結果の賞です。……なんて言うと優等生っぽいですが(笑)、本当にこの仕事はチームプレイです。優れたチームの中にいるからいい仕事ができて、その仕事がまた次の仕事につながる。グラミー賞はその結果ですね。
●グラミー賞受賞作品『VIDA』ドラコ・ロサの楽曲
――ハリウッドのレコーディングエンジニア・プロデューサー、しかもグラミー賞。普通の日本人からすると、ずいぶん遠い世界です。ヤギさんがそれを目指した原点はどこにあるんですか?
ヤギ 音楽の仕事に就きたいという思いがわいてきたのは、高校時代ですね。子どものころから音楽教室には通っていましたが、それはあくまでも「お稽古事」。中学、高校とロックバンドでドラムも叩いていましたが、プロのドラマーになろうとは本気では思ってなかったですね。
でも、高校3年生になって、初めて「音楽の仕事に就きたい」「スタジオでレコードやCDをつくる仕事がしたい」と明確に思ったんです。大人たちに「将来を考えろ」なんて言われても全然ピンとこなかったけど、自分が音楽をやっている姿はすぐにピンときた。だからその道を目指しました。
――「ピンときた」。それだけで、将来の職業を決めたんですね。
ヤギ はい(笑)。高校のときにいい音楽をいっぱい聞いていたので、「このような素晴らしい音楽が生まれる瞬間にいたい。そのような仕事に就きたい」と強く思ったのです。
実は、当時は非常に不器用で、特に、高校を卒業するころは人間関係がうまくいっていなかった。僕は誰に対しても、感情を出してはっきりものを言うほうだったんですけど、そのくせガラスのハートで、言い返されるとすぐに傷ついて、しょっちゅう喧嘩していた……だけど弱い(笑)。
すべてのコミュニケーションがそんな感じだから周りからは弾かれるし、勉強もできないし。スポーツも、一所懸命やっても部活でレギュラーをとれないし。なんかもう、すべてがダメで。自我だけはあったんですけど、現実が伴わなくて。学校が全然楽しくなかったんですよね。
――なんか、意外です……。
ヤギ いや、ほんとにそうだったんです。
それで、そんな生活で唯一ハッピーだったのが、下校するときにウォークマンで音楽を聞くことだったんです。音楽を聞いている間は、とても気分が高揚して、日常から離れることができた。その中で妄想がどんどん膨らんで、音楽に携わる仕事がしたい、それも本場・アメリカのハリウッドで音楽の仕事がしたいというようにイメージが固まっていきました。
はっきり言って、現実逃避ですよ(笑)。現実逃避の中で、将来の自分のイメージがつくられていったんです。というより、当時の僕には、そこにしか、自分の居場所がありませんでした。悲しいと言われれば、そのとおりですね(笑)。
――いや、でも、高校生って多感な時期ですからね。なんとなく、わかる気がします。ちなみに、そのころからすでに、「アメリカでグラミー賞をとる」という夢は見えていたんですか?
ヤギ ええ、見えていました。ただ、いかんせん「現実逃避」ですからね。まったく現実的でない。「アメリカで音楽の仕事をして、フェラーリを乗り回して、グラミー賞をとるんだ。それが幸せなんだ!」とか、その程度のものでした。実際はグラミー賞をいただいても、フェラーリを乗り回す生活なんて送れないんですけどね(笑)。
本当に、しょうもない子どもの夢でしたよね。今の僕が聞いたら一笑に付すような夢ではありましたけど、当時の僕にとっては、その夢しかすがるものがなかったんでしょうね。