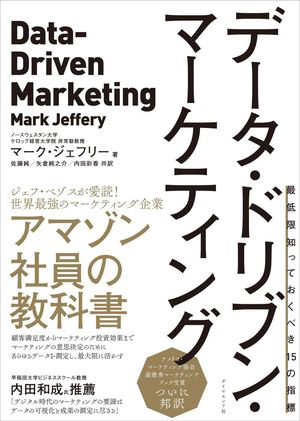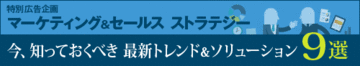昨年末にヤフーの宮坂社長が「これからはデータ・ドリブン企業と呼ばれたい」と発言して、一気に日本でも認知が広がった感のある「データ・ドリブン・マーケティング」。数回にわたってそのエッセンスを紹介する『データ・ドリブン・マーケティング――最低限知っておくべき15の指標』は、世界最強のマーケティング企業アマゾンのジェフ・ベゾス氏の愛読書であり、アメリカ・マーケティング協会が選出する最優秀マーケティング・ベストブック(2011)の待望の邦訳である。
データ・ドリブン・マーケティング担当者は
社内でエース扱いされ、昇進が早く、
重要な役職に就いている
「毎週の役員会議で、他の役員たちは様々な武器を使いこなして議論をしているのに、私はそこに丸腰で参戦しているような状況です。いつもやられてばかりで、うんざりですよ」
フォーチュン100社に名を連ねる大企業のマーケティング幹部によるこのコメントが、深く印象に残っている。マーケティング部門の活動の成果について質問された時に、具体的なデータで答えられないことをかなり悔しがっていた。この多難な時代において、マーケティング効果測定や、データ・ドリブン・マーケティングはますます重要になっている。マーケティング担当者は、投じる費用の正当性をしっかり示すと同時に、マーケティングの成果を大幅に向上させなければ立ち行かなくなるだろう。
なぜ多くの企業にとって、データ・ドリブン・マーケティングは難しいのだろうか。その理由として、「やり方がわからない」といった漠然としたものから、ブランディングや認知率向上といった短期的な売上指標に直結しない活動の扱いが難しいといった具体的なものまで、数多く聞かれる。
事態をことさらややこしくするのは、指数関数的に増加し続けるデータ量の問題だ。インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)社の推計によると、世界のデータ量は年率60%で拡大しており、約20ヵ月ごとにデータ量が倍増していることになる。マーケティング担当者たちは、この巨大なデータ量に圧倒されてしまい、時間もリソースも限られる中で、それを使って自分たちの活動の有効性を示すことができないままになりがちだ。
しかしながら、データ・ドリブン・マーケティングの考え方や、適切な指標を使ったマーケティング効果測定手法を修得するマーケティング担当者や企業も、少しずつ現れてきた。私が知る限り例外なく、データ・ドリブン・マーケティングを推進した担当者は社内でエース扱いされ、昇進が早く、重要な役職に就いている。また後述する通り、マーケティング効果測定の指標を使いこなし、データ・ドリブン・マーケティングを組織文化に根づかせることに成功した企業は、この組織能力を強力な武器としてライバル企業に業績で大きな差をつけている。
数年前に、米大手家電量販店チェーンのベスト・バイ社の最高マーケティング責任者(CMO)であるバリー・ジャッジにライバルはどこかと尋ねたところ、ウォルマート社だと即答された。超効率的なサプライチェーンと規模の経済を最大限活用することで、価格や粗利を最小限に抑え、グローバル小売業の競争環境を激変させてその頂点に立つウォルマートの名前が出ること自体に驚きはない。しかしながら、ライバルのサーキット・シティ社の名前が挙がらないのは意外だった。
「彼らは全然わかってないんですよ」というのが当時のジャッジの評価だ。サーキット・シティのマーケティング戦略は、とにかく継続的にセールを実施することだった。セールによって来店客数を伸ばし、売上を増やす。しかしながら、ウォルマートの台頭以降、小売業の粗利率は極小化されており、セールをすると赤字になるような構造になってしまっていた。その結果、サーキット・シティは売上を上げるためにセールを実施し続けなければならず、そのセールが赤字を生むという、ジャッジの表現を借りるなら「死の連鎖」状態に陥ってしまっていたのだ。
残念ながら、サーキット・シティは過去の遺物となってしまった。同社は2009年1月に破産申請し、清算された。過去20年の間に、多くの米国の中堅小売企業が同様の事態に陥っている。たとえば、共にかつては地場小売業の雄であった、シカゴの百貨店マーシャル・フィールズ社や、フィラデルフィアの百貨店ジョン・ワナメーカー社も単独では生き残れず、その他100社以上の企業と同様に、合従連衡の波に飲み込まれてしまった。これらの百貨店は、今では米国最大の百貨店企業メイシーズ社の傘下となっている。
一方、ベスト・バイ社はそうならずに済んだ。もちろん、彼らも需要喚起型マーケティングで来店者を増やすための費用をたくさん投じてはいる。しかしながら、ベスト・バイはブランディング、CRM、データ・ドリブン・マーケティングのためのインフラといった領域に、競合他社と比べて大きな投資を行っているのだ。また、振り返りによる継続的な改善活動もきっちりしている。マーケティング活動の結果を測定し、そこから学んだことを次回以降の活動にフィードバックすることで、マーケティングの最適化が実現されている。
ベスト・バイでは、消費者の購買行動特性やデモグラフィック属性を、個店単位で分析している。たとえば、ある地域での分析を通じて抽出された消費者セグメントを、「ジル」(訳注:女性の名前)と名づけた。ジルのイメージは、家庭の運営を取り仕切る「サッカー・ママ」(訳注:郊外の中流家庭の母親で、子供をサッカーなどの習い事に送迎することからついた呼び名)だ。ジルは、家電の購入に関しても決定権を握る。データに基づき、ベスト・バイでは、数多くのジルが存在する地域の店舗では、彼女たち向けのマーケティング活動を行った。
具体的には、デジタル機器を母親と子供が一緒に使っている写真の店内バナーでの掲示、ダイレクトメール、そしてジルが好む商品の展開強化といった施策が実行された。対象店では、マーケティング活動実施前後の比較により、売上増加率が測定された。
この事例は、マーケティング格差をよく体現している。少数の企業が正しいマーケティングに移行する中で、多くは取り残されている。その結果、上位企業は競争優位性を確立する一方、残りの企業は苦戦しながら徐々に市場シェア、そして利益を減らしていき、同業他社に吸収されるか、撤退を余儀なくされるケースすら少なくない。