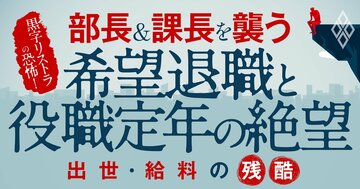大正時代から現代まで、その時代の経済事象をつぶさに追ってきた『週刊ダイヤモンド』。創刊約100年となるバックナンバーでは、日本経済の現代史が語られているといってもいい。本コラムでは、約100年間の『週刊ダイヤモンド』を紐解きながら歴史を逆引きしていく。(ダイヤモンド社論説委員 坪井賢一)
連載第26回と第27回で、現在の9電力会社による地域独占体制成立の由来を探索してきた。1951年に現行システムが完成したのだが、意外だったのは、国家総動員体制下、発電・送電を国家管理するために日本発送電株式会社が設立されるまで、戦前の日本の電力産業はほぼ自由市場で、数十社から数百社が競争していたことである。
政府は日中戦争を視野に、国家総動員体制を敷く。歴史上初めての総力戦であり、生産力の集中、効率化が必要だと考えたのである。つまり、自由な資本家・経営者による競争を放置しておくと、戦争のための生産力集中ができないということだ。
これははじめ、政治家や軍部から出たコンセプトではなく、当時の経済官僚のビジョンだった。今回から何回か、電力国家管理への道を詳しくみておきたい。
革新官僚により電力会社は国有化へ
社会主義化に反発した東京電燈社長・小林一三
1936年、内閣調査局は電力会社(当時62社)の所有と経営を分離し、所有は資本家・株主のままで、経営を国有化するという「電力国家管理案」を編み出す。東邦電力社長、松永安左エ門が「官吏は人間のクズ」(1937年)と発言して物議を醸したころだ。
当然のことながら、資本家・経営者は猛烈な反対運動を起こす。しかし、前回述べたようにけっきょく、1938年に「電力国家管理法」が公布されてしまう。
この間、内閣直属の国策立案機関として設置された企画院に集まる官僚は、生産力を戦争遂行のために集中させる統制システムを立案していた。このような経済官僚たちは、革新官僚と呼ばれた。彼らのモデルはスターリンの五ヵ年計画だったといわれる。つまり、社会主義計画経済の応用だ。