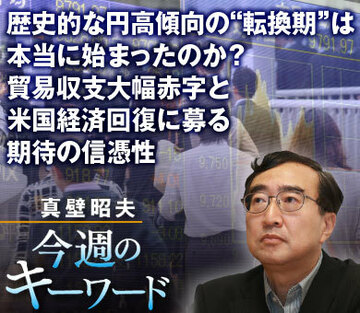前回、2001年からの量的緩和は、マネタリベース(ベースマネー)を増加させたものの、マネーストックを増加させることはなく、また物価にも影響しなかったことを述べた。その意味では、量的緩和政策は目的を達成できなかったわけであり、失敗であった。
しかし、真の目的は、国債の購入を通じて長期金利の上昇を防ぐことだったと考えることもできる。その意味では成功である。
また、為替レートを円安にすることにも寄与した。実は、現代世界における金融政策は、国内経済条件に直接の影響を与えるというよりは、国際間の資本取引に影響を与え、為替レートを変化させることが最大の効果である。
開放経済での金融政策は
為替レートを変化させる
金融政策が為替レートに影響することは、開放経済に関する標準的なマクロ経済学のモデルである「マンデル=フレミング・モデル」が予測することでもある(注1)。
ただし、マンデル=フレミング・モデルでは、金融緩和をするとマネーストックが増えてLM曲線が右にシフトし、そのために金利が低下するとしている。2003年からの日本で起きたことには、これとは違う側面もあった。第1に、マネーストックが増加したわけではなかった。第2に、日本の金融政策だけによって円安になったというよりは、円キャリー取引が誘発されたことによる面が強い。そしてこの背後には、アメリカの金利が05年頃から急上昇したことがある。この経緯をもう少し詳しく見よう。
【図表1】には、2年債で見た日米金利差と円ドルレートの推移が示されている。両者の相関はきわめて強い(注2)。
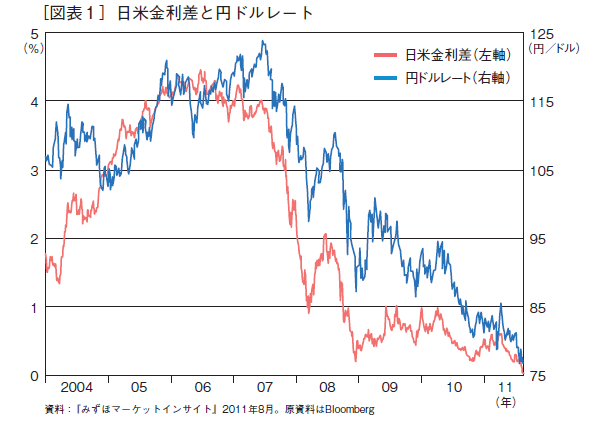
2005年頃からアメリカ2年債の利回りがかなり急速に上昇した。それまで1%台であったものが、04年中頃から2%台となり、05年には3%を超え、さらに上昇した。これは、住宅価格の高騰を防止するためにFRB(アメリカ連邦準備制度理事会)が金融引き締めに転じたことの結果である。
図から明白に見られるように、それに応じて円安が進んでいる。これは、円キャリー取引などの形態で、日本からアメリカへの資金移動が増加したことの結果である。
なお、このときに、グリーンスパンが「謎」と呼んだ現象が発生した。金融引き締めを行なったにもかかわらず、10年債利回りが上昇せず、一時的にはむしろ下落さえしたのである。これは、アメリカに流入した円キャリー資金の影響だった可能性がある(注3)。