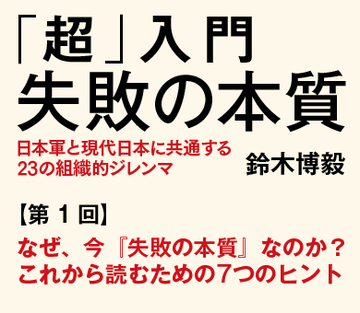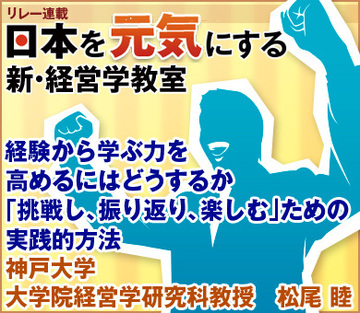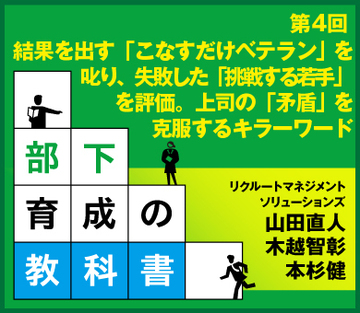Kathryn Schulz
Kathryn Schulzアメリカのジャーナリスト。ニューヨークタイムズ・マガジン、ローリング・ストーン誌などに寄稿。『まちがっている エラーの心理学、誤りのパラドックス』によって、全米で注目される書き手になる。
――この本『まちがっている エラーの心理学、誤りのパラドックス』(青土社刊)(原題:Being Wrong: Adventures in the Margin of Error)はあなたの処女作ですね。同じ業界の人間として言えば、「誤り」というテーマについて執筆することを考えただけで、気が遠くなりそうです。いったいどれくらいのリサーチをされたのでしょうか。
まず、あなたが言ったように、信じられないほど気が遠くなりました。処女作のいいところは、どういう本になるかまったく想像できないことです(笑)。リサーチも広範囲に及ぶものでした。2004年に、このテーマについて本を書こうと真剣に考えたのですが、出版に至ったのは6年後の2010年です。どれくらい大変だったかがおわかりいただけるでしょう。しかも、フルタイムでとりかかってこれだけかかったのです。
――何をきっかけに、このテーマについて書こうと思ったのですか。
振り返ると、大きなことが2つ起きて、それからヒントを得たと言えると思います。ひとつは大量破壊兵器のばかげた失態があり、その後遺症が2004年ごろ出てきました。誰かの間違った思い込みが、これほどまでに劇的な結果になる、ということを考えたのがきっかけです。2つ目は金融部門、そして政治部門での誤りです。今まで正しいと思っていたことが間違っていた、ということが、金融危機で証明されたのです。
私の心の奥底に、「誤りたくない」という欲望が強く刻まれました。私は極めて偏見の強い頑固な人間ですが、自分が何について話しているのかわからないときでさえ、「誤りたくない、自分は正しい」と思っていることに気がつきました。みんなが心の奥底で「正しくありたい」という不合理な欲望を持ったら、いったい社会はどうなるのか、世界はどうなるのかと考え始めました。
――分野によっては、自分の考えが間違っていたのか、あるいは正しかったのかを知るのに、かなり時間がかかる場合があります。一方で天気予報のように、すぐにフィードバックを得られる場合もあります。
スポーツの試合も、すぐにわかりますね。