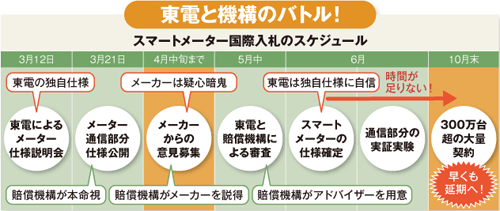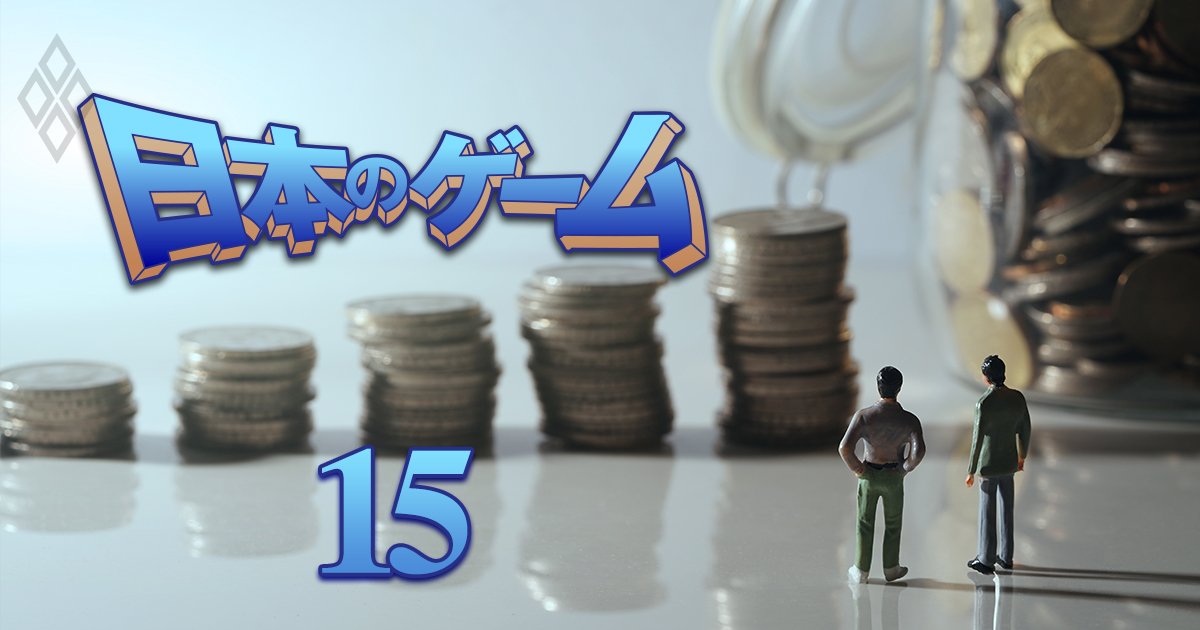「第1回入札は実質的に半年以上の延期になり得ます」
東京電力が、政府の原子力損害賠償支援機構と共に取り組むスマートメーターの国際入札。欧米の主要メーカーも参画し、今後5年間で1700万台を発注する世界でも類を見ない規模の一大プロジェクトだが、機構は外資メーカーなど約10社に、早くも異様な“延期方針”を伝え始めている。
スマートメーターは「東電改革」の第一歩。それがすでに根本から揺れ始めている。背景には既存下請けメーカーとの強固な関係を保ちたい東電と、外資参入による門戸開放を狙う機構の間の激しい主導権争いがある。
事の発端は、3月12日に開かれたメーター仕様の説明会。巨大受注に目を輝かせ参加した国内外61社に渡された仕様案は、東電が既存4社と共同開発した「ねじ1本まで決められた高コストな独自仕様」だった。スケジュールもわざとタイトに設定されており、「内情を知る既存4社しか受注できない」(外資メーカー)と「出来レース」の様相が濃厚となっていた。
気付いた機構は反撃に出た。「大きな仕様の変更があれば初回の入札で導入台数をゼロにすることが可能。つまり、実質的に半年以上延期にする」(経済産業省関係者)ことで、出来レースを食い止めようとしたのだ。それで時間に余裕ができれば仕様変更の余地ができ、意欲を失った外資メーカーらに新規参入を促すことができる。
スマートメーターの導入はこれまでの手動検針による人件費を削減するだけでなく、新たな省エネ産業の開拓、発送電分離など電力改革全体にも影響を及ぼす「改革の1丁目1番地」(同)だ。ここでつまずくと、東電と周辺企業の利権がさらに強化されるだけでなく、改革までもが骨抜きになる。経産省幹部は「東電とのだまし合いに勝ち抜くしかない」と表現する。
ここに1枚の資料がある。機構がメーカーに配布した3月12日の説明会の議事録だ。会合で東電幹部は、メーター仕様変更の可能性を問う質問に「変更する場合は平成29年度以降導入分と考えている」と発言していた。しかし、議事録には「が、早ければ平成27年度(第2期)から変更の可能性もあります」との文言が加筆された。
「仕様変更に後ろ向きだった東電の姿勢を嫌った機構が事後的に付け加えたようだ」(政府関係者)というのが実情だが、機構のなりふり構わぬ必死さが見て取れる。
では、窮地に追い詰められたはずの東電がここまで改革に抵抗するのはなぜか。それは半世紀近くにわたって深い関係を築いてきた既存4社との利権構造を極力温存したいからだ。