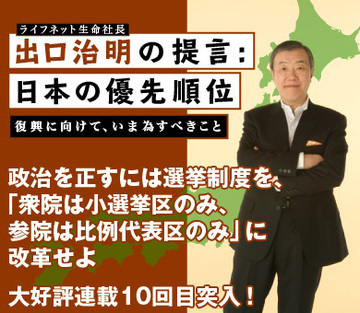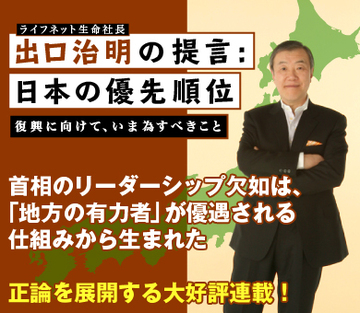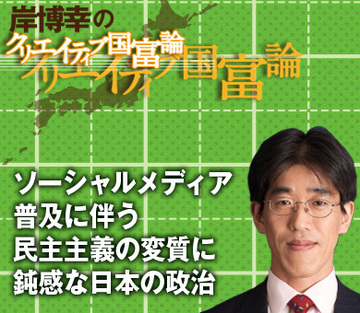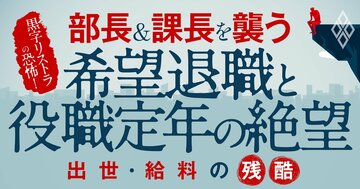朝日新聞(5月3日朝刊)の世論調査によると、衆院小選挙区の一票の格差が解消されずに、違憲状態のまま、衆院を解散し総選挙をすることについて、「してもよい」は27%で「するべきではない」が53%と大きく上回った。ほぼ、ダブルスコアである。改めて、市民の常識が健全であることが、裏付けられたように思われる。そもそも民主主義は、「大勢の人を長期間だますことはできない」という人間の歴史上の経験則に基づいた制度である(大勢の人を短期間、あるいは少数の人を長期間だました実例は幾つかあるが)。国会はこの市民の厳しい視線に正面から応えなければならない。
最高裁の判決を読み直そう
一票の格差とは何か。それは、住所による選挙権の差別に他ならない。例えば、ある地方から東京に転居してきた人が、住民票に関する転入届を行ったとき、区役所の窓口で「住所変更により、あなたの一票の価値は衆議院議員選挙0.6票、参議院議員選挙0.3票になりました」と告げられたら、恐らくその人は激怒するだろう(住所による一票の価値は、一人一票実現国民会議のHPで簡単に確認できる)。
現在のわが国では、その事実が目に見える形で告げられないだけで、住所による選挙権の差別が堂々と行われている。これは明らかに憲法第14条が定める法の下の平等に反する。もちろん、一票の格差とは、こういった法律論だけにはとどまらず、深い病根を抱えていると思料するが、その点については以前に述べた通りである。
一票の格差については、1960年代から何度も何度も違憲訴訟が行われてきたが、昨年の3月23日、最高裁大法廷は2009年の衆院選について、選挙自体は有効としながらも、現行制度は「違憲状態」とする厳しい判決を出した。
この判決が画期的だと言われているのは、選挙区割りにおける「1人別枠方式」を格差の原因と明確に認定したことではないだろうか。1人別枠方式とは、人口の少ない地域に配慮するとして、1994年に導入された仕組みで、小選挙区の300議席の配分は、まず都道府県に1議席ずつ割り当て、残りを人口に応じて割り振る方式である。