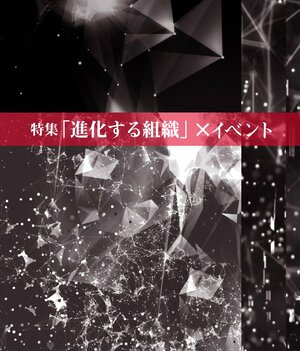炭素に価格付けを行い
脱炭素技術の開発促進を
――ハーバード大学教授のマイケル・ポーター氏が提唱するCSV(社会的価値と経済的価値の両方を創造する経営)に通じる考え方ですか。
私自身は、クラウス・シュワブ氏の考え方に共鳴しました。彼は1971年に世界経済フォーラム(WEF)を創設するとともに、同年に「マルチステークホルダー」のコンセプトを提唱しました。企業は株主だけではなく、社会などさまざまなステークホルダーに目を向けるべきというのが主旨です。当時は、企業は株主のものであり、ただ短期の利益を重視すべきだという考えが強く、激しく議論されました。
その後50年が経過して、世界を取り巻く環境は大きく変わりました。人類の存続を危うくする気候変動問題をはじめ、ダイバーシティーに関する問題など、複雑な社会課題が生じています。こうした変化を受け、経営者の間には、複数のステークホルダーに目を向け、より長期的な株主価値の創造を重視する考え方が深く根付いてきていると感じます。
近年、ESG投資や企業の「パーパス」(存在意義)が注目を集めるのは、こうした社会の変化が背景にあります。
――状況変化に企業が翻弄されないように、パーパスがアンカーとして機能するということでしょうか。
そう思います。企業は社会における役割や存在意義、つまりパーパスをもっと真剣に考える必要があります。経営者は、経済環境の変化の中で、持続可能で、望ましい経営を実行しようとしています。それを支持する投資家も増えてきている。社会も政府もそれを支持するようになり、その視点で経営を見ています。今日のような突発的なエネルギー危機の顕在化により、短期利益を追求しなければいけないという圧力に経営者が流されてしまわないようにパーパスの役割は増しています。
当社もそうですが、企業が中長期で発展するために最も大切なのは、社会における自社のプレゼンスや魅力を高め、優れた人材を引きつけて採用・育成し、社内にとどめておくことです。そのためには、社会の中で果たすべき役割や貢献できるリソースを明確に定義するパーパスの意義はますます高まると思います。
――最後に、政府はどんな役割を果たすべきか、お聞かせください。
世界的な脱炭素活動や経営に向けて、政府が行うべき施策を4つ提言します。
第一に、炭素排出や脱炭素活動に関しての透明性を担保する制度を確立することです。誰が見ても納得できるデータを開示するように制度設計しなければいけません。
第二に、政府には、排出する炭素に価格を付けてほしいと思います。困難であるのは承知していますが、価格付けすることで、企業の脱炭素経営を促進することになります。
第三に、脱炭素テクノロジーの開発について企業が投資するインセンティブを、政府には創設してもらいたいと考えます。中長期的な問題解決になる方法です。
第四に、世界的に脱炭素活動が求められる中、低所得国ではさらなる経済成長が必要という現実を踏まえて、高所得国は低所得国に対してこれまで以上に支援を行うべきです。低所得国の成長と脱炭素活動の両立について、高所得国は自分事として支えていく必要があります。