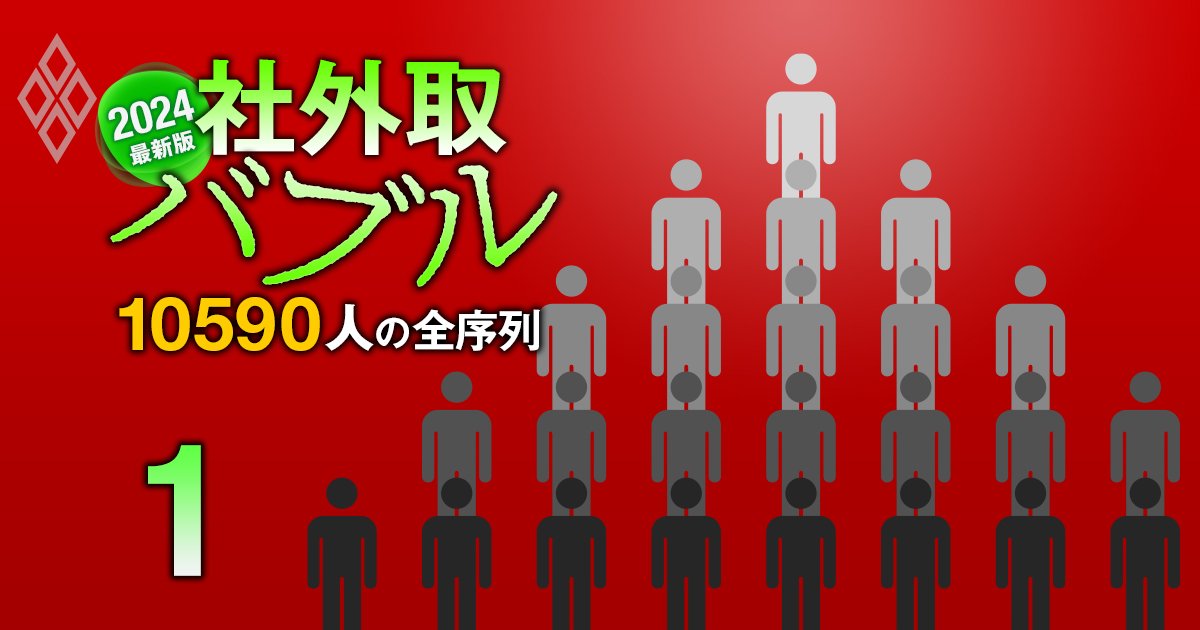「職場を選ぶことのできる人」が有利なのは昔からそうなのだが、現在、職業の盛衰がいわゆるホワイトカラーの職種に至るまで急速に動く気配を見せている。
話題の対話型AI(人工知能)「ChatGPT」が象徴的だが、知識を用いて解決策を探し、これを分かりやすく顧客に伝えるような仕事のいくつかが崩壊する可能性が小さくない。あなたがこれから蓄えようとしている知識とスキルは、2年後にはまだ立派な職業として成立しているかもしれないが、10年後には大いに怪しいかもしれない。
この見極めは、「今」行うよりも、「2年後」に行う方がやりやすい。その時に「選べる立場」を持っているかどうかは、人生そのものの有利不利を分ける。
2年後というと、大学4年を卒業して就職したとして24、25歳だ。受験勉強に励んだ10代のころの吸収力は衰え始めているかもしれない。しかし、まだ新しいスキルに取り組む柔軟性は残っているだろう。ただし、その時点でチャンスを得られるかどうかが問題なのだ。
自分は「転職できる人」か?
職務経歴書を作れ
自分が、「転職できる人」であるかをチェックするには、自分の職務経歴書を作るのがいい。自分がどのような職業上の能力を持っているか、実際にどのような仕事をしてきたかについて記述した、職業人としての自分の説明書だ。
「2年後の自分の職務経歴書が、他社にとって十分に魅力的であること」を目標に、仕事や研修に励むといい。
「2年」では大した仕事はできないと思うかもしれないが、それは自分を甘やかし過ぎだ。たいていの仕事は、2年間集中的に努力すると、「素人とは違う」という程度のレベルにはなる。
実際に就職2年後に転職活動をしたときに、採用担当者がまず見るのは履歴書の学歴の方かもしれないが、2年あれば何らかの仕事はできる。あるいは、仕事のスキル習得に向けた努力を具体的に説明できるようにはなる。履歴書段階の相対的な有利不利に対して、プラスの点数を積み増すことができる。学歴の不利なども、ある程度は回復・逆転するチャンスがある。
一般的に、職業人の人材価値は、「能力+実績」で評価される。付け加えるなら、これから働ける年数が関係するが、これは新入社員の時点ではまだ意識しなくていいだろう。肝心なのは、資格を持つなど能力の指標になるものの他に、実際に仕事に能力を使った説得的な事実だと心得よう。
当面の仕事の内容は、次にやりたい仕事につながるものなら理想的だが、そうでなくても構わない。そもそも会社では仕事を選べないだろうが、そこは、そう気にしなくていい。若い段階では、能力を実際の仕事に使ったプロセスで十分評価されるはずだ。