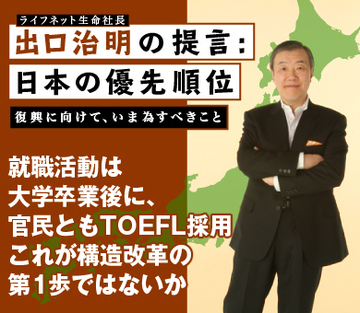先日、とある公立大学に講義に伺った際、学長と小一時間ばかりお話しする機会があった。学長は、こう言われた。「少子高齢化の現状では、学生をどこからどうやって集めてくるかが本当に大変です。学生数が減れば、大学はこのままの姿では生きていくことができないのですから」と。確かにそれはその通りであろう。大学改革については当コラムでもこれまでに何度か取り上げてきたが、今回は「学生をどこから集めてくるか」という一点に絞って論じてみよう。
グローバルを目指すなら
秋入学と英語での講義が車の両輪に
仮に学生を18才前後の若者と定義する。わが国の年少人口は減り続けている。大学進学率を一定に置くと、学生の数は減り続けるという答えしか出てこない。そうであれば、大学を国際化して、世界各国から18才前後の若者を集めて来ようという発想しか残されていないということになる。これが大学の国際化である。
グローバルを目指すなら、しかし、2つの関門があることを忘れてはならない。世界の優秀な若者は、実は、世界中で取り合いになっている。極論すれば、世界中の優秀な大学が、若者の分捕り合戦を行っていると考えた方がわかりやすい。世界の大学の大勢は秋入学である。そうだとすれば、わが国の大学が春入学を継続して世界中の若者にアピールできるはずがない。悔しいかもしれないが、デ・ファクトになってしまったものはもはや取り返しがつかないのだ。グローバルを目指すのなら秋入学への切り替えは必須である。
これが最初の関門であるが、2つ目の関門は英語による授業である。リンガ・フランカは既に英語の時代になって久しい。これも残念ながらデ・ファクトである。デ・ファクトについては合わせるしか方法がないのだ。しかも日本の大学の国際競争力は低い。東大(25番程度)と京大(50番程度)の2校がかろうじてトップ100にとどまっているという窮状である。
このレベルの競争力で、しかも世界ではほとんど使えない日本語を勉強するというハンデを自ら克服して、わが国に世界中の優秀な学生が集まってくると考えることはできない。秋入学と英語での授業という2つの関門を突破した上で、大学の国際競争力を相当嵩上げしないと、世界中から優秀な学生を集めてくるという方策は、絵に描いた餅に終わってしまうだろう。