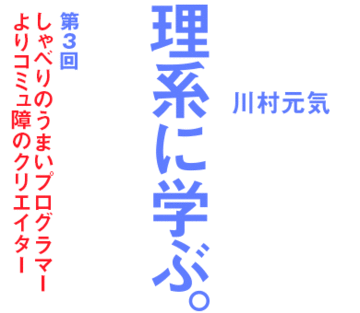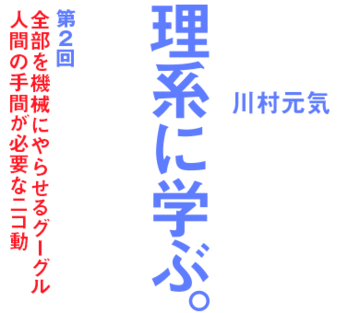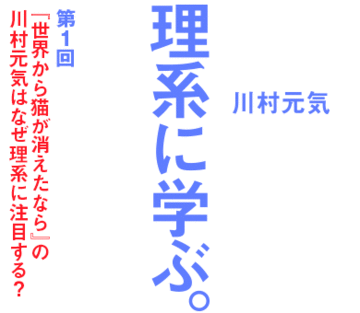『告白』『悪人』『モテキ』『バケモノの子』『バクマン。』などを手がけた映画プロデューサーで、初めて書いた小説『世界から猫が消えたなら』が120万部を突破し映画化。2016年も映画『怒り』『何者』など、次々と繰り出される企画が話題を集める川村元気。その背景にあるのは「“苦手を学ぶ”ことで、人間はぎりぎり成長できる」という一貫した姿勢だという。
そんな川村元気が、話題の新刊『理系に学ぶ。』では、「文系はこれから何をしたらいいのか?」をテーマに最先端の理系人15人と、サイエンスとテクノロジーがもたらす世界の変化と未来を語っている。
本連載ではその中から5人との対談をピックアップするが、第4、5回では、月間利用者2億人を誇り、ノリのいい理系集団とともに世界に向かうLINE取締役CSMOの舛田 淳さんにご登場いただく。
LINEはどういう人たちが始めたんですか?
川村 舛田さんには、2012年に僕が書き下ろした初小説『世界から猫が消えたなら』をマガジンハウスの編集者と持ち込ませてもらって、そのときに「面白かったから、LINE初の連載小説として発表を」と提案していただいて以来の間柄ですね。
舛田 あれは完全にノリでしたね(笑)。
川村 無名な作品を「面白かったから」という理由だけで取り上げてくれたのに驚いて、確かにノリのいい会社だなと思いました。その印象は今も変わっていませんが、多くの人はLINEという企業をITという括りで見ると思うので、すごく戦略的で、ビジネスにシビアなんだろうという印象を持っているんじゃないかなと思うんです。
舛田 そういう印象を持たれることもありますが、LINEは決してそのような文化の集団ではありません。今日はLINEらしいやわらかいところをお話ししますね。
川村 まずはプログラマーを中心に理系の集団を束ねている企画者としてのお話を伺いたいんですが、今現在のLINEのユーザー数は、どれくらいなんですか?
舛田 日本で6800万人、全世界ではアクティブユーザーが月間2億1500万人くらいで、現在もアジアを中心に成長しています。
川村 すごい数ですね…舛田さんを筆頭に当初はどういう人たちが始めたんですか?
舛田 今のLINEには韓国のオンラインゲームコミュニティ「ハンゲーム」、同じく韓国の検索サービス「ネイバー」、ご存じ「ライブドア」という3つの系譜があるんです。まず私もいた「ネイバー」の日本法人がグーグルとヤフーに勝負を挑んで、日本でこてんぱんにされた。結果、私も含め経営陣が「スマートフォンアプリに特化したコミュニケーションの新しいサービスを考えろ」という指令を出して、こてんぱんにされたチームにいた3人の女性たちが、考えに考え抜いて、半分泣きながら骨子を作ったんですよ(苦笑)。
川村 7人の侍ではなく、3人の女侍がいたんですね。
舛田 ちょうど東日本大震災で社会のトレンドが変わった頃で、それまでは不特定多数の知らない人とつながるためにネットのテクノロジーを使っていたけれど、「それって違うんじゃないの。目の前にいる人との関係が軽く見られているけど、本当はこっちが大事でしょ」ってことになった。それで開発とデザインのエース級の人材を引っぱってきて、最初は10人強くらいのチームで始めました。
川村 それでもたったの10人。ゲリラ戦だったんですね。
舛田 そうですね。しかも2011年の春にスタートして、当初目標としていた100万人を突破するまでが本当に大変で、最初の1、2ヵ月は数字がぴくりとも上がらない状態でした。社内に反対の空気があるのに、内部ベンチャー的に一部のメンバーだけで開始したところもあって、スカイプやツイッターやフェイスブックがある中で、普通に見れば決して成功の確率が高いプロジェクトではなかった。だからこそチャンスがあると思って始めたんですけどね。