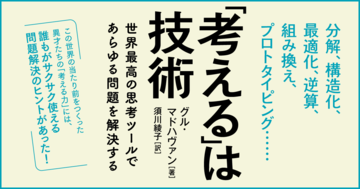ペニシリン。数々の感染症患者の命を救ってきたこの抗生物質がない世界もまた、スマートフォンやATMと同じく、もはや想像することはできない。当然、その発見者であるフレミングは、ノーベル生理学・医学賞をはじめ、数々の栄誉に浴している。
しかし、実は「ペニシリンが医療現場で当たり前に手に入る世界」に貢献したのは、まったく別の、ある無名の女性だと知っているだろうか。『「考える」は技術』を手がかりに、彼女の「適応、改良、応用」を支えたある思考法に迫りたい。

ペニシリン「発見」に隠された
3つの「運命」
優れた製品を1つだけつくるなら、そう難しいことではない。
1928年、イギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミングは、ブドウ球菌を培養していたシャーレを見て驚いた。あるシャーレにアオカビが混入したのだが、そのまわりだけブドウ球菌の繁殖が止まっていたのだ。フレミングはこのカビをペニシリンと名づけた。
彼は1929年に『ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・エクスペリメンタル・パソロジー』誌に論文を発表し、ペニシリンの抗生物質としての可能性を指摘した。当初はあまり注目されなかった。というのも、ペニシリンを化学的に分離して臨床の場で活用する手段がなかったからだ。フレミングは研究をなかばあきらめた。それから10年ほどして、オックスフォード大学の研究者エルンスト・チェインとハワード・フローリーがペニシリンの抽出に成功して治療上の有用性を報告したが、大量生産はできなかった。いくつかの研究グループがこの課題に挑んだが、いずれもうまくいかなかった。
1941年末、真珠湾攻撃をきっかけに抗生物質の不足は緊急課題となった。第二次世界大戦のさなか、連合国側の負傷兵の治療のために大量のペニシリンが必要とされていたが、十分な量は確保できなかった。1942年には、製薬会社メルク・アンド・カンパニーが、たった1人の患者に対して、アメリカ中のペニシリンの供給量の半分近くを使うということもあった。敗血症という致命的な感染症の治療のためだ。ペニシリンは人の体内でほんのわずかな期間しか生きられず、治療にはそのたびにかなりの量が必要だった。供給不足を補うため、患者の尿から抽出したペニシリンを再利用する医師がいたほどだ。
のちの講演で、フレミングはこう語った。「1928年に私のシャーレにカビが混入したのは運命でした。1938年にチェインとフローリーが多くの抗生物質のうち、ほかでもないペニシリンを研究することになったのも運命であり、ペニシリンがもっとも必要とされた戦時中にその研究がようやく実を結んだのもまた運命でした」
フレミングは「運命」という言葉を3度使っている。1度目は彼の偶然の発見について。2度目はチェインとフローリーについて。3度目については、特定の人物の名前はあげられていない。あくまでも「ペニシリンがもっとも必要とされた戦時中にその研究がようやく実を結んだ」にすぎない。ところがこのあとで詳しく述べるとおり、3度目の運命は、フレミングの偶然の発見よりはるかに重要だったと言えるかもしれない。