名古屋で10月11日に始まった国連地球生きもの会議。人類を含む全生物の存続がかかる重要な会議だが、国同士の利害対立が激しく合意は困難だ。しかし、生物多様性に対する企業の影響の大きさが周知となった今、たとえ会議が崩壊しようとも、企業はその責務を免れられない。
(「週刊ダイヤモンド」副編集長 大坪 亮)
かつて日本のオオカミが絶滅したように、今オランウータンやゴリラがその危機にある。昆虫や植物など全生物では、1日になんと平均約100種が絶滅しているといわれる。
地球上には約3000万以上の種が存在すると推定されるが、人間の活動が種の絶滅を加速している。生物の乱獲や土地開発、外来種の持ち込みによる生態系の撹乱などによって、恐竜が絶滅した白亜紀末の100倍という速さで生物種が絶滅しているのだ(国連「ミレニアム生態系アセスメント」2005年)。
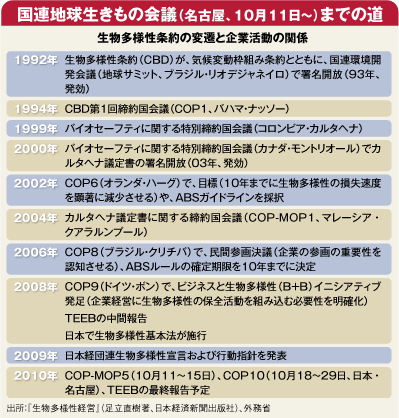
こうした事態を改善するために結ばれたのが生物多様性条約だ。1992年にブラジルで開かれた国連環境開発会議(地球サミット)で合意され、現在194ヵ国・地域が批准している。
地球サミットで同時に決まった気候変動枠組み条約は、97年に採択された京都議定書で、温暖化ガスの削減目標が決められ具体的な活動が始まっているが、生物多様性条約のほうは遅れている。

条約の目的の実現に向け、2年に1度、締約国会議(COP)が開かれる。10回目が今月名古屋で開催のCOP10(右上表参照)。
生物多様性は「生物は個々に違い、多様である」という意味だが、条約では、(1)生態系(森林や湿原など生物が生きる環境)、(2)種、(3)遺伝子という三つのレベルでの多様性と、生物が相互に連関していることを重要視している。
たとえばオオカミが絶滅すると獲物になっていたシカが増え、そのエサの植物が食い荒らされ、森林が衰退するというように、一つの種の絶滅が他の種や生態系に連鎖する。このままのペースで絶滅が進み、地球という生態系の臨界点を超えると回復が不可能となり人間を含めた生物すべてが絶滅する可能性もある。事態改善に向けた行動は待ったなしだ。







