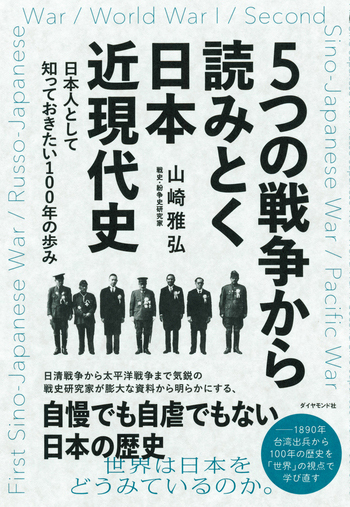近刊『日本会議 戦前回帰への情念』(集英社新書)が発売4日でたちまち重版・4万5千部突破の気鋭の戦史・紛争史研究家の山崎雅弘氏による新連載です。日本の近現代史を世界からの視点を交えつつ「自慢」でも「自虐」でもない歴史として見つめ直します。『5つの戦争から読みとく日本近現代史』からそのエッセンスを紹介しています。第2回はアジア最初の近代化をもたらした岩倉使節団から他のアジア国への態度の変遷を解説します。

江戸末期に結ばれた不平等条約改正のために
日本という国が、近代国家として国際社会へのデビューを果たしたのは、265年にわたる江戸幕府に終止符を打った「明治維新」の後、1868年1月に成立した明治新政府時代のことでした。
オランダやイギリス、フランス、アメリカなどの欧米諸国と日本の外交関係は、江戸時代から築かれていましたが、それらの関係は対等なものではなく、関税や犯罪処罰(領事裁判権)などの面で、日本よりも相手国側に有利な「不平等条約」でした。
そのため、岩倉具視をはじめとする明治新政府の指導者たちは、日本が国際社会で存在感を示すためには、まず欧米列強との「不平等条約」を改正して、対等な関係を築くことから始めるべきだとの結論に達し、その予備交渉を行うための使節団を結成します。
使節団の団長には岩倉自身が就任したことから「岩倉使節団」と呼ばれたこのグループには、大久保利通(後の初代内務卿)、木戸孝允(後の第二代文部卿)、伊藤博文(後の初代総理大臣)などの政府高官が46人、一緒に渡航した留学生(後に自由民権運動の指導者となる中江兆民、後に日露戦争の講和条約で重要な役割を担う金子堅太郎、後に日本の女子教育の環境改善に貢献する津田梅子など)を含めると総勢107人が参加し、通訳として新島襄(後の新島八重の夫、同志社大の実質的創始者)が同行しました。
明治四(1871)年11月12日(日付は当時使われていた「陰暦」)、岩倉使節団は横浜港を出発し、まず12月6日にアメリカ西海岸のサンフランシスコに上陸しました。
そこから、12月22日に大陸横断鉄道で東海岸を目指して出発し、1872年1月21日にようやくアメリカの首都であるワシントンDCへ到着、ホワイトハウスでグラント米大統領に謁見しました。日本を出発してから、約2ヵ月後のことでした。
岩倉使節団が直面した「近代」とは
岩倉使節団は、行く先々で現地のアメリカ人からフレンドリーに迎えられたため、もしかしたら不平等条約の改正は、意外と簡単に実現するかもしれないな、と楽観的に考えていました。ところが、アメリカ政府を代表して岩倉使節団と面会した国務長官ハミルトン・フィッシュは、いきなり日本側が予想もしなかったポイントを突いてきました。
「あなた方は、全権委任状(国の代表者として条約に調印する権限を持つ証)をお持ちですか?」
岩倉と日本側代表団は、相手が何を聞いているのか意味がわからず、額を突き合わせて相談しました。国と国との正式な交渉を行う人間は、自国の政府から発行された「全権委任状」を持参していなくてはならない、という、近代的な国際外交のルールを、この時点で正しく理解していた人間は、日本側代表団の中には一人もいませんでした。
うろたえた日本側は、すぐに「全権委任状」を取りに帰らせますと言い、大久保利通と伊藤博文を日本に向かわせました。二人は、再び鉄道で大陸を西へ向かい、船に乗って日本へ戻り、明治天皇から全権委任状を賜った上でまた船に乗り、太平洋を横断してサンフランシスコに再上陸し、鉄道を乗り継いで代表団のいる東海岸へと急ぎました。
大久保と伊藤が、往復で4ヵ月かけてヘトヘトになって「全権委任状」を持ってくるまでの間、岩倉使節団は予備交渉を進めようとしました。けれども、アメリカ側は日本の司法制度が前時代的だという理由で、条約の改正に応じようとはしませんでした。せっかく大久保と伊藤が「全権委任状」を取りに帰った甲斐もなく、岩倉使節団は結局、アメリカとの不平等条約改正に失敗しました。ただ、使節団は条約改正とは別の、きわめて重要な目的をも帯びていました。
それは、欧米各国の社会を視察し、産業や社会の仕組みを学び取ることで、日本国内の近代化を進め、日本が外国に植民地化されることを避けようというものでした。岩倉使節団は、アメリカからヨーロッパに渡ってイギリス、フランス、ドイツ、ロシアなどを歴訪し、各国で様々な種類の工場や、産業を支える資本主義のシステム、指導者が強大な権力をふるって国内を統治する「帝国」の政治形態などを貪欲に学び取りました。
アジア唯一の近代国「日本」の取った行動とは
明治時代の日本が、水を吸うスポンジのように西洋文明を吸収し、服装や建物まで西洋化する姿勢を見せたことは、欧米の人々を驚かせました。
そして、当時の日本人は「西洋のルールを学び、その文脈で能力を発揮すれば、欧米列強から『一等国』として認めてもらえるはずだ」と考え、他国との関係構築においても「西洋式ルール」に従う姿勢をとりました。
この時に、日本が参考にした西洋式ルールの一つが『萬國公法』(ヘンリー・ホイートンというアメリカ人が1836年に書いた、当時の国際法の解説書)でした。幕末の社会変革期に活躍した坂本龍馬もこの本(宣教師が訳した日本語版が日本国内に流通していた)に着目し、日本の近代化に必要なのは、こうした西洋式ルールをきちんと学び、それを応用する能力を身につけることだと理解していました。
しかし、当時の東アジアで、そんな考えを持っていたのは、事実上日本だけでした。日本を除く東アジアでは、清国(現在の中国)を中心とする「華夷秩序」と呼ばれる世界観が根強く定着しており、日本が動向を気にしていた隣国の朝鮮国も、この「華夷秩序」の枠組みにおとなしく従う方針をとっていました。
当時の言葉で「華夏(かか)」とも呼ばれた中国が、文化的にも民族的にも「世界」の最上位を占め、周辺諸国はそれより一段も二段も低い「四夷(しい)」つまり「中国の四方にいる野蛮な異民族」と見なすという、「華夷秩序」の世界観。それは、全力で「欧米と同等の国」を目指していた当時の日本の考え方とは、まったく相容れないものでした。
こうして、東アジアでは徐々に、西洋式ルールで「欧米と対等の関係になる」ことを目指す日本と、清国中心の「華夷秩序」の枠組みが支配する大陸との間で、政治的な摩擦が生じることになります。そして、その摩擦が具体的な「対立」へと拡大した結果が、十九世紀末の朝鮮をめぐる、日本と清国の衝突、つまり「日清戦争」でした。
先に述べた通り、当時の朝鮮は東アジアでただ一国、欧米諸国との交流を拒絶する「鎖国」を続けており、強大な清国の庇護下にある限り、いざという時には清国に守ってもらえるはずだと信じて安心していました。しかし日本は、1875(明治八)年に軍艦を朝鮮に派遣して、開国させる交渉を強引に進めます(江華島事件)。
日本が朝鮮に開国を要求したのは、それが日本の利益になるからでしたが、ロシアの朝鮮進出を危惧していたアメリカ、イギリス、フランスなども、朝鮮が開国して自国との条約を結ぶことを望み、鎖国の門を押し開こうとする日本を陰で応援していました。
特にフランスとアメリカは、何度か直接、朝鮮に開国を要求して失敗し、自国の宣教師や商船の乗組員を殺されていたので、日本が朝鮮に対して「強い姿勢で鎖国の扉をこじ開ける」ことに期待を寄せていました。
その結果、日本は翌1879(明治九)年に、朝鮮との間で「日朝修好条規」という条約を締結します。その内容は、朝鮮を「独立国」と認める代わりに鎖国を解かせ、日本側に有利な条項を数多く朝鮮側に受け入れさせる、不平等条約でした。
日本はそれまで、知識と経験の不足から、欧米諸国との交渉では何度も悔しい思いをさせられていましたが、朝鮮は日本よりさらに外交の知識と経験に乏しい「アマチュア」でした。そのため、最近覚えたばかりの「欧米式の外交テクニック」を繰り出す日本に、朝鮮は全く太刀打ちできませんでした。