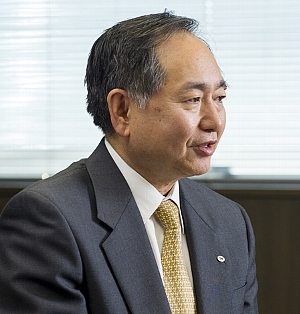Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
今月は、ヤマトホールディングスの木川眞会長が、同社の「イノベーションを生む体質」をテーマに執筆。みずほコーポレート銀行出身の木川会長が、小倉昌男以来のヤマトグループの革新をどのように受け継ごうとしてきたのか。銀行時代の経験も踏まえて聞いた(聞き手/週刊ダイヤモンド論説委員 原 英次郎)
銀行時代の修羅場経験がなければ
ヤマトグループの経営はできなかった
――ヤマトグループは革新体質をDNAとして持っていると感じました。同時に、現在の改革には「コンダクター」を自認する木川さんの経営方針も色濃く反映されているようにも見えます。
木川さんの銀行員生活の後半は、バブルの崩壊による銀行の経営危機、富士銀行、第一勧業銀行、日本興業銀行の経営統合によるみずほフィナンシャルグループの誕生と大激動の時代でした。銀行時代の経験はどう影響していますか。
木川 銀行時代の厳しく辛い経験がなければ、今の自分はなかったと思います。私が2005年にみずほコーポレート銀行からヤマト運輸に入社したときに、経営者として磨かなければならない大事なことが4つあると自覚していました。
1つ目は、「挑戦力」。後の「バリュー・ネットワーキング」構想やプロジェクトGにつながっていくのですが、リーダーは戦略を立てるだけでなく、自ら先頭に立ってやりきる姿を見せる必要があるということ。
2つ目が、「決断力」。腹をくくるということ。「バリュー・ネットワーキング」構想の旗艦として建設した羽田クロノゲートは、総額1400億円の過去にはない巨額の投資。従来の宅急便ターミナルの発想では投資回収は極めて困難でした。しかしその一方でヤマトグループが総合物流企業に生まれ変わる大きな可能性を秘めているとも感じていました。だからこそ腹をくくって投資し、新しいビジネスモデルの創出に知恵を絞り出しました。
3つ目が、「危機対応力」。これは単純なリスク管理ではなく、危機が起こった時に経営としてどう対応するかということ。危機管理は初動動作を間違えると、その後、さらに事態を悪化させることになりかねない。そのため、トップは適切な判断ができるように日頃から考え、その上で何があっても逃げない。中途半端な言い訳はしない。
最後の4つ目が、「発信力」。経営者としてやりたいことを社員に対してどう発信するかということ。経営の意思が社内に正しく伝わらなければ、会社は思うようには動きません。これらは全部、銀行時代の経験で磨かれたものです。
――木川さんの銀行時代とは、どのようなものでしたか。
木川 1973年に富士銀行に入行してヤマト運輸に転ずるまでの約30年間は、10年毎に銀行を取り巻く環境が違いました。
最初の10年は、とにかく楽しく働いていただけです。富士銀行だけでなく、銀行界全体が国や企業を健全に支えている時代でしたから、若いが故にあまり苦労もなく仕事を楽しんでいました。
次の10年はいわゆるバブル期ですが、私は金融自由化によって新しい仕事が次々と生まれる中で、それに対応していく仕事をやらせてもらえた10年でした。
84年の「日米円ドル委員会報告」をはじめに、日本でも金融自由化が本格化していくなかで、最初は金融政策や金利動向をどのように読んでいけばよいのかという「日銀ウォッチャー」のような仕事に携わりました。これは富士銀行の中での第一号でしたし、その後ALM(資産負債の総合管理)という、新しい金融リスク管理の立ち上げにも関わりました。
そして最後の10年間は、修羅場でした。経営幹部としてバブル崩壊の後処理に追われ、多額の不良債権処理で富士銀行自体が破綻寸前にまで追い込まれ、三行統合で何とか危機を脱したと思ったらシステム障害。でも一番の修羅場は2001年ニューヨークで起こった「9.11テロ事件」です。