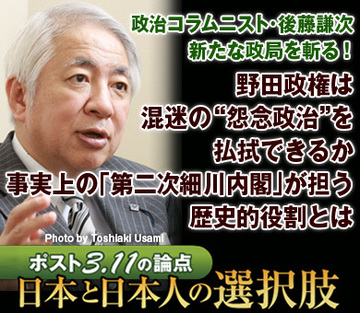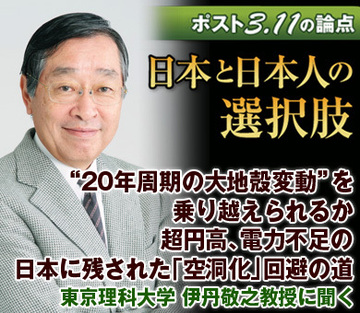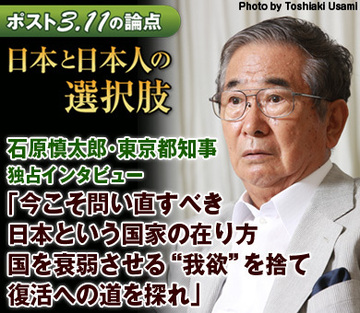経済のグローバル化が進むなか、都市が膨張を続けている。国連によると、2030年の世界人口は約80億人にまで増え、その60%は都市に暮らすようになると予測されている。ヒト、モノ、カネを巡る都市間の競争が激しさを増すなかで、東日本の復興という重い課題を背負ったままの日本の都市はどのようなビジョンと戦略を持って臨むべきなのか。東京と地方都市の2つのテーマに分け、都市に詳しい2人の識者にそれぞれうかがった。
今回は、建築家の隈研吾氏に話をうかがう。これまで公共事業によってなんとか延命を続けてきた地方都市。しかし、その延命措置が限界を迎えようとしていたさなか、東日本大震災は発生した。以前と比較できないほど厳しい状況へと追い込まれた地方都市に希望はあるのか?(聞き手/フリーライター 曲沼美恵)
「上から目線」ではなく、
「下から目線」の都市計画
――東日本大震災の復興に際し、かつての全国総合開発計画(全総)のようなものを打ち立てる必要がある、という意見があります。これに対し、隈さんはどうお考えですか?
 隈研吾(くま・けんご)/1954年生まれ。建築家。東京大学大学院教授。スコットランドやスペイン、フランス、中国など海外のプロジェクトを手がけるほか、高知県檮原町をはじめ、地方の小さなプロジェクトやまちおこしにも詳しい。おもな著書に『負ける建築』(岩波書店)や『新・都市論TOKYO』『新・ムラ論TOKYO』(いずれも集英社新書、ジャーナリスト、清野由美氏との共著)
隈研吾(くま・けんご)/1954年生まれ。建築家。東京大学大学院教授。スコットランドやスペイン、フランス、中国など海外のプロジェクトを手がけるほか、高知県檮原町をはじめ、地方の小さなプロジェクトやまちおこしにも詳しい。おもな著書に『負ける建築』(岩波書店)や『新・都市論TOKYO』『新・ムラ論TOKYO』(いずれも集英社新書、ジャーナリスト、清野由美氏との共著)
建築でも都市計画でも、ぼくは絵というものにはそもそも未来への夢や希望のようなものが含まれていなくちゃいけない、と思っています。じゃあ、それを誰が持っているのかと言えば、やはり、その場所に暮らす人たちです。
全総(全国総合開発計画)のように第三者が「上から目線」で計画を立てていってうまくいった時代というのは、政治や官僚に対して社会が強い信頼感を持てた時代です。ぼくらはもう、そこに戻ろうとしても戻れないわけだし、戻る必要もない。そんな昔の方法に戻るよりは、今ある小さな芽を大事にして、下からの知恵やエネルギーを集め、たくさんの人を巻き込みながらそれを大きくしていくやり方のほうがいい。
これはぼくの好きなエピソードですが、ル・コルビジェがアルジェリアの都市計画を作って政府に見せた時、「こんな壮大な計画、いつできるかわからない」と反論された。そしたら彼は「いつできるかはわからないけれども、明日からでもすぐに取りかかれますよ」と答えた。都市を作るというのは本来、そういう性格のものです。今日・明日できることはなにか、とひたすら前に進んでいって、気がついたら想像もできなかった大きな夢に到達している。
今はまず、一人ひとりが下手でもいいから自分の夢や理想を絵に描いて、恥ずかしがらずに裸になったつもりで一生懸命に説明して、人にも夢を共有してもらう。そういう地道な、地に足のついた活動を積み重ねていくことだろう、という気がします。