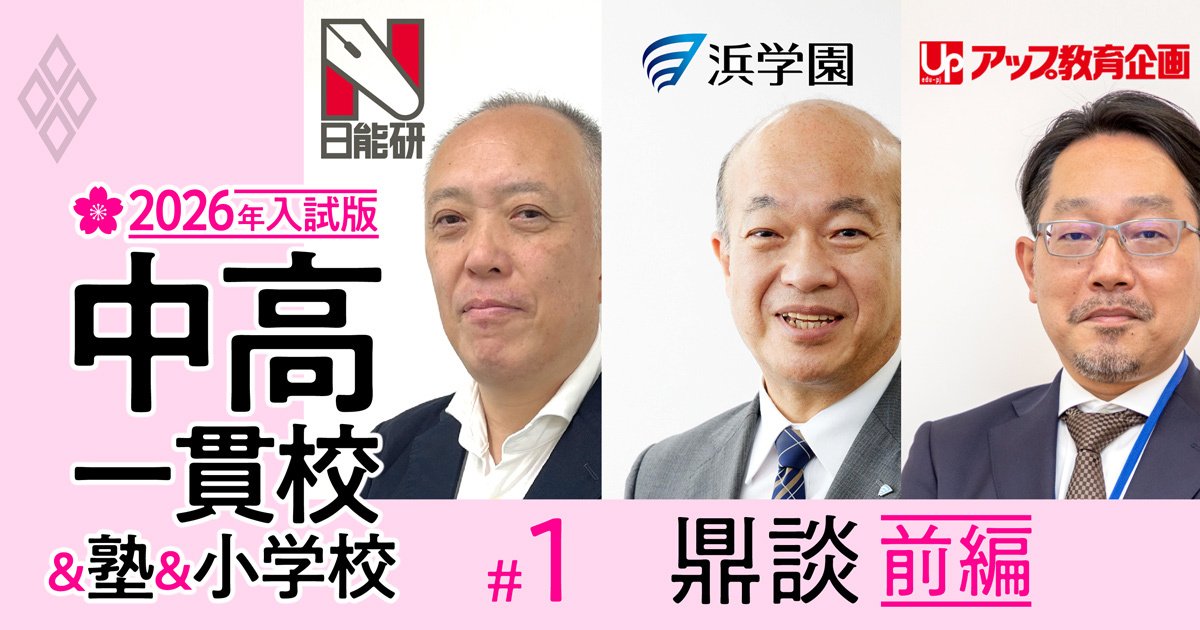写真はイメージです
写真はイメージです
大阪府箕面(みのお)市では、「公教育改革」が進んでいる。教育委員の過半数を公募することで注目を集める箕面市だが、特筆すべきは、教育現場で“タブー”となりがちな「数値」をもとにした改善だ。生徒の学力の経年変化を追い、校長が現場の教師を指導する際にも数値を根拠にする。こうした取り組みの結果として生徒の学力を引き上げている。この箕面市の取り組みは、公教育のクオリティを飛躍的に高める可能性がある。
貧困家庭の子どもは貧困に陥りやすいという、いわゆる「貧困連鎖」が日本ならず世界的にも問題視されているが、これを断ち切るためにも公教育の果たす役割は非常に大きい。というのも、私立小中学校の生徒数は全国で31万人[*1]、それに対して、公立小中学校の生徒数は全国で約940万人[*1]と、公立小中学校の生徒数は全体の約97%にのぼるからだ。さらに言うと、貧困家庭の子どもの多くは公立学校に通うことになるため、この人数差以上に公教育にはその責任が問われる。
ちなみに筆者自身は公立の小中学校に通ったが、率直に言うと、その教え方について懐疑的である。というのも、学力の高い生徒にとっては、難関校の受験に通用しない授業を受けることとなる一方で、授業について行くことができない生徒もいる。多様な生徒一人ひとりにきめ細かな対応ができていないことが懸念される。
学習塾で感じた合理性、講師の評価が生徒の成績推移と連動
筆者の体験として、中学時代に通った学習塾では、生徒の学力レベルに応じてクラス分けが行われ、成績の上下に伴ってクラスも入れ替わっていた。