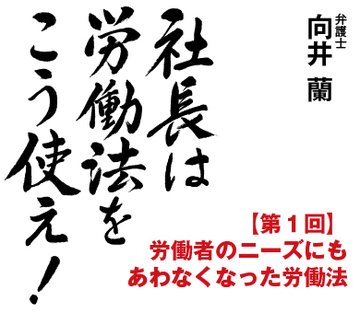気鋭の労務専門弁護士である向井蘭氏に、労働法と労務トラブルのポイントを「経営者のために」解説してもらう連載です。
第2回となる今回は、労働法が定める「労働者」や「管理監督者」といった定義が、多くの人の認識とは異なっているという、労務の大切なポイントを解説します。
働いている人すべてが労働法上の「労働者」というわけではない
労働基準法では労働者を「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。つまり、労働して給料をもらう人を労働者と称しているわけですが、一概に、仕事をしてお金をもらう人すべてが労働者であるとは言えません。
たとえばNHKの受信料を集金する人に関しては、裁判所は一貫して労働者と認めていません。集金の時間、場所、方法について集金人の裁量にゆだねられていること、再委託が可能なこと、そして賃金が時給ではなく歩合で支払われていることを理由に、労働者と認めないのです。
またプロ野球選手にも労働組合がありますが、ひとたびプロ野球選手個人と球団間のトラブルが起きて裁判となれば、裁判所が選手を労働基準法上の労働者として認めるかどうかはわかりません。
1年のうち6分の1は野球選手としての活動を連続して休んでいること、公式練習や試合以外の指揮命令はほとんどないこと、副業をもっていることなどを理由に、労働者として認められず、労働基準法は適用されない可能性が高いです。
他にも、働く場所の拘束が少ない、上司からの指示を受けない、副業が可能という条件を満たす人は、多くの場合、労働者として認められません。たとえばフリーのライターや翻訳者などの職業がこれに当たります。
このように労働者として認められるかどうか曖昧な人は、意外とたくさんいます。労働基準法が制定された時代とは経済状況も社会情勢もまったく異なる今、労働者は弱いという前提も、労働者の定義も見直すべきなのかもしれません。細分化した産業構造に合わせて、業界、業種ごとに特例をおくなど、時代に合わせた措置が必要ではないでしょうか。