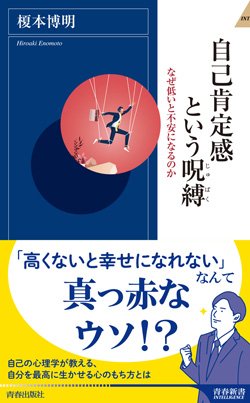これには、児童期から思春期にかけての認知能力の発達により、抽象的思考ができるようになることで、理想自己を高く掲げるようになり、また現実自己を厳しい目でみつめるようになることが関係しています。
その証拠に、別の調査では、小学5年生では理想自己と現実自己のギャップとIQとの間になんの関係もないけど、より年長になると、同じ学年でもIQの高い者の方がギャップが大きくなることが示されています。
現実自己と理想自己のギャップの大きさは、認知能力の発達のしるしなのです。心理的に成熟し、理想を高く掲げると同時に、現実の自分を厳しい目でみつめるために、自分の未熟さや至らなさを感じ、自己嫌悪に陥るわけです。自分はまだまだだと自己嫌悪に陥るのは、向上心があることの裏返しとも言えます。
ゆえに、ずっと自己肯定したままというのは、心理的な成熟が滞っているとみなすこともできるのです。理想を高く掲げたり、自分を批判的に振り返ったりすることがないため、自己肯定していられるわけです。そこには自己嫌悪もなければ、向上心もみられません。
自己肯定感には向上心が含まれるということを考えたら、要求水準を下げて自分に満足すればいいということではないはずです。自分をさらに向上させていこうという心の構えが必要です。そんな向上心のある自分だからこそ、真に自分を肯定できるのです。