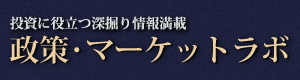最大の失敗は
不良債権処理の先送り
――第5章で、そこまでの章をまとめる形で、「失われた30年」の要因を集約していますが、個々の要因における再帰的思考の欠如について具体的に教えてください。
政策の失敗は30年間で約10〜15年間ごとに現出し、企業経営の課題と複合して、日本経済の長期停滞をもたらしたと思います。
最大の失敗は、1990年代〜2005年と15年間もかかった不良債権処理の遅れです。バブル崩壊による巨額の不良債権問題は、世界各地で起きていますが、他国では通常3年程度で処理されています。
日本での長期化要因は、経営者や為政者の課題先送り意識や慣行にあります。当時、債権者の銀行には「不良債権処理=債権放棄=銀行員失格」、債務者の経営者には「倒産=清算=企業の死」の観念が固まっていて、それを回避したかった。いずれ株価や地価が回復して解決できると思い込み、対応先送りで自分たちは逃げ切れるという姿勢でした。
銀行は債権の一部放棄によって回収額が増える可能性があるとか、企業経営者は倒産後の事業再生や新事業育成で成長を回復するという発想がありませんでした。為政者も同様の精神構造で、有効な政策実施を怠りました。
市場の圧力などから、銀行や証券会社が経営破綻に追い込まれ、その度ごとのびぼう策により、日本経済全体の成長力が失われていきました。この点において、第二の政策失敗があります。過剰債務等で疲弊した企業の金利負担を軽くする金融緩和を長期継続し、低収益性企業の存続を支援しましたが、これは社会全体として一時的な痛み止めになる一方、経済の新陳代謝を妨げ、成長を抑制することになりました。企業は、リストラが回避できても、設備投資や人材育成投資を行えず、日本全体で人的資本の劣化につながりました。
――いわゆる「ゾンビ企業」を多く生み出したことで、日本全体での新陳代謝が抑制されてしまったのですね。
本書第1章で詳述しましたが、その帰結としての「不良債権処理の後も、長期停滞が続いた理由」を最後にまとめました。「企業間分業の萎縮」と「人的資本の劣化」です。
そのメカニズムは、(1)不良債権の大量発生による企業間の相互不振で、企業間の分業が崩れ、生産性が低下する。(2)低生産性の下で、教育や技術向上など人への投資が低調になり、人的資本が劣化する。(3)不良債権処理が長引いて、人的資本が相当程度に劣化すると、企業間で元通りに分業しても採算性が取れなくなるので、企業はサプライチェーンを再生しない。(4)企業間分業が再生しなければ、経済全体で低生産性が続き、人的資本の劣化が進む。人的資本の劣化が進むと、企業間分業は採算が取れないので再生しない、という悪循環が続く、というものです。
2010年代には、異次元緩和による金利負担の長期低減で、財政規律が緩み、政府債務は膨らみ続けます。企業においては、アニマルスピリットを衰退させ、イノベーションを阻害しました。本書に書きましたが、2021年頃から「低金利政策の長期化は、経済成長率を低下させる」という研究が海外を中心に増えています。
また、人口減少と超高齢化という人口動態も、長期経済低迷の背景にあります。少子・高齢化が進む中で財政・社会保障制度の持続性に国民全体が不安を感じ、貯蓄性向を高めます。多少景気が回復しても、消費を増やそうとは考えません。
――2001年に小林教授が加藤創太氏(現在、東京財団政策研究所研究主幹)と共に著した『日本経済の罠』(日本経済新聞社)では、それまでの「失われた10年」を分析しています。同書ではすでに、既存の経済理論や経済政策の限界を示し、「不良債権問題の経済学」「バランスシートの罠」という章を設けて詳述していますが、日本の為政者には受け入れらなかったのでしょうか。
当時の経済学や政策決定過程に限界がありました。過去の失敗の蓄積が将来に影響するという体系になっていなかった。1990年代末になって、ようやくマクロ経済学にバランスシートの要素が入って、過去の失敗の蓄積が将来に影響するという問題を分析できるようになりました。
それ以前は、バランスシート変数の問題に着目したマクロ経済学の研究は、ベン・バーナンキ(プリンストン大学教授、後に米国連邦準備制度理事会(FRB)議長、2022年ノーベル経済学賞受賞)による1930年代の大恐慌の研究などごく少数でした。バーナンキの83年の論文では、大恐慌の悪化原因は、貨幣量の収縮にあるという通説だけではなく、銀行危機で銀行から企業等への信用供与が機能不全となったことで総需要が収縮したことにあると論じています。しかし当時この理論はメジャーではなく、その後、洗練され、99年になって標準的なマクロ経済政策の分析ツールとして認められるようになります。
日本が不良債権で苦しんでいた1990年代初頭にはそういう理論はありませんでした。当時の教科書にあるケインズ経済学ではとにかく財政出動、金融緩和で経済を刺激すれば、景気はそのうち回復すると考えられていたのです。実際、そうした経済対策を展開しました。不良債権処理は確かにやるべきことだが、経済政策とは違うというイメージでした。大問題ではあるけれども、それ自体は経済の先行きにさほど影響を与えないんじゃないかという考えを、当時の経済学者や為政者は持っていたと思います。
――2000年以前に私たちが学んだケインズ経済学では、景気悪化時には、中央銀行が低金利政策を実施し、0%近くまで下げても民間投資が動き出さない「流動性の罠」に陥ったら、政府が積極的な財政政策を発動するのが良いと言うものでした。
流動性の罠についてはちょっと難しい問題があります。日本の場合、ゼロ金利政策を実施したのが1999年で、流動性の罠に陥ったのがこの頃でした。しかし、財政政策はそれまでに限界まで実施していて、これ以上の財政拡大の余地がないというコンセンサスになっていたと思います。経済理論では、流動性の罠に陥ったら、金融緩和は効かないから財政拡大するということになっていますが、現実には財政は出し尽くしていたので、次に打つ手がない状態だったのです。
そこに、「将来見通しの期待を変える」「インフレ期待を作れば大丈夫」という新しい理論が出てきた。それが、いわゆる「リフレ派」の理論です。それまでのケインズ経済学の教科書には書いていないことを唱えた新しい学派です。
――本書第2章で詳述されているように、1998年頃の日本経済については、ポール・クルーグマン(当時マサチューセッツ工科大学教授、2008年にノーベル経済学賞受賞)も、「期待を操作すれば良い」と提言していました。
クルーグマンは、日本経済は縮小していくと予想し、その予想のもとでは自然利子率(需要と供給が一致する利子率)はマイナスになっていると主張しました。クルーグマンの議論は、日本経済の長期縮小は受け容れた上で、足下の需要と供給が一致するようにさせるために、将来のインフレ期待(予想)を醸成し、現実の金利をマイナスの自然利子率に近づけて、需要喚起を促す策を提言していました。
2000年くらいまでにはバランスシート問題が米国では認識されていたけど、次善の政策として、リフレのような、期待に働きかけることが有効だと思われていました。不良債権処理は社会全体に大きな痛みを伴うので、アカデミズムから政策提言として不良債権処理の推進案はあまり出てきませんでした。期待に働きかけるリフレ案のほうが誰も傷つけず、痛みを伴わないので、そちらの方が言いやすかったのです。
実際、欧米においても、リフレ政策が望ましいということで、2008年のリーマンショック、10年代の欧州債務危機でも、大規模に金融を緩和しました。ただし、それによって期待が変わったかどうかという点はまだ論争が続いています。理論的に必ず期待を変えられるとは言い切れていません。どんどん金融緩和をやって量的緩和とかフォワードガイダンスをやれば、何がしかインフレ的になるということは各国で経験したけれども、それは政策が効いたからかどうか、疑問視する研究者もいます。