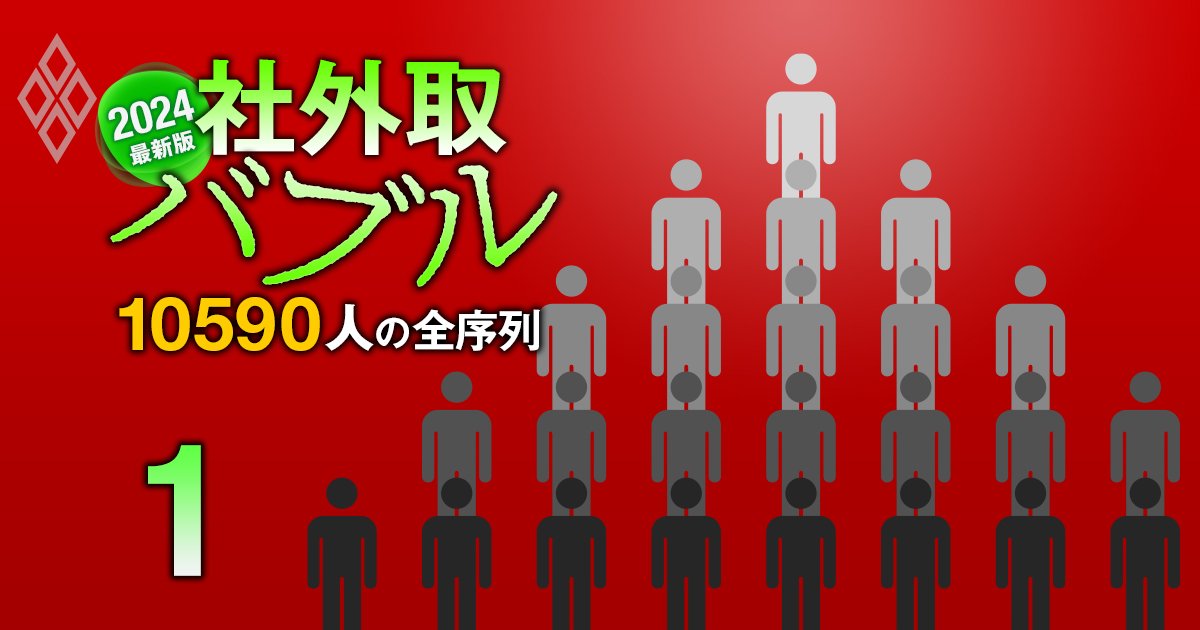それが今の「花から花へ」に変わったのは、戦後・昭和22(1947)年。終戦によってそれまで神と仰がれていた天皇が「人間宣言」をなさった。国家主義から民主主義の時代へと移り、「栄ゆる御代」は「花から花へ」と変わったのだ。
さてその時点まで、この歌には2番の歌詞も存在していたのをご存じだろうか。
「おきよおきよ、ねぐらのすずめ。朝日のひかりのさしこぬさきに」。
「ねぐらをいでて、こずえにとまり、あそべよすずめ、うたえよすずめ」。
なぜか「ちょうちょ」は、2番になると「すずめ」になっているのだ。それどころか、3番も4番も歌詩があった。明治29(1896)年、「ちょうちょ」がはじめて教科書に登場してから15年後の教育音楽講習会発行の教科書『新編教育唱歌集』から3番と4番が加えられている。
 『歳時記を唄った童謡の謎 こんなに深い意味だった』(笠間書院)
『歳時記を唄った童謡の謎 こんなに深い意味だった』(笠間書院)合田道人 著
「ちょうちょ」は2番ですずめになり、3番になると、「とんぼとんぼ、こちきてとまれ」、なんと「とんぼ」になるのである。さらに、「つばめつばめ、飛びこよつばめ、古巣を忘れず今年もここに」。なんと!「つばめ」に変身してしまうのだ。2番以降の詩は稲垣千穎が作った。
唱歌というものは歌を通じ、子どもたちにいろいろなことを教える役目を持っていた。学びである。この4つの詩で、子どもたちにわが国の四季を教えたのである。
ちょうちょで春の訪れを知らせ、その後やってくる夏、夏の朝をすずめで表現した。さらに秋は当然、赤とんぼ、そして冬。早く寒い冬から春に変わって、つばめよ、いつもの年と同じようにわが家の古巣にかえっておいで!と歌った。
ひとつの歌で空飛ぶ昆虫や鳥を覚え、さらにそれらを通して日本独特の美しい春夏秋冬を教えていたのである。