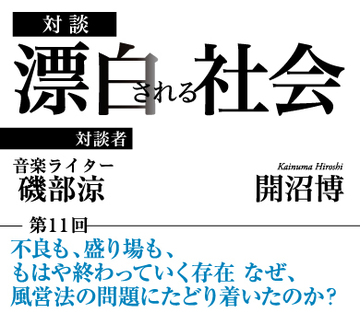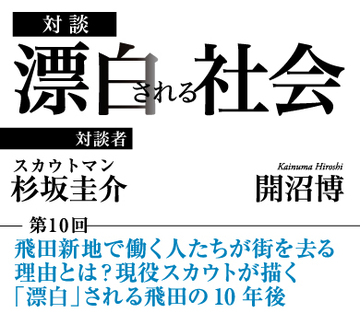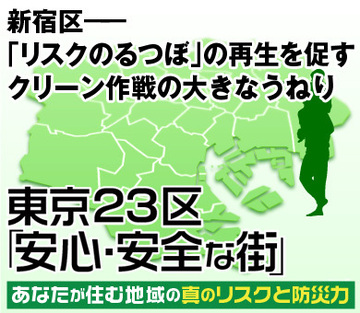売春島や歌舞伎町といった「見て見ぬふり」をされる現実に踏み込む、社会学者・開沼博。そして、クラブ規制で注目を浴びる風営法の問題に正面からぶつかり、発信をつづける、音楽ライター・磯部涼。『漂白される社会』(ダイヤモンド社)の刊行を記念して、ニュースからはこぼれ落ちる、「漂白」される繁華街の現状を明らかにする異色対談。
六本木の有名クラブVANITY摘発が大きな話題を呼んだクラブ規制の問題。実は、摘発に踏み切った警察には、ある明確な意図があった。第2回は、取り締まる側と取り締まられる側双方の視点から、踊ってはいけない国の現在に迫る。対談は全5回。
現場の主張と乖離する改正運動
開沼 『踊ってはいけない国、日本』と『踊ってはいけない国で、踊り続けるために』(以上、河出書房新社)は、タイトルも見た目も似ているものの、2冊目で大きく方向転換をされているようにも見えます。また、磯部さんご自身もそれを「転向と見えるかもしれない」とも書かれています。
勝手に単純化してまとめると、1冊目では過剰規制反対を盛り上げて「押し切るぞ!」という勢いがあった。そのために、運動と現場のリアリティを切り捨ててしまった部分があるかもしれない、と。ところが2冊目では、具体的にどう変えていくのかに向かって、現場のリアリティと付き合いながら、条件闘争も辞さない立場になった、と。
これは、「条件闘争路線に寝返るなんて、妥協しているじゃないか」とも見られかねないわけですね。磯部さんがそのような心変わりをされた理由を聞かせてください。
 磯部涼(いそべ・りょう)
磯部涼(いそべ・りょう)音楽ライター。1978年、千葉県千葉市生まれ。1990年代末から商業誌への寄稿を開始し、主に、日本のマイナーな音楽の現場について執筆してきた。著作に、『ヒーローはいつだって君をがっかりさせる』(太田出版)、『プロジェクトFUKUSHIMA!2011/3.11-8.15 いま文化に何ができるか』(K&B)、『音楽が終わって、人生が始まる』(アスペクト)がある。
近年は、日本のクラブ業界においてタブー視されてきた風営法の問題解決に取り組み、同問題をテーマにした『踊ってはいけない国、日本』(河出書房新社)と、その続編『踊ってはいけない国で、踊り続けるには』(同)の編著者を務めた。
撮影:植本一子
磯部 1冊目の反省として、自分がつくるとどうも左翼臭くなるなぁというのがあったんですね。
開沼 それは、自分を冷静に見た時にということですか?
磯部 過剰規制というロジックがそもそも左翼的じゃないですか。
開沼 反権力、反体制を前提としている。
磯部 そうです。あるいは疎外論とか。
開沼 なるほど。
磯部 本を読んでもらえば、そんなに単純なことは言っていないとわかってもらえると思うんですけど、「まえがき」のように短い文章で煽らなければいけないときは、どうしても左翼的なロジックに頼ることになってしまって。
そもそも、タイトルがミス・リードですからね。あれだけを目にした人が、「表現の自由を守れ!」「自由が規制されている!」という主張がされている本なんだという印象を持ってしまっても仕方がない。
昨年の風営法改正運動を先導したLet's DANCE署名推進委員会は、左翼的な人脈の基に成り立っていました。それは、隠していることでも何でもなく、彼らのホームページにある通り、共同代表は中村和雄さんが務めているわけですが、彼は京都の人権派弁護士で、2008年、2012年と日本共産党の推薦で市長選に出馬していますからね。
中村さんをトップにしたLet's Danceは、まさに、「表現の自由を守れ!」と主張する運動でもあった。ただ、事業者の中にはまた違ったリアリティを持っている人たちも多いんです。結果、運動の現場と文化の現場が乖離してしまった。その様子を間近で見ていたので、これはまずいなと思ったんです。
開沼 その「まずいな」という感覚が1冊目と2冊目の間で確実に生じた変化だと?
磯部 そうですね。