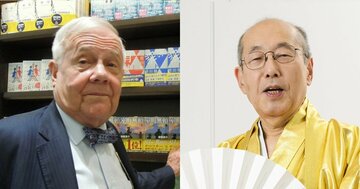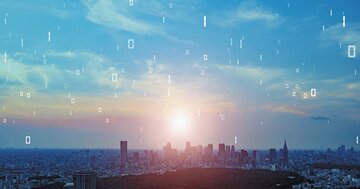救済ばかりか「復活」まで視野に
東京電力を取り巻く様々な思惑
福島第一原子力発電所の事故からまもなく3年。復興から取り残された形の福島では、「もう戻るのはあきらめた」との声が多く聞かれる。だが、事故を起こした当の東京電力は、さまざまな思惑のなかで“救済”されようとしているばかりか、“復活”まで虎視眈々と狙っている。「復興の加速」という美辞麗句の影で――。
2013年9月6日、ロシア・サンクトペテルブルクを出発し、アルゼンチン・ブエノスアイレスへ向かう政府専用機、ボーイング747の機体前方の秘書官席では言い知れぬ緊張が漂っていた。
わずか30時間後に、20年五輪招致の総会を控え、安倍晋三首相以下、官邸スタッフの元には現地から「福島第1原子力発電所の汚染水問題がネックとなり、苦戦」との情報が伝えられていた。また日本では、東京電力の下河邉和彦会長が「五輪で負ければ辞める」と周囲に漏らしていた。
「汚染水には触れざるを得ない」
官邸スタッフは、総会で首相が行うスピーチ原稿を書き直し、首相も機内で演説の練習を続けた。ギリギリの路線変更だった。
こうして、東京五輪招致の決め手になった「汚染水アンダー・コントロール」の演説は生まれた。
汚染水対策がおぼつかないこともあって、後の国会審議で、この「アンダー・コントロール」が厳しい追及を受けることになるのだが、一躍“国際公約”となったことで、福島第1原発事故の果てしなく厳しい現実が耳目を集めることになり、国も本格的に対応せざるを得なくなった。
「福島の問題は国が責任を持たないと、前進しない」。首相のスピーチからさかのぼること2週間前。自民党内でも福島をめぐる議論がスタートしていた。
東京・永田町の自民党本部5階にある東日本大震災復興加速化本部に、大島理森本部長が復興庁幹部と共に、経済産業省や財務省、そして環境省の局長クラスを次々と呼び、「勉強会」を開いた。