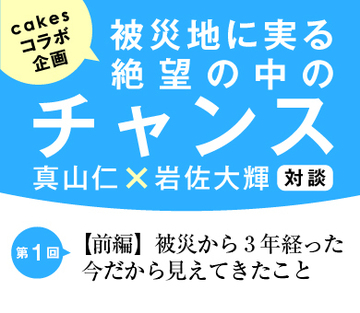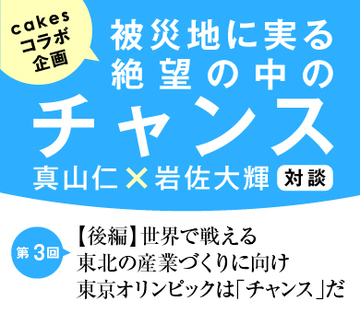『ハゲタカ』シリーズなどで知られる、作家の真山仁さん。デビュー10周年を記念した本連載では、第一弾として、ロングインタビューのダイジェストをお送りします(完全版はcakes掲載)。真山さんの新聞記者時代の先輩である中央公論新社の石田汗太さんが聞き手となり、旧知の仲だからこそ引き出せた各作品への思いや作品づくりの裏側をお楽しみください。常に日本の「今」とともに歩み、作品を送り出してきた真山仁さんと日本の10年を、ともに振り返っていきましょう!
希望なき21世紀のデビューは
必然であり、作家として恵まれている
――真山さんの公式デビュー作品は2004年刊の『ハゲタカ』(ダイヤモンド社、現講談社文庫)ですね。しかし実は03年に「香住究」の合作ペンネームで『連鎖破綻 ダブルギアリング』(ダイヤモンド社)を出している。この「幻のデビュー作」が、今年12月に角川文庫(詳細は本記事の最終ページ)になるそうですね。まずは03年以後、作家としての真山さんの目に、日本がどのように映ってきたかをおうかがいできますか。
 真山仁(まやま・じん) 小説家。1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部政治学科卒業。新聞記者、フリーライターを経て、2004年企業買収をめぐる熱き人間ドラマ『ハゲタカ』でデビュー。2007年に『ハゲタカ』『ハゲタカ2(『バイアウト』改題)』を原作とするNHK土曜ドラマ『ハゲタカ』が放映され、大きな反響を呼ぶ。同ドラマは国内外で多数の賞を受賞した。ほかに、地熱発電をテーマにした『マグマ』も、2012年にWOWOWでドラマ化された。その他の著書に、日本の食と農業に斬り込んだ『黙示』、中国での原発建設を描いた『ベイジン』、短篇集『プライド』、3.11後の政治を舞台にした『コラプティオ』、「ハゲタカ」シリーズ第4弾となる『グリード』、『そして、星の輝く夜がくる』などがある。10月30日に新刊『売国』(文藝春秋)を刊行予定。2014年でデビュー10周年を迎えた。【写真:長屋和茂】
真山仁(まやま・じん) 小説家。1962年大阪府生まれ。同志社大学法学部政治学科卒業。新聞記者、フリーライターを経て、2004年企業買収をめぐる熱き人間ドラマ『ハゲタカ』でデビュー。2007年に『ハゲタカ』『ハゲタカ2(『バイアウト』改題)』を原作とするNHK土曜ドラマ『ハゲタカ』が放映され、大きな反響を呼ぶ。同ドラマは国内外で多数の賞を受賞した。ほかに、地熱発電をテーマにした『マグマ』も、2012年にWOWOWでドラマ化された。その他の著書に、日本の食と農業に斬り込んだ『黙示』、中国での原発建設を描いた『ベイジン』、短篇集『プライド』、3.11後の政治を舞台にした『コラプティオ』、「ハゲタカ」シリーズ第4弾となる『グリード』、『そして、星の輝く夜がくる』などがある。10月30日に新刊『売国』(文藝春秋)を刊行予定。2014年でデビュー10周年を迎えた。【写真:長屋和茂】
真山 その問いに対して、まっすぐな答えじゃないかもしれないんですけど、われわれが子どもの頃は「21世紀は夢と希望の世紀だ」というイメージがありました。たぶん手塚治虫さんのアニメやマンガの影響も大きいと思うんですけれど、現実には、21世紀を迎える手前で、日本からはその希望がすべて失われてしまいました。
日本の戦後史は、いろいろ苦難は多かったけれど、俯瞰してみれば右肩上がりの時代が長かったと思います。しかし、バブル経済崩壊後の日本は躓きの連続で、「失われた10年」どころか「失われた20年」と言われて、ようやく景気が上向きになりかけた2008年にリーマン・ショックが起きた。そして、そこから立ち直ろうとした矢先の11年に、東日本大震災と原発事故です。そういう意味では、21世紀は、日本という国がアイデンティティーを喪失して始まった世紀だと思うんですよ。
――2000年代は、のっけから先行き不透明感に覆われてました。
真山 さらに突き詰めると、そもそも日本ってどんな国なのか、わからなくなっていると思うんです。『コラプティオ』(文藝春秋、現文春文庫)の文庫コピーではないですが、「おまえは何者なのだ?」という問いに自ら答えられない国になってしまった。バブルが弾けるまでは、「がんばったら報われる国」という答えもあり得ました。それが完全に無効になった今、われわれはもう、どう生きたらいいのかわからなくなっている。
 真山仁とニッポンの10年を振り返る
真山仁とニッポンの10年を振り返る拡大画像表示
そんな、行く先が見えない時代に小説を書いていることは、非常に恵まれていると私は思っているんですね。
――作家として自分は恵まれていると。逆境ではなく。
真山 そうです。少し前までの日本は、昨日も今日も明日も変わらない、がんばれば報われる社会だった。それがもはや、3ヵ月後の未来さえ見通せない。そんな状況は、社会を見ながらものを書く人間にとっては、不謹慎と叱られるかもしれませんが、ずっと小説のネタに困らないということなんです。社会の変化の中に、危うい隙間や落とし穴がいくらでも見えてきますからね。
だから、小説を自分の内側からひねり出す必要がなく、自分がこの社会をどう考えるかによって、小説のきっかけがどんどん生まれてくる。これは、単なる明るい希望を書きたくない私のような作家にとっては、時代が味方してくれているようなものです。
まあ、自分で自分にそう言い聞かせているところもあります。2000年代に自分がデビューしたのは必然なんだ、早くデビューしなくてよかったんだってね。