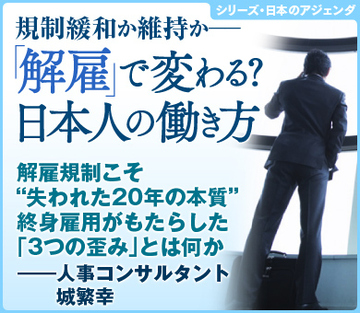筆者は2000年7月から2007年7月まで、ちょうど7年間英国に留学していた。それは、日本で「郵政民営化の実現」を掲げる小泉純一郎氏が首相に就任し、構造改革を断行した時期と、小泉内閣退陣後、第一次安倍晋三内閣の政権運営が混乱し、改革の結果としての「格差拡大」が社会問題となり始めた時期と重なる。当時、英国社会の中にいながら、日本を外からみて、気になることがあった。
構造改革後の英国社会:
生き生きとした労働者階級の人たち
英国は、日本より約15年早く「鉄の女」マーガレット・サッチャー首相(当時)の下、減税、金融ビッグバンなどの規制緩和、国営企業の民営化などの「構造改革」を断行した。サッチャー首相のリーダーシップで「英国病」を克服し、筆者が住んでいた頃の英国は、長期的な好景気を謳歌していた。
英国から遅れて構造改革に取り組んでいた日本は、反対派の激しい抵抗により、改革が骨抜きになっていくことが続いた。日本では、強いリーダーシップで改革を断行したサッチャー首相の人気が高かった。
一方で、英国内ではサッチャー首相は庶民から嫌われ、不人気であった。英国在住の間、筆者はいろいろな英国人と接したが、「日本人の感覚」でサッチャー元首相を称賛するようなことを言ったら、皆、嫌な顔をしたのには驚かされたものだった(同様の反応は、ロシア人にミハイル・ゴルバチョフ元ソ連大統領の話をした時にもよく見られた)。
ただ、サッチャー元首相は酷評されてはいたが、英国では「格差問題」が、日本ほど深刻な社会問題になっているわけではなかった。格差の広がりは問題視されていたが、日本のように自殺が急増したり、異常犯罪が増加することはそれほどなかった。
むしろ、英国人は非常に明るく日常生活を謳歌していた。上位層、中間層との所得格差が広がったとされた労働者階級はどうだったか。平日の午後、大学の近くの街を歩いてみると、まだ昼間だというのに、パブには労働者と思われる男が多数いて、楽しそうにビールを飲んでいた。
話題は、週末のフットボールのことだ。地元チームの贔屓の若手選手のことを熱く語っていた。彼らは、午前中は建設作業員などをして少し働き、午後はこんな調子だった。どういう仕組みでビール代を稼げるのはよくわからないが、とにかく貧しさに苦しんでいる様子ではなかった。
週末は、贔屓のチームのユニフォームを着て、フットボール場でビールを片手に応援である。大学から車で1時間くらいの街に、ウェストブロミッチ・アルビオン(WBA)というイングランド・プレミアリーグのチームがあり、当時稲本潤一選手が在籍していた。筆者は、博士論文の執筆の傍ら、毎週のようにサッカー場に観戦に行っていた時期があったが、サッカー場のスタンドで、労働者のおじさんたちは優しく、明るかった。「日本の兄ちゃん、今日もジュンイチは試合に出てないな。でも、心配するな。あいつはいい選手だぜ!」という調子で、いつも気さくに話しかけてくれた。