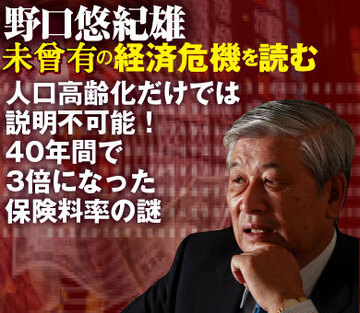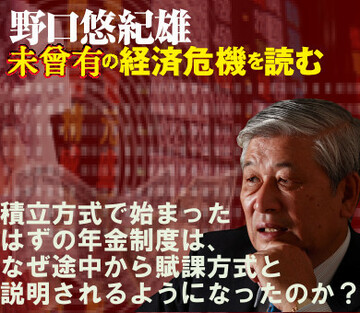厚生年金の将来の財政状況は、「財政検証」として推計されている。その最新版は、2009年の2月に発表されたものだ。厚生年金についての「基本ケース」の結果は、【図表1】に示すとおりである。
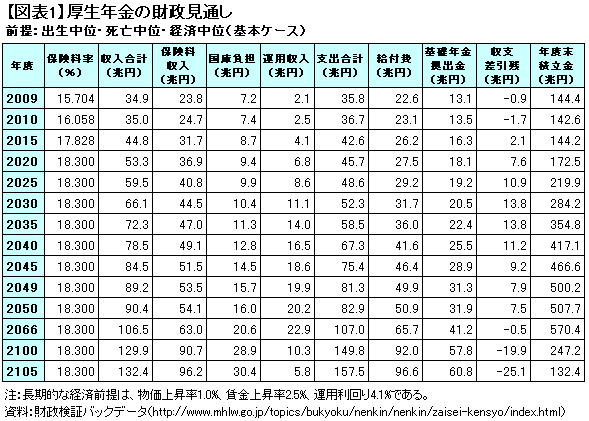
これによれば、積立金は現在144.4兆円だが、今後増える。2049年には500兆円を超えて、なお増加する。2066年からは年間収支がマイナスになり積立金の取り崩しが始まるが、2105年になっても、まだ132兆円の残高がある。つまり、今後100年間は、積立金はなくならないわけだ。これを見ている限り、「年金財政が破綻する」などということはありえないように思われる。
しかし、この数字は、一定の仮定に基づいて計算されたものである。「今後50年以上の期間にわたって積立金が増え続ける」という結果は、経済的な前提条件に強く依存しているのである。それが満たされなければ、結果は大きく変わる。
とくに問題なのは、この連載の第65回で述べたように、賃金上昇率が2.5%、積立金の運用利回りが4.1%と想定されていることだ。これらは、明らかに過大な想定と考えられる。
「基本ケース」の経済想定は楽観的過ぎる
ここでは、賃金の問題を取り上げよう。日本の賃金は、1990年代末までは増加し続けていた。日本の年金制度は、こうした経済情勢を基本にして設計されている。すなわち、経済が成長し、物価や賃金は上昇するものとして設計されてきたのである。したがって、問題とされたのは、名目値で決められている年金が、上昇する賃金にいかにキャッチアップできるかということであった。このために、インフレスライドの制度が導入されていたのである。
問題は、この傾向が将来も続くと考えてよいかどうかである。
実は、すでに10年以上前から、この前提は満たされなくなっている。すなわち、賃金の上昇率は停滞し、さらには絶対額が減少するようになった。たとえば「現金給与総額」(事業規模5人以上)の指数を見ると、1997年の108.5をピークとして、それ以降はほぼ一貫して低下している。2009年においては95.1であるから、この間に13%強下落したわけだ。