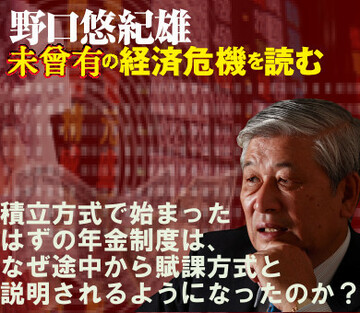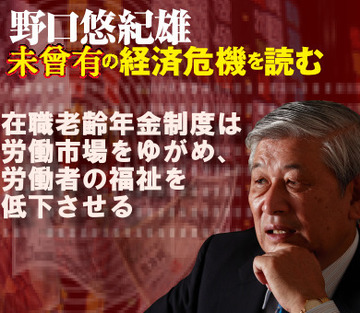前回、人口構造の変化が年金財政に影響を与えることを述べた。
すなわち、(1)平均余命の伸長による「絶対的高齢化」は、年金受給者数を増加させる。(2)少子化による「相対的高齢化」は、受給者に対する保険料納付者の比率を低下させる。積立方式であれば(1)の要因により、賦課方式であれば(1)、(2)の要因により、年金財政は逼迫し、給付の引き下げや保険料の引き上げが必要になる。
ただし、ここでつぎの点に注意する必要がある。すなわち、問題となるのは、人口構造の変化そのものではなく、「年金制度設計時の見通しとその後の実際の推移の食い違い」である。なぜなら、年金は長期にわたって継続する制度であるから、制度設計時において将来人口の見通しはなされているはずであり、その見通しに立って保険料や給付水準が決定されているはずだからである。
しばしば、年金の説明で「高齢化が生じたから年金財政が逼迫した」とあるが、これは不正確な説明だ。高齢化の進展そのものは、仮に現実が予測どおりに推移していれば、年金財政を悪化させる要因にはならないのである。「予測を超えた高齢化」だけが、年金財政を圧迫するのだ。
人口高齢化の予測と現実の乖離は
どの程度だったか?
日本の人口構造が高齢化することは、かなり以前から予測されていた。そして、実際に、著しい高齢化が生じた。
では、予測と現実値の乖離は、どうだったか? それを具体的な数字で示そう。
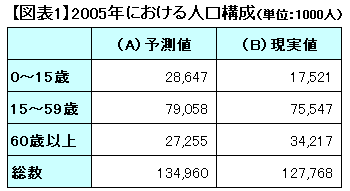
【図表1】のA欄に示すのは、1969(昭和44)年において当時の厚生省人口問題研究所が行なった将来人口推計の2005(昭和80)年の値である(*1)。それに対してB欄に示すのは、05年の実際の値である。
高齢者人口(60歳以上人口)は、69年推計では約2725.5万人と予測されていたが、現実には3421.7万人になった。すなわち、「絶対的高齢化」が予測を超えて進行した。高齢者の絶対数は、予測値の1.26倍になったのだ。
また、高齢者人口1人当たりの生産年齢人口(15~59歳人口)は、66年推計では2.91人に低下すると予測されていたが、現実にはもっと低下して2.21人となった。つまり、「相対的高齢化」も、予測されていたより進展した。
*1 中位推計。なお、人口問題研究所は、現在では、国立社会保障・人口問題研究所。ここで示した数字は、『社会保障統計年報(昭和49年版)』の第276表による。