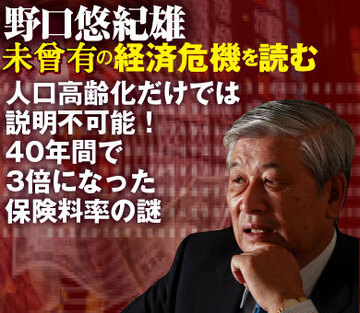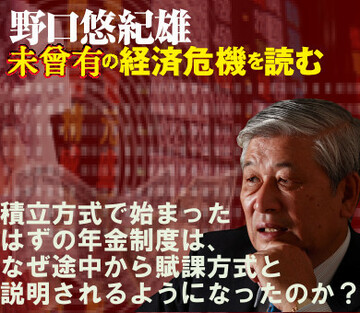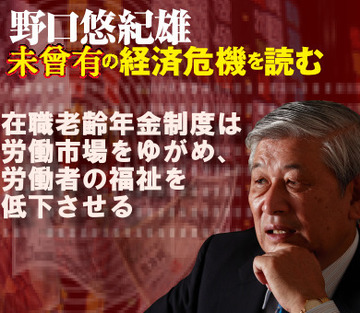ある時点まで、日本の公的年金は積立方式を意図して運営されていた。これまで第86回、第87回で述べてきたように、年金給付式に保険料納付期間が入っていること、1970年以前は現実の年金給付総額はきわめて少額であったことから、このことは明らかである。
また、1980年以前は、財政再計算において「平準保険料」という指標が計算され、これが保険料決定の基本とされていたことからもそれは裏付けられる。
「平準保険料」とは、その保険料を維持すれば、年金制度が未来永劫にわたって運営できるような保険料である。具体的には、つぎのように算出される。まず、人口推計と将来の年金給付水準想定に基づいて、将来にわたる年金給付の割引現在値を求める(「割引現在値」とは、将来の値を割引率を用いて現時点の値に引き直し、これをすべての時点について足し合わせたものである)。一方、人口推計と将来の保険料率想定に基づき、将来にわたる保険料収入の割引現在値を求める。さらに、将来にわたって想定される国庫負担の割引現在値を求める。そして、
年金給付の割引現在値=保険料収入の割引現在値+国庫負担の割引現在値
となるように、将来の年金給付水準と保険料率(平準保険料率)を定める。
仮に将来の人口が人口推計どおりに推移するならば、ここで定めた保険料と積立金の運用収入によって、将来の年金給付をまかなえるはずである。
成長率と利子率に関する想定の齟齬
平準保険料率の計算にあたっては、人口推計とともに、つぎの2つのパラメータの想定が本質的に重要な役割を果たす。第一は、経済成長率(あるいは、保険料計算の基礎となる賃金上昇率)であり、いま一つは割引率(利子率)である(*1)。
1980年以前の計算では、まず経済成長率(賃金上昇率)がゼロと置かれた。そして、割引率としてその当時の長期利子率に近い5%ないし6%という値が用いられた。
しかし、これは、信じられないような誤りである。後で説明するように、ゼロ成長経済においては、利子率はゼロ付近のきわめて低い値になるはずだ。したがって、経済成長をゼロと置くのであれば、割引率としては非常に低い値を用いる必要があった。他方、割引率として現実の長期利子率に近い値を用いるのであれば、成長率としても現実の経済成長率(あるいは現実の賃金上昇率)に近い値を用いる必要があったのである。
ところが、平準保険料計算においては、そのような経済的配慮は一切なされず、上記のように奇妙きわまりない想定が採用された。
賃金上昇率がゼロの世界で6%近い高い割引率を想定することは、将来の事態を過大に割り引いてしまうことを意味するのである。その結果、将来において進展する人口高齢化をほとんど無視する結果となった。