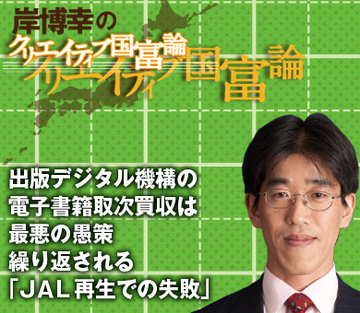紀伊國屋書店は9月10日刊行の村上春樹さんの自伝的エッセイ「職業としての小説家」の初版の9割を買い切った。売れ残りリスクを引き受けてでも、書店の利益率を高めるこの取り組みは、返品できることを前提とした委託販売が主流の出版業界に一石を投じるものだ。同書店の経営戦略と出版業界の課題について、『週刊ダイヤモンド』10月17日号の特集『「読書を」を極める!』に掲載した高井昌史・紀伊國屋書店社長のインタビュー拡大版をお届けする。
──本が売れない状況が続いています。国内外で大規模な店舗を展開する紀伊國屋書店の経営戦略は。
 たかい・まさし/1947年東京生まれ。70年に成蹊大学法学部卒業、71年紀伊國屋書店入社。各地の営業所長などを経て、93年取締役、2008年社長就任。出版文化産業振興財団常務理事なども務める。
たかい・まさし/1947年東京生まれ。70年に成蹊大学法学部卒業、71年紀伊國屋書店入社。各地の営業所長などを経て、93年取締役、2008年社長就任。出版文化産業振興財団常務理事なども務める。Photo by Masato Kato
1964年にできた当社の新宿本店には、紀伊國屋ホールや画廊があります。初期の頃には喫茶店もあって、今でいうブック・アンド・カフェがすでに実現していました。来年は、「紀伊國屋演劇賞」が50周年になります。こうした取り組みを通じて、文化の中心的な役割を果たしてきました。歴代の経営者が目指してきた、文化の殿堂とか知の殿堂というものに近づいてきたのかなと考えています。
69年には米国サンフランシスコに店を出しました。小売業が海外に出るのが珍しい時代に、日本の本を海外で売る一方、洋書を日本で勧めました。現在、ニューヨーク、シンガポール、ドバイ、シドニーなど海外に27店舗を出しており、皆、地域で一番大きな書店となっています。
海外売上は本だけで210億円です。文具を合わせると250億円で、近いうちに300億円を海外で売りたいと考えています。100人の社員が海外駐在などで国内外を行ったり来たりしています。
20年前、日本の出版業界の販売額は2兆6500億円ありました。その好調な時代に上げた利益を海外に投資したのです。当初は赤字で、日本国内の事業でなんとか(海外の赤字を補てんして)頑張っていました。国内の事業環境が厳しくなった現在は、配当という形でリターンを得ているということです。
売上高が約500億円に上る外商の存在も大きいです。大学などに洋書や雑誌を売っています。店舗と外商の売り上げ比は55対45ほどです。外からは見えにくいですが、外商が売上の半分を占めているわけです。
国内店舗の売上高は560億円です。売上を落とさないように頑張っていますが、ここだけで見ると他の書店と同様に経営は厳しい。当社は、国内店舗以外のところ(海外や外商)に支えられているというのが特徴です。
──米国ではネット通販大手のアマゾンの影響で大規模店が閉店に追い込まれる一方、個性的な小規模店が元気です。書店の生き残り戦略は大規模店と中小で異なってきているのでしょうか。
米国の書店大手のボーダーズが倒産しました。バーンズ・アンド・ノーブルも経営が厳しく、ずいぶん店を閉めています。こうしたチェーン店の苦境は、アマゾンに対抗できなくなってきたからでしょう。
書店は装置産業です。開店に必要な本棚や照明などを用意するのにお金がかかります。こうした中で(低コストで販売できる)ネット通販が増えれば、書店は苦しくなります。まさにアマゾンとの闘いです。
一方、特色のある独立系書店は各地で元気を取り戻しています。金太郎飴のような書店ではなく、特色を出すことが集客に結び付くわけです。
紀伊國屋書店も(大規模店ではありますが)、特徴を出そうと努力しています。日本語、英語、中国語だけでなく、フランス語、ドイツ語の書籍までそろえたり、日本の文化を生かしたイベントを開いたりして、お客さんを集めています。漫画家のサイン会やコスプレといったイベントは、米国だけでなく、中東でも人気です。著者もこうしたイベントに協力的になっています。
── 一方で、国内の出版業界は行き詰っています。出版界が見直すべき構造的な問題とは何ですか。
従来の流通の仕組みは通用しなくなっています。
再販売価格維持制度(再販制)も金属疲労を起こしている。あまりに硬直的で、それに縛られてしまう状態です。ネット通販や新古書店など、昔はなかったものが出てきています。公共図書館の貸出回数が7億2000~3000回になって、本の販売冊数を上回っている状況もあります。コンビニも“街の本屋さん”のように本を置くようになりました。
こうした逆風の中で、硬直的なことを続けていていいのでしょうか――。
本を作る「出版社」、物流を担う「取次」、売る「書店」というのが三位一体となって同じ傘の中で平和に過ごせればいいですが、それが事業環境の変化で難しくなっているのです。大手取次が書店に資本や人を出して系列化したり、(取次の)大阪屋が経営危機になると出版社が支援したり、出版社がブックオフに出資したりしている。(住み分けはすでに崩れていて)プレーヤーが、自分の考えを貫き、新しい仕組みを作っていかなければ生きていけなくなっているということです。