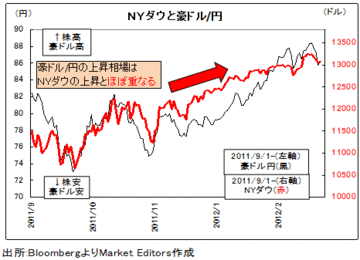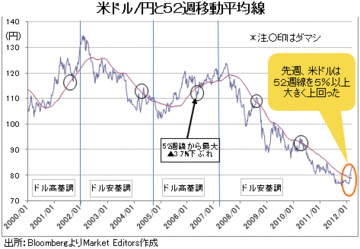4月から続いてきたユーロ安・株安に変化が見え始めました。株安はそのままですが、ユーロは反発し始めています。
これを受けて、金融混乱の主役が欧州から米国へシフトしているとの見方もあるようですが、私はそうではなくて、金融混乱自体が転換に向かっているのではないかと思っています。
ユーロは7~8月に120円、1.3ドルへと向かう!?
4月頃から同じように動いてきたユーロとNYダウですが、6月末から、別の方向へと動き始めました。
6月末にカナダで開かれたG20(20カ国・地域首脳会合)サミットで2013年までに財政赤字を半減させることで合意がなされ、景気先行き不安が一段と強くなったことが大きな要因のようです。
これで株価は一段安となり、その一方でユーロは急反発に向かったのです。
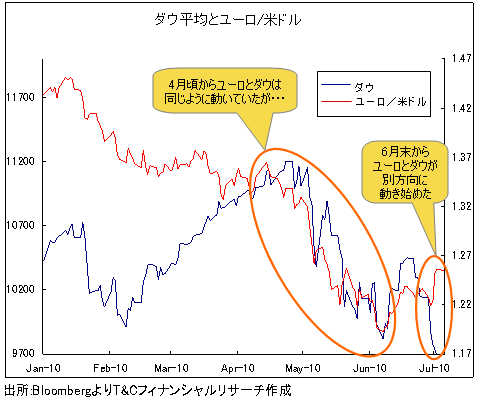
そもそも、私はユーロ安が「スピード違反」であって、反転に向かうと考えていたので、これは当然の展開だと思っています(「相場の『間違い』は必ず修正される!『何でもユーロ安』はいつまでも続かない!」を参照)。
その上で、90日移動平均線からのカイ離率がマイナス10%前後まで拡大し、経験的に「短期下がり過ぎ」を示す動きになっていた相場は、「振り子の法則」が働いて、最低でも90日移動平均線の回復へと向かうと考えるのが普通です。
今回、ユーロ/円とユーロ/米ドルで、90日移動平均線からのカイ離率がマイナス10%前後まで拡大したのは、5月末~6月初めのことでした。
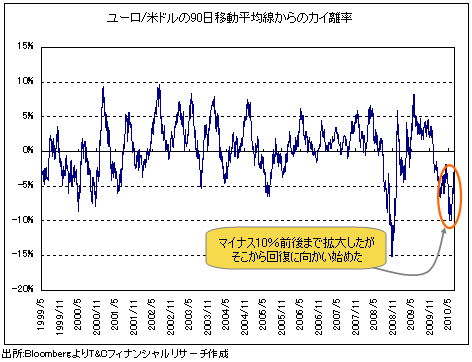
経験的には、そこから90日移動平均線の回復までに1~2カ月程度を要するため、7月から8月にかけて、ユーロ/円は120円、ユーロ/米ドルは1.3ドルへ向かうといった見通しになります。
マーケットは「1937年の再来」におびえているが…
それはそうとして、株安はまだ続くのでしょうか?
金融市場に漂っている不安感を一言で表せば、「1937年の再来」といった極めて深刻なもののようですが、果たしてそのような悲観論は正しいのでしょうか?
まず、「1937年」について説明しましょう。1930年代に大恐慌と呼ばれる世界経済の大混乱が起こり、いったん回復したものの、1937年は世界経済が「二番底」へと転落する転換点の年となりました。
大恐慌は、1929年10月、「暗黒の木曜日」と呼ばれた米国株の暴落から始まりました。その後、FDR、フランクリン・ルーズベルト政権が誕生し、ニューディール政策によってこの株価暴落は、1932年にようやく底入れとなりました。
その後、世界経済は回復へと向かったのですが、インフレ懸念が強くなったことで、1937年から景気引き締め策へ、つまり「出口政策」へと大きく舵を切りました。
これを受けて、景気は再び失速し、世界経済は「二番底」に向かうところとなったのです。
さて、2008年秋から2009年春にかけて展開された「100年に一度の危機」でしたが、その後は世界経済が回復に向かい始め、今年に入ると、その「出口政策」が動き始めました。
そして、前述したように、6月末のG20サミットで「2013年までに財政赤字を半減させる」ことで合意がなされたのです。
こういった一連の動きを横目に見ながら株式市場は続落しました。市場関係者の頭の中には、「出口政策」への傾斜が「二番底」への転換点となった1937年の再来がよぎっていることでしょう。
本当にそんな深刻なことなのでしょうか?
過去3回のダウ急落局面と現在で、何が異なるのか?
米国の有力投資週刊誌「バロンズ」の最新号には、「What does the market know that we don’t? 」という記事がありました。直訳すると、「マーケットは我々が知らない何を知っているのか?」といった感じになるでしょう。
これまで述べてきたように、G20サミットなどを横目にして株安が広がっていることからすると、「1937年の再来」があるかもしれないと言われると、何となくそうかもしれないと思ってしまいがちです。
しかし、一歩引いてみると、最近の株安が必ずしも当然のことではないといった考え方もできそうなのです。