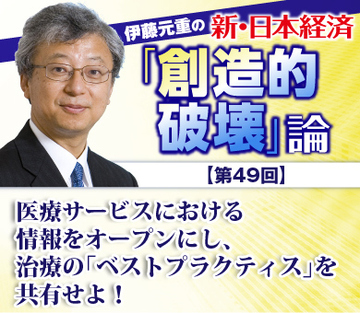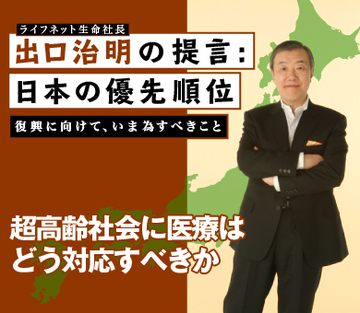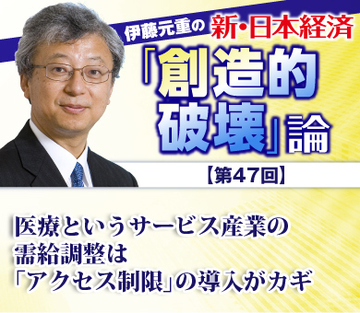今年4月に診療報酬が改定され、ついで6月には「地域医療・介護総合確保推進法」が成立した。これによって、我が国の「医療」「介護」大転換に向けて、第一歩が踏み出された。
少子高齢化が急速に進む中で、日本の社会保障が大きな改革を迫られていることは、誰の目にも明らかだ。その社会保障を語る際に最もふさわしい報告書が昨年8月に提出された。目指すべき社会保障の筋道を描いた「社会保障制度改革国民会議」の報告書である。同会議は2012年11月、自民、民主、公明3党が税と社会保障の一体改革について合意し野田内閣が設けた。年金、医療、介護、少子化の4分野を対象に、病院や施設の利害関係者でない15人の大学教授など有識者で構成。目先の思惑を排してより客観的にあるべき将来像を提案した。
2008年の福田・麻生政権時の「社会保障国民会議 最終報告」で、社会保障の機能強化とサービスの効率化が謳われ、団塊世代が75歳を迎える2025年を目標としたが、その改革の方向性を引き継いでいる。
今回の報告書は社会保障論議の集大成と言うべきもので、随時具体化されていく。
例えば、「患者の自己負担について『年齢別』から『負担能力別』への転換」が報告書で提言されたことを受けて、冒頭の「地域医療・介護総合確保推進法」では来年8月から年金年収が280万円の高齢者には、介護保険の利用料を1割から2割に増やすことを盛り込んだ。
報告書の中身の多くは、4分野のうちで改革が遅れている医療システムに重点を置いた。今回は、報告書を読み解きながら医療改革の方向性を追ってみる。
「治す」医療から「支える」医療へ
“平均寿命80歳”で一変した患者像
報告書では、医療・介護分野の改革について述べた部分の冒頭で、「欧州各国では、1970~80年代に病院病床数の削減に向かい、医療と介護がQOL(生活の質)の維持改善という同じ目標を掲げた医療福祉システムの構築に進んでいった」と世界の流れを見渡したうえで「日本はそうした姿に変わっていない」と糾弾し、改革の必要性を訴える。
変えるべきことは何か。
一言で言えば、医療の役割を「治す」から「支える」に転換させることだという。「治す」のは病院であったが、「支える」のは地域の診療所である。「病院完結型」から「地域完結型」への移行でもある。
なぜこのような転換が必要なのか。答えは簡単、明白である。