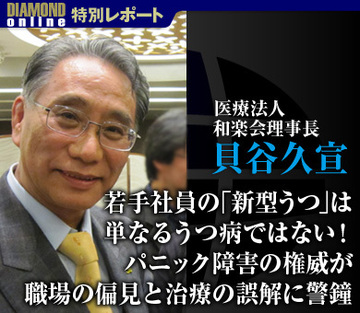大うつ病やそううつ病などの気分障害は、客観的診断法が未だ確立されていない分野。
唯一、MRIで脳の血流量の変化を調べ、うつ病か否かを診断する「光トポグラフィー検査」は、今年4月から健康保険が適用されている。実施施設に厳密な条件や報告義務が課せられるため、普及に時間はかかるだろうが、低額で客観的な検査が受けられるようになったことは患者・家族にとって朗報だろう。自己負担分は数千円程度(3割負担)である。
となると、次は「血液検査」が欲しいのは全世界共通で、各国の研究者がしのぎを削っている。日本では血液中EAP(エタノールアミンリン酸)濃度やBDNF(脳由来神経栄養因子)をターゲットとした研究が進んでいる。
このうち、BDNFは脳内で神経新生や発達に関係するタンパク。うつ病患者では血中濃度が低下しているが、健康な人でも高ストレスに曝されると低下するため、診断精度はいまひとつだった。しかし直近の成果では、BDNF遺伝子内で生じる「メチル化」という現象の違いを比較して、健康者、うつ病、統合失調症をほぼ100%の精度で検出できる段階まで来ている。実用化が待たれる。
また先日は、米ノースウェスタン大学から、特定のRNAの血中濃度から大うつ病の診断ができる可能性が報告された。RNAは遺伝子情報の「伝達・翻訳」を担う分子。成人うつ病患者と健康な成人の血中RNA濃度を比較したところ、三つのRNAで明らかな違いがあった。また、特定のRNAを有するうつ病患者では、認知行動療法が効きにくいなど確定診断以外に、適切な治療法を選択するためのデータが得られる可能性が示唆されている。
よくいわれるが「うつ状態」と「うつ病」は違う代物だ。うつ状態には「適応障害」が隠れていることが多く、うつ病とは治療法が異なる。認知症の初期というケースだってあり得るのだ。誤った診断名で誤った治療を続けるほど悲惨なことはない。患者や家族の一生を左右するのだから。客観的診断法の早期確立は社会的課題でもある。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)