バブル崩壊以降、低迷していた美術品ブームが復活の兆しを見せている。オークション市場が整備され、愛好家が流れ込んでいるのだ。だがこのブーム、まだ「バブル」と呼ぶにはほど遠い。美術品を買い漁っているのはもっぱら海外の富裕層ばかりだ。直近では、米国で出品された運慶の「大日如来像」をすんでのところで三越が落札するなど、文化財の国外流出危機まで騒がれている。
「10万、20万とちまちま上げるな。100万円でどうだ!」――。熱気に包まれた会場から、お客の威勢のよい声が飛ぶ。
ここはお台場にある毎日オークションの美術品競売会場。オークションは絵画、装飾品、陶芸、貴金属などのジャンルがあり、出品点数は一回につき1200点にも上る。安いものは10万円のアンティークウオッチから、高いものは数百万~数千万円もする北大路魯山人の壺やエミール・ガレのガラス工芸品まで、多種多様だ。
会場を埋め尽くす参加者は200~300人。目当ての逸品を競り落とそうとパドル(入札フダ)を振り上げるお客に、オークショニア(進行役)も大わらわだ。
「いまや1回の取扱高は2億~3億円。出品者・購入者双方から落札額の10~15%の手数料が入るため、ひと晩で数千万円は売り上げが立つ」と、岡澤利栄取締役はホクホク顔である。
最近、都内の競売会場はいずれも同様の盛況ぶりだという。「1980年代のバブル期以来20年ぶり」という美術品ブームの兆しが見え始めているのだ。
バブル期といえば、大企業や富裕層による美術品投機が華やかなりし時代。安田火災海上保険(現・損保ジャパン)がゴッホの「ひまわり」を53億円で購入したエピソードは、あまりにも有名だ。
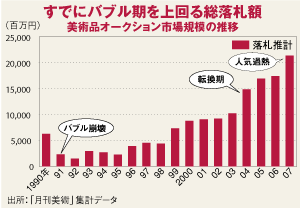 しかしそんな投機ブームも、バブル崩壊により一気に沈静化してしまった。美術品オークションの市場規模は、90年代半ばにバブル末期の3分の1まで低迷した。
しかしそんな投機ブームも、バブル崩壊により一気に沈静化してしまった。美術品オークションの市場規模は、90年代半ばにバブル末期の3分の1まで低迷した。
だが2004年以降、ブームは目に見えて再燃し始めた。美術品の平均落札額は40万~50万円台とバブル末期の10分の1程度だが、「取引数が増えたこと、ピカソやシャガールなど1億円を超える高額作品の落札数が増えたことにより、市場規模はすでにバブル期を上回っている」(倉田陽一郎・シンワアートオークション社長)。
2007年の市場規模は対前年比23%も急拡大し、200億円を超えた(上のグラフ参照)。







