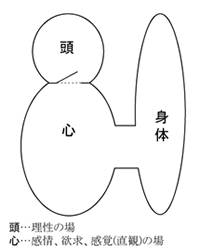前連載(「うつ」にまつわる24の誤解)の第16回でも取り上げましたが、現代の「うつ」において、このような悩みが浮上してくるケースが非常に多くなってきています。
今の社会では、幼い頃から「やらなければならないこと」を休みなく課せられてくることが多く、なかなか、ゆっくりと「やりたいこと」に思いを巡らす余裕が与えられていません。
そのうえ、外から「与えられる」膨大な知識を次々に記憶し、「与えられた」方法で要領よく情報処理することを求められるために、人々の多くは、「自分は何をしたいのか?」「これは本当に自分がやりたいことなのか?」といった問いを持つこと自体に、不慣れになってしまっているようです。
しかしながら、このように「主体」を見失ってしまったという悩みは、現代人のみに見られる新しいテーマというわけではありません。これは、近代的自我の目覚め、つまり「主体」として生きたいと真摯に願う人間であれば、昔から避けては通れないテーマだったのです。
今回は、この苦悩に直面した代表的な人物として夏目漱石を参考にしながら、現代の私たちが、失われた「主体」をいかに回復できるかという問題について考えてみたいと思います。
漱石の感じていた「空虚さ」
私はこの世に生まれた以上何かしなければならん、といって何をして好いか少しも見当がつかない。私はちょうど霧の中に閉じ込められた孤独の人間のように立ち竦んでしまったのです。(夏目漱石『私の個人主義』中公クラシックス版より)
夏目漱石は、若い頃から内面に「自分が何をしたいのかわからない」という「空虚さ」を抱えていました。
大学で英文学を専攻して学んでみても、漱石には、文学がわかったという手応えが得られない。卒業して成り行きで教師になってはみたものの、その仕事にもまったく興味が持てない。そんな悶々とした状態で過ごしていたところに、突然文部省から英国留学を命ぜられたのです。漱石33歳、明治33年のことでした。
慣れぬ異国の地で、彼の「空虚さ」は解消するどころか日々増幅するばかりで、いくら本を読んでみても、ロンドン市内をうろついてみても、一向に晴れる気配はありませんでした。そうして漱石は、ついに強度の神経衰弱、今日で言う「うつ」状態に陥ってしまったのです。
漱石が神経衰弱にいたったこのような経緯は、現代の「うつ」においてもとてもポピュラーなパターンだと言えます。
進学や就職に際して、実のところ特にやりたいことがあるわけでもないままに、何となく流されて選択して進んでしまう。そして、与えられた勉強や仕事はそれなりにこなすけれども、特別やりがいを感じるわけでもない。そんな日々を重ねて行くうちに、ある時ふと「自分はいったい何をしているんだ?」「これが自分の望んだ生き方なのか?」「なぜ働かなければ(勉強しなければ)ならないんだろう?」といった疑問がわき上がってくるようになり、それがじわじわ強まって、ある日とうとう動けなくなってしまうというパターンです。