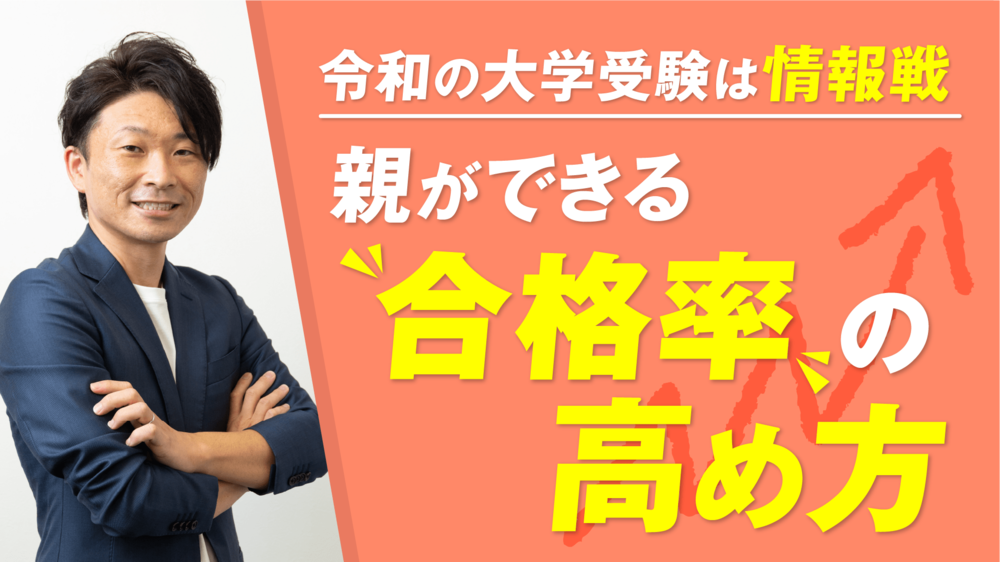短期記憶と長期記憶について
人間の脳は海馬により短期記憶が行われ、大事なことや繰り返されるものは大脳新皮質で長期記憶されます。また、重要でないことは海馬で止まって忘れていくようになっています。勉強では学習した知識を脳にいかに大事なことと刷り込ませるかが重要です。もちろんすべての知識が一回で長期記憶にならないため、長期記憶にならなかった知識を拾い上げて再度長期記憶にしていくことができれば、勉強は効率化されていきます。
短期記憶の環境を整える
短期記憶の一つに人間には作業中の記憶を一定時間保持しておく「ワーキングメモリー」というものがあります。短期的な記憶で、明日明後日と覚えているものではありません。これは慣れれば一定のキャパシティは広げられますが、限界があります。
つまり勉強を効率的にするためには短期的な記憶量を増やすよりも、ワーキングメモリの処理数を減らす必要があります。複数のことをするとワーキングメモリを使いすぎてしまうため、勉強する際には多くのことを同時にやらない方が良いです。
ワーキングメモリに負荷をかけることは、それを鍛えることに繋がるので、悪いことではないですが、疲れているときはワーキングメモリに負荷をかけず1つのことに集中した方が良いです。学校の授業を聞きながら別の内容をすることは効率が悪いですし脳が疲れます。そうすると集中力の継続時間が短くなり、前頭前野が疲労して意欲が落ちてきます。
内職(授業中にほかの勉強をすること)は必要な場合もあると思いますが、このような仕組みを理解した上で実施するか検討していくと良いでしょう。さらに、こうした脳機能から考えると、スマートフォン片手に友達からの連絡のやり取りをしながらや関係ない動画を見ながらの勉強は効率が悪くなるということを理解しておきましょう。
・本番まで時間があり脳を鍛えるためにはマルチタスクで負荷をかけていく
・疲れているときやこれを覚えたいというときはシンプルタスクの方が集中できる
記憶を定着させる長期記憶の仕組み
記憶に大切なことは「理解」「感情」「接触回数」の3点です。
- 理解
- 感情
- 接触回数
脳は大事なものを海馬から大脳新皮質へ移行し、長期記憶を形成していきます。大事なものとは繰り返し出てくるものや感情を伴うもの(恐怖や喜び)です。感情は強烈な刺激のため、脳に強く長く保持されます。先生がおかしなことを言っていたとか、できなくて悔しかったとか、理解できて感動したなどの感情が動く状況で知識が入ったときは長期記憶に繋がります。
また、何度も何度も同じものを見ることで脳は「これは覚えておかないといけないものだ」と認識して長期記憶に繋がります。
お勧めの勉強法
・マーク法(問題集を解くとき)
・カード暗記法(理解本を暗記するとき)
私が塾での生徒指導で特にお勧めしているのが、マーク法とカード暗記法です。使い古された勉強法ですが、接触回数を増やすために、問題集を間違えた問題だけにマークを付けて周回するというのを徹底することは非常に効果的です。
問題集はこのマーク法で効率化が進みますが、社会理科系の知識のインプットについておすすめの勉強法は、1ブロックや1単元ごとに理解したら閉じて自分で思い出せるかセルフテストをすることです。自分で勉強していると暗記量に比べテストの機会がどうしても少なくなってしまうため、このように1ページや1つの区切りごとに思い出す作業をすると良いでしょう。
さらに覚えたことをノートでなく、ルーズリースを4分の1サイズに切ったカードにメモしていくのもおすすめです。ノートだときれいに書いてしまって時間がかかってしまうのと、再現性がなくなってしまうので、メモ程度の小さい内容にして、あとで捨てるくらいの気持ちでまとめたり、書き出したりします。
フラッシュカードとの違いは裏面に答えを書かず、一瞬それをみて、同様の内容が再現できるかをテストしていきます。それをフラッシュカードのように高速で周回していき徐々に減らしていくとか、どうしても暗記できないものはカードをよく目にする壁に貼るなどで、知識との接触回数を増やしていくと楽しく継続できます。
長期記憶につなげるために暗記できなかったものは何度も接触していく必要があるため、このように楽しく継続できて、手数を減らして繰り返しやすい環境を整えることを勧めています。
思い出す作業が実は重要
初めて英単語を覚えるとき、すべて大事だと思っているのに翌日には忘れてしまっている単語が複数あるといったことは誰しも経験があると思います。しかし、これは完全に忘れてしまっているわけではなく、大体のことは1回覚えたら断片として頭に入っています。
大事なのは思い出せるかどうかです。今はAが出てきたけどBは出てこない、しかし、翌日になったら逆が出てくるということもあり、たまたまどちらが想起しやすかったかの違いで、これは時間帯やその場所、そこにあった情報等で変わってきます。
覚える、蓄えるという機能と、それを想起する(思い出す)という両方ができて初めて使えるようになるので、勉強をする際にはインプットとアウトプットの両方を意識することが重要です。例えば、Appleという文字を書いて覚えるときに、リンゴの絵があったり、赤いものを見たりしながら勉強をした方が、文字とイメージが結びつき、覚えやすくなります。
テストは思い出す作業に最適
記憶は、覚えることと思い出すことのプロセスすべてをいいます。単に単語を100個覚えるとしても、そのプロセスでは思い出す作業をしていなければ、テストの時にはなかなか答えを思い出すことができません。思い出すことを何度も行っていると、脳で思い出すコツができてきます。テストは思い出す作業を簡単に練習できる機会としてとても良いものになります。
テストというのはイベントであり経験です。いかにパターンに慣れるかが重要なのです。テストを100回受けたことがある子と2回しか受けたことのない子では、同じ知識量を持っていても、経験があり慣れている子の方が結果が良いことは想像できると思います。これは自転車に乗れるようになるのと一緒でパターン化できるようになっているからです。
英単語でいえば、テストを何回も受けているとLOOKとSEEのニュアンスの違いがわかってくるようになるのと一緒です。授業でどちらも意味は「見る」と最初に教わるより、何度もテストで長文を読んだ方が理解できるのです。ネイティブの方は幼児の頃から理屈ではなく、何度も使用する場面を経験して、LOOKとSEEの使い分けをしているのだと思います。
さらに感情を伴う記憶は覚えやすいと言われています。何かを思い出せないときに、わからないと思い答えを見ると「これだったか!」のように情動が乗るため、感情を伴い忘れにくくなります。記憶はエピソードと結びつけることが大切なのです。
記憶を応用できるようにするために
記憶したものを入試でできるようにするためにはテストで思い出す作業も必要だとお伝えしました。入試では記憶したものがそのまま出題されるだけでなく、応用問題も出題されます。この応用問題をできるようにするために2つの大切な要素があります。それは「物事を立体的に記憶すること」と、「脳を休めること」です。
立体的な記憶や理解
例えば、小さい子どもにバナナというものを覚えさせようと「これはバナナ」といってもすぐに忘れてしまいます。しかし、バナナというものの味や香り、触感や熟すと色が変わっていくなど、さまざまな情報を色んな方向から立体的に記憶させると、応用のできるものとして記憶されます。
受験勉強でいえば、テストのために一夜漬けして問題を覚えたとき、同様の問題が出たら答えられるかもしれませんが、応用問題が出されると答えられないことがあると思います。しかし、何回も繰り返して思い出したり、その問題を多方向から捉えたりすると、一方向から見た記憶だけでなく、多方向から見た構造として記憶が立体構築され忘れ難くなるのです。
歴史でいえば、因果関係や背景を捉えたり、視覚的に記憶したりすることが重要です。平家のことだけを覚えようとしても覚え難いですが、源氏もいたということを認識することによって、何年に平家がどうなったかということを忘れ難くなり、色んな方向から見た構造として記憶が立体構築されるのです。つまり、ストーリーや物語として理解すると忘れなくなるということです。
また、五感をフルに使った経験として覚えると深い記憶になります。ただ、五感をフルにつかうと時間が必要になりますので、ここ一番!といった大切な記憶や、苦手でどうしてもとっつきにくい分野は、楽しみながら経験をすると、覚えやすいです。
脳を休めることも大切
次に、脳を休めることも記憶や深い理解をするための重要な要素です。人間はぼーっとしている時間や寝ているときに記憶が分類され整理されるようになっています。ぼーっとしているとは浅い睡眠に近いリラックスした状態をさします。
ぼーっとしていると何もしていないと思われ「早く勉強しなさい」と注意されることも多いでしょう。しかし、ぼーっと外を眺めているときや電車の中で車窓の景色を見ているときには、勉強した内容が意識にはのぼっていませんが、脳の中では大事なものとそうでないもの、あるいは一見関係ないものと結びつけたり整理整頓をしたりと記憶の内容や概念を整えているのです。だからこそ、ぼーっとしている時間を邪魔しないことがとても大切なのです。
しかし、これには注意しなければならないことがあります。それは、休憩時間にスマートフォンを見ないことです。
例えば動画等を見ると、文字や音声といった知識や情報は入ってきますが、ぼーっとすることはできておらず、自分がやるべきことが頭で整理されません。だからこそ、休憩時間等には窓から景色を見たり、歩いたりするなど、脳にあまり負荷をかけない行為にとどめて休憩することがとても大切なのです。
長期記憶できなかった知識を長期記憶にするために
勉強をやっているときの知識はだいたい同じくらいの重要度であって、ここまでの方法を知っていても、もちろんすべてを1回で長期記憶にすることはできません。それではどうしても長期記憶できなかったものはどのようにして定着させていったら良いのでしょうか。
記憶できなかったものはもう一度、衝撃や感情を与え、接触回数を増やし、五感で覚えたり経験したり、多面的に理解し、テストをして思い出す作業をするという同じトライをします。その中で自分の中で落としてしまっている原因を探します。
例えば、歴史に興味がなくて覚えられていない場合は、一問一答ではなく、資料や映像をみたり背景を知ったりすることで興味を持つことができます。このように興味がないものに興味をもたせるのも一つのコツです。または今まで強固に覚えているものに新しいものを結びつけることも効果的です。
それでも暗記できないものは無理やり自分の今までの経験やエピソードに刷り込んで結びつけることも効果的です。自分なりの語呂で暗記をしたり、覚え方を作ったりするのが良いでしょう。今ではインターネットで検索すると様々な暗記方法や解説があるので、その中で印象が強いもので暗記するのも手だと思います。
まとめ
受験までの勉強は量が多く、多くの時間を使います。そのため、このように勉強を効率化する方法をなるべく早めに学び、それを実践し試行錯誤することで、勉強の効果を高めることができます。このような勉強法は実践するのが早ければ早いほど、多くの勉強時間に影響を与えられますし、効率も上がっていきます。
世の中に勉強法は多く紹介されていますが、その中でも継続できる使えるものでないと結局続きません。なるべくシンプルで手数がかからず、やっていて楽しくなるような勉強法をみつけて続けていきましょう。
技術協力:片岡洋祐氏(脳科学者)