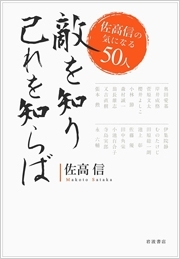元日本経済新聞社の証券部エース記者で編集委員も務めた永野健二氏が著したノンフィクション『バブル・日本迷走の原点』(新潮社)が話題を呼んでいる。もはや30年前になろうとする1980年代から90年代前半のバブル経済の実相を、その当時最前線で取材していた永野氏が生々しく伝えている。しかし、経済小説、ビジネスマン小説の巨匠として知られ、バブル時代をテーマにした作品も数多く手がける作家の高杉良氏は、この『バブル』が描く論調に違和感を禁じ得ないという。高杉氏の緊急・特別寄稿をお届けする。
 たかすぎ・りょう/1939年生まれ。出光興産をモデルにした『虚構の城』でデビュー。綿密な取材に基づき、リアリズムを追求した重厚な作品で経済小説の新境地を開く。『小説 日本興業銀行』『青年社長』『腐食生保』ほか著書多数。
たかすぎ・りょう/1939年生まれ。出光興産をモデルにした『虚構の城』でデビュー。綿密な取材に基づき、リアリズムを追求した重厚な作品で経済小説の新境地を開く。『小説 日本興業銀行』『青年社長』『腐食生保』ほか著書多数。Photo by Yoshihisa Wada
元日本経済新聞社のエース記者・永野健二氏のベストセラー『バブル・日本迷走の原点』は、我が国が“失われた20年”に陥った原因とされる1980年代から90年代前半の“バブル経済”の深層に迫ったノンフィクション作品だ。政治家・官僚・財界のエスタブリッシュ・トライアングルやバブル紳士と言われた新興不動産会社の経営者たちを実名で記すことで、最後には日本全体を巻き込むに至ったバブルの熱狂を生々しく再現している。
日本経済新聞社(日経)というインサイダー情報が集積する組織に属し、財界総理とも言われる日経連(現在の経団連)会長を父に持つサラブレッドにして自身も証券部のエース記者として名を馳せた著者ならではの、アングラ情報を散りばめたストーリー構成は読者を唸らせるものがある。読み応え十分と言っても過言にはならないだろう。
しかし、全編を通じて違和感を拭えないことも厳然とした事実だ。官僚の中の官僚と言われた大蔵省、通貨の番人たる日銀、そして銀行界、更には金融界のエスタブリッシュメントとして君臨した日本興業銀行(興銀)が、自らの支配する旧態依然とした制度を堅持せんとしたことがバブルの最大の要因とする著者の論調は、極めて大衆受けするものだ。著者本人も認めているように、銀行の下の地位に見られていた野村證券を筆頭とする証券会社を、既存秩序の改革者として肯定的に描いていることも、身贔屓ではあるものの許容範囲といえる。
それでは何が一番の違和感かといえば、自身が“社会の木鐸”として検証機能を果たすべき大手新聞社、その中でも財界の中枢に最も近い位置にいる日経に所属していながら、その本来果たすべき役割を全く実践することなく、むしろバブルを煽る役割を担ったことに対する懺悔が皆無であることだ。