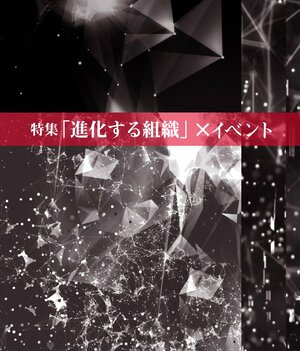これらのルーティンが崩れると、人によってはイライラして他人に当たり散らす、またある人は何事にも手がつかず1日を無駄に過ごす、またある人は自分のこだわりを自らの手で全うするまで他のことには一切手をつけられない、といった具合だ。
2022年の文部科学省の調査によると、「通常学級に在籍する小中学生のうち8.8%」に発達障害の可能性があるとしている。小中学校の一つのクラスの2人ないし3人程度に、発達障害の傾向があるということだ。
発達障害に限りなく近い
グレーゾーンも……
もっとも、小中学校の教員ら教育現場界隈では、この調査結果について「体感としてはもう少し多いかなという印象」と口を揃える。
というのは、医学的に発達障害という診断が下されることはないものの、その実は発達障害に限りなく近い……というケースもあるからだ。グレーゾーンと呼ばれるそれである。
たとえば、IQが高いがゆえに発達障害と診断を下せない、しかし本人は、対人関係が苦手、些細なことにこだわる、粘着質などなど発達障害ゆえの生きづらさを抱えているといったケースがそうだ。
そんな発達障害を持つ子を抱えたがゆえの苦悩と実態について、2人の発達障害の子を持つ家族に訊いてみた。話を聞けば聞くほど、「子どもの生きやすさは親次第」ということがわかる。
兵庫県神戸市に住むタナカさんファミリーは、夫(53)、妻(43)、娘(16)、息子(13)の4人家族だ。娘と息子は、地元では進学校として名の通った私立の中学校、高等学校に通っている。
だが、進学校へと進んだにも関わらず、娘と息子、そしてタナカさん夫婦の将来の目標は、「2人の子どもを芸術家にすること」だ。娘は美術大学へ、息子は音楽大学への進学をそれぞれ目指している。進学校での勉強と並行して、画塾やピアノレッスンへと通う日々だ。
そもそもタナカさん夫婦が2人の子どもたちを芸術家にしたいと考えたのは、ひとえに子どもたちが持つ特性ゆえだ。娘も息子もADHD(注意欠如・多動症)とASD(自閉スペクトラム症)の特性を持つ。