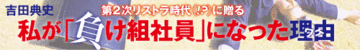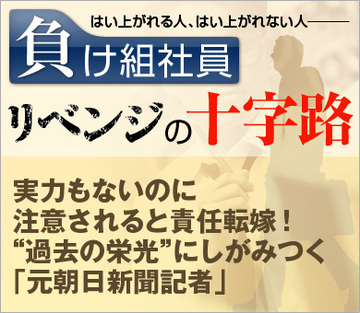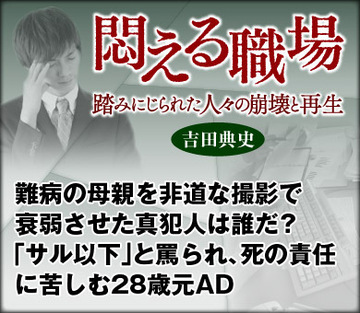本連載『悶える職場』も、今回が最終回となる。最終回は、筆者が専門学校で文章指導をしている20代半ばの会社員を取り上げたい。この男性は、大手報道機関で働いている。だが、花形の記者ではなく営業の仕事をしている。彼は記者になりたいと密かに思っているが、壁は高いようだ。
失意を抱きつつ、会社には籍を置く。そんな悶々とした日々を送るなか、彼の心を支えてくれるのが、過去の栄光である。口癖が、「自分よりも偏差値の低い連中が記者なんて……」。こうした言葉を発することで、何とか自分のプライドを守ろうとしているのだ。
この男性は、決して奇異な存在ではない。形を変えて、似たタイプの人があなたの職場にもいるはずだ。コンプレックスの裏返しで周囲をバカにする彼のような会社員が陥る「悶え」とは、いったいどんなものなのか。その心は救われることがあるのか。読者諸氏も、一緒に考えてみてほしい。
「もう辞めたい」「東京に戻りたい」
通信社の支局で働く営業マンの劣等感
「タクシーは来ているのか?……おい! 聞いているだろう?」
支局長の飯田(43歳)が、店の出入口付近に出てきた。酔っていることもあり、ぶっきらぼうな物言いになっている。
田口が(25歳)がうつむいたまま、「ええ」と小さく答える。飯田が睨みつけるような表情を見せて、料亭の座敷に戻る。
その部屋には、大手銀行の支店長や副支店長、総務課長がいた。田口の会社の取引先であり、3時間ほど前からこの3人の接待を彼らはしている。