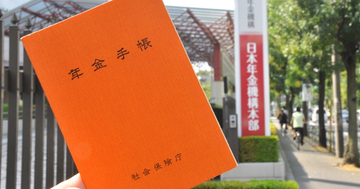『週刊ダイヤモンド』2015年7月18日号の第一特集は、「徴税強化か、魔法の番号か マイナンバーの正体」。10月から国民一人一人にマイナンバーという「背番号」が割り振られます。いったいマイナンバーとは何なのか、私たちの暮らしはどう変わるのか。そんな疑問・不安にズバリお答えします。
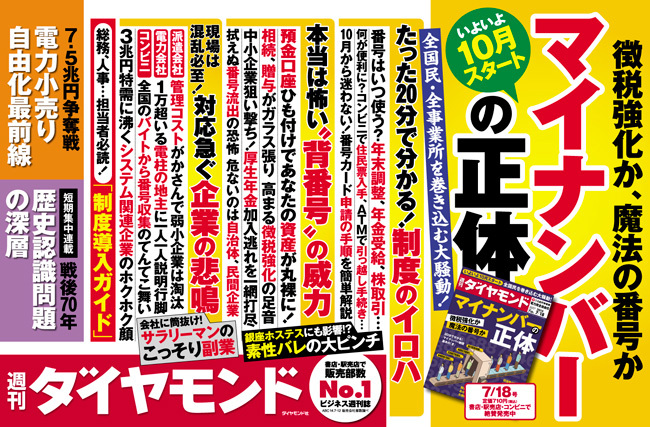
マイナンバーをめぐっては、行政手続きの簡素化や、将来的にはさまざまな民間サービスが受けられるメリットがある半面、個人資産が丸裸にされ課税が強化されることや、万一の情報流出による悪用の懸念など、デメリットも指摘されている。いったいどんな“不都合”があるのだろうか。
「小さく生んで大きく育てる」──。マイナンバー制度について語るときに、政府関係者や関係省庁、立ち上げに携わってきた人々の間で、合言葉のようになっているセリフだ。
まずは、社会保障や税金に関する最低限の行政手続きに利用するものとして、マイナンバーという制度を“生む”。そして、ゆくゆくは国民の理解を得ながら世の中に浸透させていき、その他の行政手続きや民間利用にまで範囲を広げて利便性を高め、“育てる”ことを思い描いているのだ。
ただ、その“育て方”には、よく目を凝らしておいた方がよさそうだ。多くの国民が、この10月から個人番号の通知カードが配られ始めることや、来年1月から制度が開始することをよく知らない。そんな中で、制度開始前からマイナンバーに関する改正法案を国会で議論し、早くも利用範囲の拡大を図ろうとしているからだ。
中でもその動きが気になる“育ての親”といえば、何といっても国税庁だろう。番号制度とは、国税庁にとって税金の取りっぱぐれを防ぐための最強の武器。その導入は宿願といわれてきた。
導入当初の仕組みでは、まったくもって不完全な代物にすぎない。しかし、最終的には「国税庁は番号を使って、国民の資産のフローとストック、両方の情報を全て押さえにかかるつもりだろう」と、ある税理士業界の関係者は見立てを語る。
制度の導入当初は、給料に加えて銀行の投資信託口座や証券口座、積立型・年金型保険、死亡保険などに番号がひも付くことが決まっている。100万円以上の国内入金・海外送金も同様だ。
これを第1段階とすると、ある程度のお金の流れは見えても、資産のストックは見えてこないので、国税庁が思い描く最終形には程遠い。そこで、第2段階として構想が練られているのが、銀行の預金口座とのひも付けだ。番号と預金口座のひも付けが進んでいくと、精緻にお金の流れを追い掛けることができるようになる。