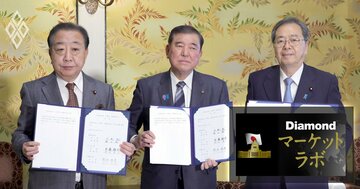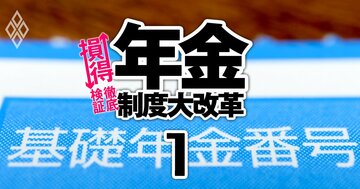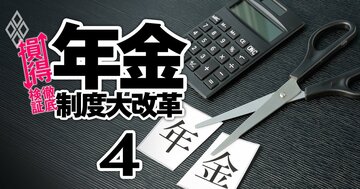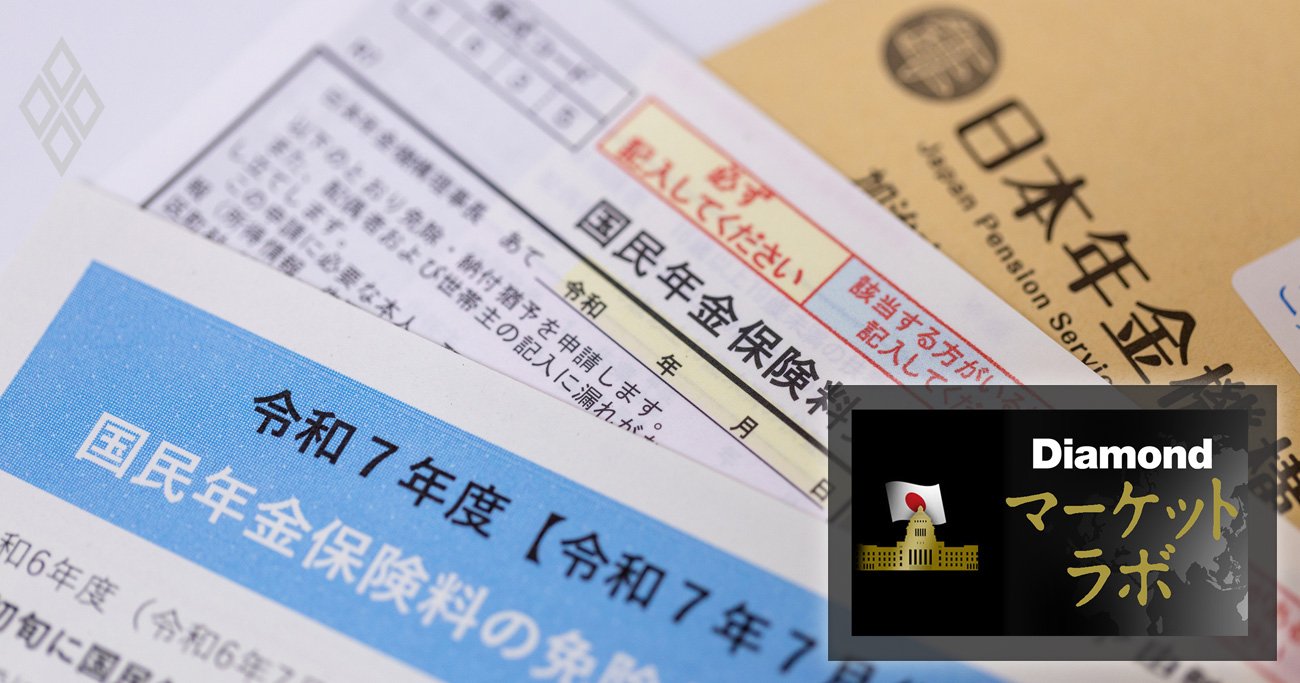 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
国民年金の財政基盤は脆弱(ぜいじゃく)である。納付率の改善が報じられるが、その内実は免除者の急増による「見かけ上の納付率」に過ぎない。基礎年金の全額国庫負担、すなわち税方式による抜本的な改革の必要性が高まっている。(昭和女子大学特命教授 八代尚宏)
納付率80%突破の裏にある
保険料免除者の増加
日本の年金制度でもっとも財政基盤が弱いのが国民年金である。自営業、学生や被用者年金の適用を受けない小規模な事業所の被用者が加入している。この国民年金保険料の徴収率が、給与から源泉徴収される厚生年金など被用者年金と比べて著しく低いことが長年の大きな課題となっている。
他方、厚生労働省は6月末に、2024年度の国民年金の保険料納付率が78.6%と12年連続で高まったと発表した。また、2年の猶予期間後に支払う者も含めた最終納付率も22年度は84.5%になったという。
この最終納付率について、厚生労働省は、日本年金機構が発足した10年度は6割台だったものが、22年度に初めて8割に達したと誇示した。これには、スマートフォン決済アプリを使って納付できる制度を導入し、利便性の向上に取り組んだことが寄与したと説明している。
しかし、ここで注意すべき点は、過去12年間に、国民年金加入者である第1号被保険者に占める免除者の比率も2割台から4割台に倍増していることである。
そして、このことが納付率の上昇にもつながっている。次ページでは、そのカラクリを解き明かしていく。