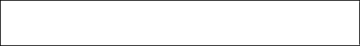特に都市部の若者を中心に、シェアハウスという新たな居住形態が受け入れられ始めたのはここ数年のことだ。自身の給与では到底暮らせない都内一等地で、安くて、楽しく、オシャレな生活を送っている者も少なくないだろう。しかし、そうした華やかさから身を潜めるかのように、「貧困」のループに陥った者たちが「新たな共同体」を築き上げるための場になりつつもある。
社会学者・開沼博は、都内を中心に13件のシェアハウスを経営する増田に密着。40代の無職男性・佐藤の死をきっかけに、遺品整理業者が死を「漂白」する現実、さらにはネズミ講が蔓延する実態といった、現代社会を象徴する夢と孤独の輪郭までを映し出していることに気がつく。
シェアハウスとは、「新たな共同性」の拠り所となるユートピアなのか、それとも、孤独と貧困を象徴するタコ部屋に過ぎないのか。連載は全15回。隔週火曜日更新。
趣味の延長でシェアハウス経営がスタート
突然、増田の携帯が鳴った。着信を見ると、先月から勤める新人スタッフの末吉からだ。
「ちょっとやばいことになりまして……住民の方、亡くなりました」
増田がシェアハウスの運営を始めたのは5年前のこと。最初は自分自身で少し広めの家を借り、使わない部屋を活用するために、インターネット上に多数存在する無料の“ルームシェア仲間募集掲示板”に書き込みをし、応募してきた人に貸し出す“趣味”に過ぎなかった。
しかし、自分がその物件から引っ越そうとした際、同居するシェアメイトは住み続けることを望んだため、自分が抜けた部屋に別の人を入れることとなる。それが、“事業”としてシェアハウス経営を始めたきっかけだった。
 部屋に置かれた2段ベッドは薄い布で覆われている
部屋に置かれた2段ベッドは薄い布で覆われている
最初の物件に住んでいた時から、「空室が出たら、その赤字を被るのは自分だから」と、シェアメイトに対して賃料を均等に割った金額を請求するのではなく、やや割高な料金を設定していた。だが、募集をかければ入居希望者が殺到し、結果として自分の家賃すら支払わないで済む状態が続いていた。そのため、自分が後にした部屋に新しい人が住むことになり、その住民から家賃を受け取ることができれば、結果的に利益が生まれることになる。
増田はその仕組みを次の物件でも試すことにした。今度は、自分が家賃を負担しなくても常に黒字が出るように、部屋ごとの単価を引き上げることを考えて、少し広めの部屋に2段ベッドを2つ置き、一人当たり3万5000円の家賃を設定した。すると、これまで1部屋6万円程度で貸していたものが、1部屋で常に2人分(=7万円)もしくは3人分(=10万5000円)、時期によっては4人分(=14万円)の売上が上がるようになる。
調理器具やエアコン、衣装ケース、テレビなど最低限の生活家具も揃え、「カバン1つ、3万5000円あれば明日から東京生活」とうたって“ルームシェア仲間募集掲示板”で募集を始めると、大量の応募者がやってきた。